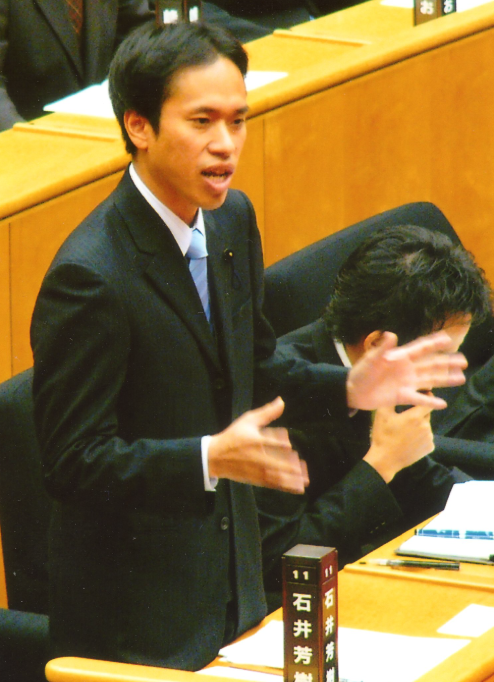県政報告
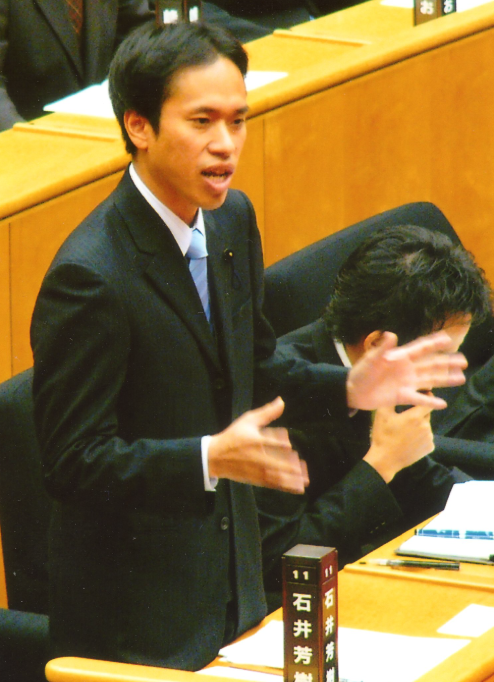
令和5年6月定例会(第2号)
2023年6月21日
(主な質疑)
- 午前十時開議
◯議長(石井芳樹君) ただいまから会議を開きます。
直ちに議事日程に従い会議を進めます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
日程第一 一般質問並びに第八十一号議案令和五年度愛
知県一般会計補正予算から第九十九号議案愛
知海区漁業調整委員会の委員の選任について
まで
- 2: ◯議長(石井芳樹君) 第八十一号議案令和五年度愛知県一般会計補正予算から第九十九号議案愛知海区漁業調整委員会の委員の選任についてまでを一括議題といたします。
これより一般質問並びに提出議案に対する質問を許します。
通告により質問を許可いたします。
新海正春議員。
〔八十二番新海正春君登壇〕(拍手)
- 3: ◯八十二番(新海正春君) 皆さん、おはようございます。
それでは、自由民主党愛知県議員団を代表いたしまして、順次質問をしてまいります。
質問に先立ちまして、去る六月二日の大雨によってお亡くなりになられた方に対しまして、心から御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
我々、自由民主党愛知県議員団は、この大雨による道路、河川、港湾などの公共土木施設や農地、農業用施設、山地、林道など森林に係る被害の復旧はもちろん、農業者等への十分かつ迅速な支援や事業者の資金繰りなど、被害を受けた方に寄り添った支援を大村知事に要望したところであり、国に対しても要望活動を行ってまいりたいと思います。
今後も県民の皆様の安全・安心の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
それでは、順次質問をしてまいります。
質問の第一は、行財政運営についてであります。
初めに、県税収入の見通しについてお尋ねをいたします。
我が国の経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む中で、外食や旅行などのサービス消費の回復など、全体として景気は緩やかに回復しております。
先行きについても、雇用・所得環境が改善する下で、緩やかな回復が続くことが期待されておりますが、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。
こうした中、本県の県税収入に大きな影響を及ぼす企業収益の状況でありますが、さきに発表のありました上場企業の本年三月期決算の内容を見ますと、海外経済の減速による影響などから製造業が減益となっておりますものの、コロナ禍からの経済再開が進んだことなどにより、非製造業が牽引したことから、連結経常利益は、全体で僅かに増益となったとのことであります。
一方、来年三月期の業績予想においては全体で増益が見込まれておりますが、製造業を中心に海外経済の先行きに不透明感が残るとも言われております。
そこでお伺いいたします。
このような景気動向などを踏まえ、本年度の県税収入についてどのような見通しをされておられるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、今後の財政運営についてお伺いいたします。
国においては、依然として続くエネルギー、食料品価格の高騰などに、機動的かつ切れ目なく対応し、国民生活と事業活動を守り抜くため、去る三月二十二日に開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、物価高克服に向けた追加策を取りまとめ、二兆二千億円余りの予備費の使用を決定しました。
本県においても、こうした国の動きに呼応し、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受ける県民の皆様や県内の事業者の方々に対する支援を速やかに実施するため、五月補正予算を編成されたところであります。
しかしながら、物価高が続く現下の経済情勢は、先が見通せない状況であります。また、新型コロナウイルス感染症が五類感染症へ移行したことを踏まえ、今後は、本格的に経済活動を回していく施策を展開していく必要があります。
さらには、現在、国において議論が進められております子ども・子育て政策の強化の動きの中で、本県としても、地域の実情に応じた独自の取組を着実に実施していくなど、適切な対応を図っていく必要があります。
一方で、本県の今年度当初予算では、千四百二十四億円もの多額の基金の取崩しが計上されており、基金の取崩しに依存する予算編成が継続しております。社会経済情勢の変化に対応しながら、新たな政策課題や県民の多様なニーズに的確に応えていくためには、一層の財政の健全化に配意しつつ、財政運営に取り組んでいく必要があると考えます。
そこでお伺いいたします。
今後の財政運営について、どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
質問の第二は、安全・安心な暮らしの実現についてであります。
まず、新型コロナウイルス感染症の五類感染症移行後の対応についてお尋ねいたします。
二〇二〇年一月二十六日に、県内で最初の新型コロナウイルスの感染者が確認されてから、三年五か月ほどが経過しました。
この間に、医療機関や高齢者施設等の現場で、昼夜を惜しんで献身的に従事いただいた医師、看護師、介護職員等の皆様をはじめ関係者の皆様には改めて感謝を申し上げます。
さて、新型コロナウイルスの新規陽性者数でありますが、二〇二〇年二月から四月にかけての第一波以降、波を経るごとに増加し、二〇二二年夏の第七波では、新規陽性者数と入院患者数が過去最多となるなど、大変厳しい状況となりました。
その後の第八波では、昨年末から今年の初めにかけて感染者数は大きく増加したものの、その後減少に転じ、四月末まで落ち着いた状況が続いていましたが、五月以降、再び増加傾向にあります。
第五波のデルタ株までと比べ、第六波からのオミクロン株では感染力が強くなった一方、人工呼吸管理などを必要とする患者の割合が低下をし、ワクチン接種が進んだことや感染による免疫の獲得に加え、治療薬の開発などもあり、重症化率や死亡率は下がってきました。
そうした中、今年五月八日以降、国は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを、これまでの新型インフルエンザ等感染症から五類感染症へ変更しました。これにより、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染防止対策は終了し、行政が様々な要請、関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な取組を基本とする対応に転換されたところであります。
感染状況の把握についても、これまでは全数把握として、毎日の新規陽性者数が公表されていましたが、定点医療機関からの報告による週一回の定点把握に変更となり、また、保健所による入院勧告や外出自粛要請などはなくなりました。
さらに、医療提供体制について申し上げますと、限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による通常の対応に移行することになりました。
しかしながら、五類感染症になったからといって、新型コロナウイルスがなくなったわけではなく、今後も一定の流行が続くことが予想されておりますので、引き続き、県において新型コロナウイルス感染症としっかりと向き合い、適切に対応していくことが何より重要であると考えます。
そこでお伺いいたします。
五類感染症移行後の新型コロナウイルス感染症への対応について、県としてどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、公共工事における働き方改革の推進についてお伺いいたします。
少子・高齢化の進行により、生産年齢人口が減少し、労働力不足が深刻化する中、休める環境づくりや生産性の向上など働き方改革の取組は大変重要であります。
休める環境づくりについては、本県では、国民全体のワーク・ライフ・バランスの充実と日本経済の活性化の実現を目指す休み方改革プロジェクトに本年度から取り組んでおります。
発信者である本県がしっかりと改革に取り組み、全国知事会に設置されたプロジェクトチームのリーダーである愛知県知事が他地域を牽引することで、全国の全ての業種に休み方改革が広がっていくことを期待しております。
今の若い人たちは、給料もさることながらプライベートの時間を重視しており、休みも確保できないような業界を敬遠しがちです。特に、建設業界の状況は深刻であり、知り合いの経営者からも、同様の理由で人材確保に苦労しているという声が多く届いております。
そこで、公共工事の担い手であり、地域の守り手でもある建設業の休める環境づくりに目を向けますと、県発注の土木工事においては、施工時期の平準化や週休二日制の導入など、しっかりと取り組まれていることが確認されます。
しかし、市町村発注工事においては、国が三月に公表した入札契約の適正化の取組状況に関する調査結果によれば、二〇二二年十月の時点で、工期の設定に当たり休日を考慮している市区町村は全国で五割未満に留まっており、本県の市町村においても、全国同様、非常に低い割合とのことでした。
休める環境づくりは、建設現場に若い人の入職を促す効果もあり、市町村を含め、県全体で取り組んでいく必要があると考えます。
また、建設工事における現場の生産性の向上については、情報通信技術、いわゆるICTの活用が有効と言われています。ICT建設機械を用いれば、熟練者に頼らなくても、経験年数の浅い方や少人数でも精度よく短時間に作業を進めることができます。
このため、県発注の土木工事では、二〇一六年度からICT建設機械を用いた施工が導入され、大規模な工事では活用していると聞いていますが、小規模な工事においては導入が進んでおらず、市町村発注工事も含めて普及させていく必要があると考えております。
建設業への罰則付時間外労働の上限規制適用が、二〇二四年四月と目前に迫る中、現場の生産性を向上させることで長時間労働を解消するとともに、休める環境を整えるなど、働き方改革を進めることは、建設業の持続的な発展にもつながるものと認識しております。
そこでお伺いいたします。
市町村を含め、県全体として公共工事における働き方改革にどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、交通死亡事故の抑止対策についてお伺いいたします。
二〇二二年の交通事故死者数は百三十七人で、四年連続で全国ワーストを免れることができました。
これも県民の皆様や、愛知県、交通安全推進協議会、実施機関、団体の皆様が一体となって各種交通安全対策を推進してきたことによる一定の成果であると考えております。
しかしながら、依然として交通事故によってこれだけ多くの人命が奪われており、昨年は七年ぶりに対前年比で増加となるなど、交通事故のない社会の実現に向けては道半ばにありますので、手を緩めることなく交通死亡事故の抑止対策を一層強力に推進していかなければなりません。
本年の交通死亡事故の発生状況につきましては、五月末現在の交通事故死者数は六十三人で、前年と比べ五人増加しており、大阪府に次いで全国ワースト二位となっております。
二月以降、交通事故死者数は対前年比で増加傾向が続き、三月には十九人もの方がお亡くなりになり、三月としては、過去十年間で最多となるなど、交通事故情勢は極めて厳しいものと認識しております。
本年も上半期が終わろうとしておりますが、年間の交通事故死者数を対前年比で減少に転じさせるには、残された半年間でいかに効果的な対策を実施できるかにかかっています。
今後の展望として、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが五類感染症に変更されたことを受け、社会経済活動の活性化など、県民活動が大きく変わってきており、人流、物流の回復に伴う交通事故の増加が懸念されます。
さらに、例年、下半期は交通死亡事故が多発する傾向にあり、夏の行楽期にはレジャーや観光等に伴う事故、日没が早まる秋以降には夕暮れ時の事故等の多発が懸念されます。
こうした中であっても、最も大切な県民の命を交通事故から守っていくためには、厳しい交通事故情勢をただ悲観するのではなく、想定される様々なリスクに対してどのような対策を講じていくのかということを前向きに検討していかなければなりません。
悲惨な交通死亡事故を一件でも多く減らし、第十一次愛知県交通安全計画に定められた二〇二五年までに二十四時間交通事故死者数を百二十五人以下にするという目標を達成するためには、警察をはじめ、県全体が一丸となって取り組むことが重要であります。
そこでお伺いいたします。
交通死亡事故の抑止対策をどのように進めていかれるのか、警察本部長の御所見をお伺いいたします。
次に、特別支援学校における長時間通学についてお伺いいたします。
特別支援学校においては、これまでも過大化による教室不足や長時間通学が課題となってまいりました。昨年の六月議会では、我が党の代表質問において、尾張北西地区の知的障害特別支援学校における教室不足について取り上げ、大村知事から校舎の増築や近隣の肢体不自由特別支援学校への知的障害部門の設置などによる改善をスピード感を持って進めていくとの御答弁をいただきました。
そして、現在、いなざわ特別支援学校の教室不足については校舎増築を、一宮東特別支援学校の教室不足については、敷地内に増築の余地がないということで、肢体不自由の小牧特別支援学校への知的障害部門の校舎増築を進めておられます。
知事は、全ての人が輝く愛知を目指し、障害のある子供たちの教育環境の充実に取り組まれる中で、特別支援学校の新設を積極的に進めてこられました。その結果、児童生徒数の増加が著しい知的障害特別支援学校では、教室不足の解消が図られるとともに、学校数が増えたことで、長時間通学の改善も進み、大変感謝しております。
一方、子供の数が知的障害ほど多くない肢体不自由特別支援学校については、市立学校を含めて県内十二校で、二十三校ある知的障害特別支援学校と比べて約半数であり、通学区域が広いため、長時間通学とならざるを得ない地域があります。この点については、スクールバスの台数を増やして送迎ルートを短縮するなどの工夫をしていただいておりますが、根本的な解決を目指し、通学距離を短くしなければ解消できないケースも少なくないと思います。
特別支援学校には、小学校段階の児童も通っておりますので、低年齢で障害のある児童が、長時間バスに揺られて通わなければならないのは、身体的にも大きな負担です。また、肢体不自由の子供を持つ保護者が特別支援学校に通わせたいと思っても、自宅から遠過ぎて通えないケースもあると聞いておりますので、できるだけ早い解決を望みます。
そこでお伺いいたします。
肢体不自由特別支援学校における長時間通学の解消に向けて、どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
質問の第三は、活力と魅力あふれる愛知の実現についてであります。
まず、子ども・子育て政策の強化についてお尋ねいたします。
二〇二二年の全国の出生数は八十万人を割り込み、二〇一七年に公表されていた予測より八年も速いペースで少子化が進んでおり、静かな有事とも言える状況にあります。
このため国は、少子化対策はこれ以上放置できない待ったなしの課題であるとした上で、次元の異なる少子化対策として、若い世代の所得を増やすこと、社会全体の構造、意識を変えること、全ての子育て世帯を切れ目なく支援することを理念として示し、今後三年間で加速化して取り組むものとして、多岐にわたる子ども・子育て支援政策を打ち出し、政府が一丸となって実施に向け取り組んでいるところであります。
ここで、本県の少子化の現状を見ますと、二〇二二年の出生数は五万一千百五十一人で過去最低を更新し、ピークであった一九七〇年代の半分以下となっております。二〇二二年の合計特殊出生率は、全国が一・二六であるのに対し、本県は一・三五と〇・〇九ポイント高く、全国二十六位であり、大都市圏としては、比較的高いとはいえ、安定的に人口を維持できると言われている二・〇七を大きく下回る状況が続き、少子化の状況は年々深刻さを増しております。
子供は社会の宝であり、急激な少子化は社会の活力の低下を招きます。社会の持続可能な発展のためにも、一人一人が多様な考え方を互いに尊重しながら、未来への希望を持てる社会の実現を目指し、社会全体で子供の成長や子育てを応援していくことが重要だと考えます。
県はこれまでも、日本一子育てしやすい愛知の実現に向け、妊娠・出産期からの切れ目ない支援や、待機児童対策をはじめとして、様々な子ども・子育てに関する支援の充実に取り組んできました。その結果、二〇二二年の保育所等の待機児童数は、近年のピークであった二〇一九年度よりも八割減少し五十三人となるなど、一定の効果を上げております。
しかしながら、若者の結婚や出産、子育てに対する負担や不安を取り除き、少子化に歯止めをかけるためには、従来の支援から一歩先へ進んだ支援が必要なのではないかと考えます。
このような中、県は先日、少子化対策パッケージとして、多様な施策を取りまとめて示されました。
そこでお伺いいたします。
本県における子ども・子育て政策の強化について、県としてどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、次期愛知県観光振興基本計画の策定について、お伺いいたします。
観光庁の最新の統計によれば、県内における日本人の延べ宿泊者数は、全国旅行支援などの効果もあり、昨年九月以降、七か月連続でコロナ禍前の二〇一九年実績を上回るなど、順調に推移しております。
私の地元、岡崎市でも、どうする家康岡崎大河ドラマ館には、連日多くの人が訪れ、三月に岡崎市が実施したアンケートでは、約四割が県外からの来場者であったと伺っております。五月十一日には来館二十万人を達成し、観光需要の着実な復活と、武将観光の高い集客力を改めて感じたところであります。
また、インバウンドについても、四月二十九日に入国制限などの水際措置が終了したため、中部国際空港における国際線の運航再開や増便が進むにつれて、力強く回復していくものと期待されます。
一方、観光を取り巻く環境は大きく変化しています。
個人の趣味や嗜好が一層多様化、高度化し、現地でしか得ることができない満足度の高い体験など、観光コンテンツの質が重視されるようになっているほか、観光地で休暇を楽しみながら働くワーケーションや、ビジネスとレジャーを組み合わせた造語であり、出張先で滞在を延長して余暇を楽しむブレジャーなど、新たな旅のスタイルも生まれています。
また、デジタル化が進み、SNSを利用した旅行前の情報収集や旅行後の投稿に加え、宿泊施設や観光施設の予約、決済についても、スマートフォンで完結する環境が急激に整いつつあります。
さて、本県の今後を展望しますと、今年度中には、ジブリパークにもののけの里と魔女の谷の二エリアが加わり、いよいよフルオープンを迎えるほか、二〇二五年には、愛知国際アリーナのオープン、そして二〇二六年には、アジア競技大会、アジアパラ競技大会の開催を控え、国内外からの注目度が一段と高まり、多くの旅行者を迎えることとなります。
こうした状況の中、本県の観光振興基本計画であるあいち観光戦略二〇二一─二〇二三が、今年度末に計画期間の満了を迎えます。
旅行需要が回復し、旅行者獲得のための地域間競争が一層激しくなる中で、次期計画の策定に当たっては、観光を取り巻く環境の変化に対応しつつ、国内外から多くの人を呼び込む大規模プロジェクトの効果を最大限に生かして、武将などの愛知の魅力をさらなる観光誘客につなげていくことが求められます。
そこでお伺いいたします。
次期愛知県観光振興基本計画について、どのような考えで策定していかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、あいち森と緑づくり事業についてお尋ねいたします。
森林は、水源の涵養、土砂災害の防止、木材の生産、生物多様性や環境の保全など様々な機能を有しております。また、都市の緑にはヒートアイランド現象の緩和や心の安らぎなど、心身の快適性を高める機能があり、カーボンニュートラルやSDGsの実現に向けた意識の高まりとも相まって、森林の保全、整備や木材利用の促進に対する県民の期待が高まっています。
こうした中で、県は、県民の皆様にあいち森と緑づくり税を御負担いただき、山から街まで緑豊かな愛知を目指して、二〇〇九年度からあいち森と緑づくり事業に取り組んでおります。
本事業は十年計画で実施されており、現在、二〇一九年度から始まった第二期の取組が進められております。今年度はその中間年に当たることから、この五月に二〇一九年度から二〇二一年度までの三年間の事業実績や成果、県民の皆様の意見を取りまとめた事業評価報告書が公表されております。
この報告書を拝見したところ、県民の皆様へのアンケート調査では、約九割の方が健全な森や緑の継承が必要で、あいち森と緑づくり税や事業の継続に賛成と回答しています。また、市町村や森林所有者等へのアンケートでも事業の効果を実感しているとの結果が得られております。
実際に私の地元、岡崎市においても、道路沿いの間伐が進んだことで、日が差し込み、明るく見通しがよくなり、車の運転がしやすくなった。台風などの倒木による停電の心配が減った。などの声を聞いており、地域から大変喜ばれております。
また、本事業では、木材利用を支援する木の香る都市(まち)づくり事業も行われており、木材を利用した施設を目にすることも多くなったと実感しております。
岡崎市内でも商業施設内のテナントや地域住民の交流施設の木質化などで本事業の支援を受けており、これら木材利用の進展が見込まれる施設で、しっかりと木材を使い、PRしていくことが重要であります。木造・木質化に対する県の支援は引き続き効果的に進めていただきたいと思います。
このように、本事業は県民の皆様や市町村、事業関係者等から非常に高い評価を受けており、我が党としては、今後も着実に取組を進めていただきたいと考えております。
そこでお伺いいたします。
第二期の事業計画期間における成果をどのように評価し、今後、どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、アジア競技大会、アジアパラ競技大会について、お伺いいたします。
大規模な国際スポーツ大会をめぐっては、運営の在り方などについて様々な意見もある中、春のワールド・ベースボール・クラシックの盛り上がりのように、スポーツの持つ力は、これからも私たちに多くの感動と勇気を与えてくれることは間違いありません。
東京二〇二〇大会の開催から約二年がたとうとしていますが、既に二〇二四年のパリオリンピック・パラリンピック競技大会の代表を選考する大会も始まっています。
また、私の地元、岡崎市出身のバレーボールの石川兄妹をはじめ、多くの本県ゆかりのアスリートが各競技で奮闘しており、今後の国際大会における活躍に胸を膨らませているところであります。
さて、二〇二六年に愛知・名古屋で開催される第二十回アジア競技大会及び第五回アジアパラ競技大会も、開催まで残すところ三年三か月余りとなりました。
大会期間中には、国内はもちろん、アジア各国から多くの観客や観光客が本県を訪れることが予想されます。大会が盛り上がることで、国内外から注目が集まり、この地域のさらなる発展につながることを心から期待しております。
現在、組織委員会では、競技をはじめ、選手の輸送や宿泊などの大会運営に向けた準備に鋭意取り組んでいることと思います。
一方で、東京二〇二〇大会のスポンサー選定等における不祥事をはじめとした様々な問題により、スポーツの価値が大いに毀損され、世間に不信や失望を与えるなど、国際スポーツ大会の開催に大変厳しい視線が向けられております。
さらに、国際的な原材料価格の上昇や円安等による物価の高騰が社会経済活動に大きな影響を及ぼしており、愛知・名古屋大会を取り巻く環境は、開催が決定した二〇一六年から大きく変化しております。
こうした中、組織委員会の会長である大村知事は、本年三月二十七日に開催された組織委員会の理事会において、マーケティング代理店の決定方法や、大会の収支予算の見通しの厳しさを踏まえたメイン選手村の整備取りやめの方向性など、愛知・名古屋大会が新たな国際スポーツ大会の在り方を示していくための大きな一歩と言える決断を示されました。
さらに、先週十五日に開催された理事会では、競技会場の多額の仮設整備費の抑制を図るため、県外施設への競技会場変更について決議される等、大会の開催実現に向け、関係者との十分な調整を行い、着実に準備を進めています。
今後も、しっかりと透明性や公平性を確保しながら、課題に一つ一つ取り組んでいくことが不可欠であり、そうした取組により、世界に誇れる大会、語り継がれる大会としてほしいと考えております。
そこでお伺いいたします。
今後の組織委員会の対応や大会準備等にますます注目が高まっていく中で、愛知・名古屋大会の成功に向けた取組をどのように進めていかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
質問の第四は、新しい時代に飛躍する愛知づくりについてであります。
まず、社会状況の変化を踏まえた文化芸術施策の推進についてお尋ねいたします。
二〇二〇年以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、文化芸術イベントの中止や規模の縮小、人々の行動自粛等により、文化芸術を支える個人や、文化芸術団体等による活動の減少など、文化芸術分野においても甚大な影響を与えました。
また、少子・高齢化の進行による人口減少は、文化芸術の担い手の減少につながるとともに、公演の鑑賞者や美術館の入館者の減少にも影響し、需要の減少や市場の縮小が見込まれています。
これからの文化芸術施策の推進に当たっては、こうした社会状況の変化を着実に捉え、反映させていくことが重要です。
こうした中、政府は、二〇二三年三月二十四日、文化芸術基本法第七条第一項に基づき、文化芸術推進基本計画(第二期)─価値創造と社会・経済の活性化─を閣議決定しました。
この計画では、新型コロナウイルス感染症をはじめとした文化芸術施策を取り巻く状況の変化を踏まえ、コロナ禍からの早期回復を図りながら、文化芸術の本質的価値及び社会的・経済的価値を創出して未来を切り開くための四つの中長期目標と、特に推進すべき七つの重点取組を示しております。
さらに、それらの取組の展開に当たって意識すべき三項目として、文化施設等のハード及びデジタル空間を含めた場の整備、文化芸術に関する創造的活動等のソフトの充実、文化芸術の担い手を確保し、育成、養成するための人材の育成、養成が掲げられております。
その中でも、ハードである文化施設については、集客力を有し、地域の活性化や大きな経済効果をもたらす施設であるとして、二〇二二年の博物館法改正を踏まえ、文化芸術の価値を生かしながら、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業、その他の関連分野とも適切に連携し、地域に新たな価値を提供すべく、機能強化を図ることとされております。
本県においては、文化芸術施策の中核的施設として、愛知芸術文化センターと愛知県陶磁美術館が設置されており、文化芸術の本質的価値を生かして、社会的・経済的価値を創出していくために果たす役割は、今後ますます重要になると考えます。
例えば、交通の便がよく集客力のポテンシャルが高い芸術文化センターについては、再開発が進む栄地区のにぎわいにどのように参画、貢献していくのか、また、陶磁美術館については、ジブリパークに近いという立地を生かし、周辺自治体や近隣施設との連携をどのように進めていくのかなど、検討すべき課題は多いと考えます。
そこでお伺いいたします。
文化芸術施策の推進に当たっては、地方自治体の果たす役割が大きいと考えますが、本県としてどのように取り組んでいくのか、また、その中でも、本県の文化芸術の拠点である芸術文化センター等文化施設における課題に対してどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
最後に、あいちモビリティイノベーションプロジェクト、空と道がつながる愛知モデル二〇三〇についてお伺いいたします。
県では、二〇二四年十月にオープンを予定しているSTATION Aiの二階に、本県にゆかりのあるイノベーティブな事業を興した起業家、経営者の業績を伝える産業偉人展示施設を整備されるとのことです。
本県を代表する企業でありますトヨタ自動車を興した豊田喜一郎氏は、欧米の産業構造の変化を実感するとともに、将来の自動車産業の必要性を見据え、豊田自動織機の中に現在のトヨタ自動車の基となる自動車部を作ったと言われています。
このように、愛知の先人たちは、時代の変化に対応し、消費者のニーズを踏まえた新技術やサービス、さらには新たな産業を創出してきました。現在、愛知県が世界有数のモノづくり産業の拠点となっているゆえんであります。
現在、社会は、少子・高齢化の一層の進行に加え、IoT、人工知能の急速な発達、カーボンニュートラルへの対応など新たな課題に直面しています。
また、本県の基幹産業である自動車産業においても、通信機能を生かしたサービス、自動運転、カーシェアリング及び電気自動車を指すCASEといった概念や、様々な交通手段を最適に組み合わせて一つの移動サービスとして捉えるMaaSといった新しい概念が生まれ、まさに百年に一度の大変革の時代を迎えています。
本県が引き続き日本の成長エンジンとして我が国の発展を強力にリードしていくためには、変化に的確に対応し、この変革期を乗り越えていかなければなりません。
こうした中、本県では、昨年十二月に、愛知発のイノベーションを絶え間なく創出していくための新たな仕組みとして、革新事業創造戦略が策定されました。この戦略では、民間提案を起点として、社会課題の解決と地域活性化を図る官民連携プロジェクトの創出を目指しています。
そして、この枠組みの第一弾として、新しいモビリティー社会の実現を目指す、あいちモビリティイノベーションプロジェクト、空と道がつながる愛知モデル二〇三〇が立ち上がり、知事御出席の下、民間企業各社との連携協定締結式とプロジェクトチームの第一回会合が開催されたところです。
そこでお伺いいたします。
このイノベーションにより、どのような社会を目指し、その実現に向け、どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
以上、自由民主党愛知県議員団を代表して、県政各般にわたる様々な課題について質問をしてまいりました。明快な御答弁を期待いたしまして、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔知事大村秀章君登壇〕
- 4: ◯知事(大村秀章君) 自由民主党愛知県議員団の新海正春総務会長の質問にお答えをいたします。
初めに、県税収入の見通しについてのお尋ねであります。
本年度の県税収入は、企業収益の回復による法人二税の増などを見込みまして、昨年度の当初予算額から九百七十八億円増収の一兆二千四百六十七億円を計上したところであります。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する前の二〇一九年度決算額一兆二千六億円の水準を回復するものの、懸念材料であります海外景気の下振れ、物価上昇や金融資本市場の変動等の影響などから、慎重な見通しを立てている企業が多く、昨年度の県税最終予算額一兆二千八百四十五億円と比較をいたしますと、三百七十八億円の減収を見込んで計上しております。
こうした中で、法人二税に影響を及ぼします上場企業の本年三月期決算の連結経常利益の状況を見ますと、全産業ベースは前期比一%の増でありましたが、本県の主要産業であります自動車産業をはじめとした製造業全体では、前期比四%の減となっております。
また、海外景気の下振れなどによる、先行きの不透明感も強く、今後の企業業績に与える影響についても懸念をされます。
まだ年度が始まったばかりでもありまして、現時点で県税収入を見通すことは困難でありますので、今後の企業収益の動向に十分注意を払いながら慎重に税収を見極めてまいりたいと考えております。
続いて、今後の財政運営についてであります。
本年度の当初予算編成におきましては、減債基金の任意積立分九百九十九億円と財政調整基金四百二十五億円を合わせまして、千四百二十四億円もの基金の取崩しを計上せざるを得ず、単年度の歳入だけで歳出を賄うことができない状況が続いておりまして、本県の財政運営は依然として厳しい状況であります。
今後も、物価高騰の動向が見通せない中で、海外景気の下振れや金融資本市場の変動等の影響が懸念される現状におきましては、年度途中の不測の財政需要へ機動的に対応するための手元資金を確保していくことが重要であると考えております。
また、来年度に向けましては、二〇二五年にかけて団塊の世代が七十五歳以上の後期高齢者となることに伴いまして、医療、介護等の扶助費の増加が避けられないことなどから、本年度の当初予算におきまして多額の取崩しを計上した基金残高の回復に努めていく必要があると認識をいたしております。
このため、まずは、本年度内の財源確保にしっかりと取り組むとともに、昨年十二月に策定をいたしましたあいち行革プラン二〇二〇後半期の取組に沿った、歳入歳出両面にわたる行財政改革の取組を着実に進めてまいります。
あわせまして、愛知の経済・産業力をさらに強くする施策を推進し、産業の活性化や雇用の維持、拡大を図ることで税源の涵養につなげ、健全で持続可能な財政基盤の確立に取り組んでまいります。
次は、新型コロナウイルス感染症の五類感染症移行後の対応についてのお尋ねであります。本県では五類感染症移行に伴う国の方針を踏まえまして、これまで実施をしてきました感染症対策について見直しを行いましたが、引き続き、県民の皆様の生命と健康を守ることを最優先して取組を進めていく必要があると考えております。
そのため、相談体制につきましては、県民の皆様に安心して相談いただけるよう、受診・相談窓口を九月末まで、ワクチンに関する相談窓口は来年三月末まで継続するということといたしました。
また、ワクチン接種につきましては、五月八日から六十五歳以上の高齢者等を対象とした追加接種が始まっておりまして、希望される皆様が速やかに接種を受けられるよう、市町村、医療機関、医師会等関係団体の皆様と連携を図り、取組を進めてまいります。
また、医療提供体制を引き続き確保するため、入院のための確保病床を維持するとともに、新たに外来診療を始める医療機関に対する助成制度を拡充するなど、幅広い支援を九月末まで行っているところであります。
外来対応医療機関、これまで診療検査医療機関と言っていたコロナの、要するに患者さんといいますか、発熱した方を診ていただく医療機関につきましては、五類移行前の四月には二千二百七十二か所、全県で、二千二百七十二か所でありましたが、これをできるだけ増やしていただけるようにお願い、要請をさせていただいておりまして、現時点では二千四百十五か所と、百四十三か所の増加となっておりまして、引き続き、こうした発熱患者さんに対応いただける医療機関を順次拡大してまいります。
そして、これまで行政が担ってきました入院調整につきましても、医療機関による調整へ円滑に移行できるよう、入院調整・相談窓口を五月八日から新たに設置いたしまして、医療機関からの相談に対応しております。
さらに、本県独自の取組といたしまして、感染した妊婦の方の分娩対応や、高齢者施設等への緊急時の往診、訪問看護を行う医療機関への支援にも引き続き取り組むなど、医療提供体制に万全を期してまいります。
五類感染症への移行後におきましても、感染状況と入院患者の状況を注視しながら、県民の皆様の生命と健康を守ることを最優先し、新型コロナウイルス感染症対策にしっかりと取り組んでまいります。
続いて、公共工事における働き方改革の推進についてお答えをいたします。
道路や河川などの社会インフラは、日本一元気な愛知の産業を支えておりまして、その整備や維持を担う建設業が持続的に発展できるよう、働き方改革を進めることは大変重要であります。
このため、本県では市町村と共に愛知県公共事業発注者協議会を設置いたしまして、働き方改革の推進に向けて、歩調を合わせて、課題解決に取り組んでおり、時間外労働の上限規制が適用される二〇二四年度を目途に、生産性の向上や労働環境の改善を進めております。
生産性の向上につきましては、本県では中小規模の工事など、より多くの工事でICTを活用できるよう、関連する基準の緩和や工種の拡大を実施してまいりました。今後は導入の進んでいない市町村の発注工事におきましても、ICTが普及するよう支援をしてまいります。
次に、労働環境の改善につきましては、まずは休める環境づくりが重要でありまして、休日を考慮した適正な工期での発注を、全ての市町村が二〇二四年度までに実施するよう働きかけております。
県発注の土木工事におきましては、今年度から、原則週休二日制としておりまして、さらに年次有給休暇の取得率が高いなど、休み方改革マイスター企業に認定された企業に対しまして、インセンティブを導入してまいります。
今後も本県がリーダーシップを発揮いたしまして、市町村や建設業界と共に、公共工事における働き方改革を推進し、建設業のさらなる発展につながるよう、しっかりと取り組んでまいります。
次に、特別支援学校における長時間通学についてであります。
私は、二〇一一年に知事に就任して以来、二〇一四年のいなざわ特別支援学校を皮切りに、昨年のにしお特別支援学校、この春の千種聾学校ひがしうら校舎まで、これまでに五校を新設するとともに、設楽町と田原市への分教室の設置、みあい特別支援学校の校舎増築を行い、合わせて八校で取組を進めてまいりました。
校舎増築につきましては、現在、いなざわ特別支援学校と小牧特別支援学校、二校においても進めております。さらに、市立の特別支援学校につきましても、財政支援を行いまして、五校の取組を進めさせていただきました。ということで、全部合わせますと特別支援学校の新設、増築等で十五校、この十数年余りで十五校、取組をさせていただいております。
こうした取組によりまして、知的障害の特別支援学校を中心に、教室不足と、長時間通学を改善することができました。
一方、議員お示しのとおり、肢体不自由の特別支援学校では、通学に時間のかかるケースもあると承知をいたしております。例えば、名古屋市港区の港特別支援学校へ通学している子供のうち、緑区、名東区、天白区、豊明市、日進市、東郷町の在住者は、スクールバスの乗車時間が六十分を超えております。こうした長時間通学をできる限り早期に解消するため、新たな肢体不自由特別支援学校の設置を検討してまいりましたところ、名古屋市から、天白学校体育センターを候補地としてはどうかという強い提案、要望がありまして、港特別支援学校の長時間通学を解消するのに適切な立地でありますので、この地に新たに特別支援学校を設置することといたします。本議会におきまして、二〇二七年四月の開校を目指し、基本設計費などの補正予算をこの六月議会でお願いしているところでございます。
今後も、障害のある子供たちが少しでも身近な通いやすい学校で学び、地域とのつながりの中で成長していけるよう、教育環境の充実にしっかりと取り組んでまいります。
続きまして、子ども・子育て政策の強化についてのお尋ねであります。
本県では、少子化の克服に向けまして、二〇二〇年三月に策定をいたしました、あいちはぐみんプラン二〇二〇─二〇二四に基づいて、若者の就学、就職、結婚、妊娠、出産、子育てまで、ライフステージに応じた切れ目ない支援を行ってまいりました。
しかしながら、年間出生数がピーク時の半分以下にまで落ち込むなど深刻な状況が続いておりまして、少子化対策は、国、地方を挙げて取り組まなければならない最重要課題であると認識しております。
このため、本年四月には小倉少子化対策担当大臣に私から直接、子供政策充実に向けた要請を行わせていただきました。
また、国におきましては現在、次元の異なる少子化対策について財源を含めた議論が進められておりますが、愛知県としてできることから国に先行して取り組んでいくため、四つの方針の下、本県独自の少子化対策パッケージを取りまとめたところであります。
方針の一つ目は、男性の育児休業取得を促進する中小企業等への支援、二つ目が、低所得の子育て世帯への相談支援と合わせた経済的サポート、三つ目が、様々な問題を抱える妊産婦の方への精神的、経済的なサポート、四つ目が、結婚を希望する男女の出会いサポートの強化でありまして、これらの方針に基づく事業実施に必要な補正予算をこの議会にも提案させていただいております。
今後、少子化対策パッケージに掲げる事業を着実に進めるとともに、国が強化する子ども・子育て政策内容も踏まえながら、希望する誰もが安心して子供を生み育てることができ、次代を担う子供が健やかに成長することができる社会の実現を目指してまいります。
続いて、次期愛知県観光振興基本計画の策定についてお答えをいたします。
愛知には、三英傑を生んだ歴史をはじめ、全国一を誇るモノづくり産業や、自然、伝統文化など、様々な魅力があります。
今年は議員、御地元の岡崎を中心として、どうする家康という大河ドラマがずっと、毎週、毎週やっておりまして、愛知県のいろんな各地も紹介していただいておりますので、私も大変楽しみに見ておりますが、多くのお客さんが全国からお越しいただいているというふうに承知をいたしております。
こうした本県独自の魅力を観光コンテンツとして磨き上げ、国内外へと売り込んでいくため、これまで三次にわたり観光振興基本計画を策定し、市町村や関連団体、事業者等と連携を密にしながら、愛知の観光の活力を高める施策を総合的に推進してまいりました。
次期計画の期間は、ジブリパークのフルオープン後となる二〇二四年度から、アジア競技大会及びアジアパラ競技大会が開催される二〇二六年度までを予定しておりまして、この三年間は、愛知の観光を大きく飛躍させる大変重要な期間だと認識しております。
このため、国内外から訪れる旅行者により満足度の高い愛知の観光を楽しんでいただけるよう、上質な施設環境や心に響く体験の提供など、観光資源の付加価値をさらに高めていく必要があります。
そして、今後を見据え、観光プロモーションのデジタルシフトを加速させ、国内外から注目される本県の大規模プロジェクトとともに、観光県あいちの魅力を効果的に発信していく必要があります。
さらに、本県が主導する休み方改革によりまして、観光需要の平準化を進め、快適な愛知の観光を実現していくことや、スタートアップを巻き込んだ多様な連携により、新たな観光コンテンツやプロモーション手法の開発などを促していくことも重要だと考えております。
こうした考えの下、外部の有識者の意見を聞きながら、来年二月を目途に計画内容を固め、地域の観光関連産業に元気を与えるとともに、愛知のブランド力を一層高めていく、次期観光振興基本計画を策定してまいります。
次に、あいち森と緑づくり事業についてであります。
第二期の事業計画期間における成果につきましては、公益的機能の発揮や環境保全、カーボンニュートラルの実現などにつながる森林整備や木材利用が着実に進んでいると評価をしております。
間伐につきましては、防災、減災やライフライン確保の観点から、道路沿い等を重点的に実施しておりまして、昨年度までの四年間では延べ百四十八キロメートルの道路沿いの間伐を行っております。
また、木の香る都市(まち)づくり事業では、多くの県民が利用する施設や、高い波及効果が見込まれる施設など四十三件を支援いたしました。
昨日、私は、県の木の香る都市(まち)づくり事業で助成、支援をいたしました名古屋市中川区の烏森オフィスを視察してまいりました。あおなみ線、JR関西線、近鉄線の乗客の目にも留まる木をふんだんに使った木造二階建てのオフィスであります。ちょうど、線路が枝分かれしていくところに造ってあるものでございます。工法やデザインに、様々な工夫が凝らされておりまして、室内も木に囲まれた心地よい空間が広がっておりました。
こうした建物が先導的な役割を果たしまして、木造・木質化がさらに進展していくよう、しっかりとPRをしてまいります。
このほか、里山林の整備や都市の緑づくりにおきましても、県民参加の地域活動が展開されるなど、成果は着実に積み上がっております。
一方で、今回の事業評価では道路沿いの間伐の一層の促進や、伐採木の有効利用、高齢化した人工林の若返りの推進、木材利用の取組拡充など、事業内容に対する様々な御意見をいただいております。
そこで、こうした御意見を踏まえまして、県民の皆様に御理解をいただけるよう、事業内容を十分に検討した上で、引き続き、山から街まで緑豊かな愛知の実現を目指し、あいち森と緑づくり事業を一層推進してまいりたいと考えております。
続いて、アジア競技大会、アジアパラ競技大会についてお答えをいたします。
愛知・名古屋大会の開催準備は、実施競技や競技会場の決定、ホテル等を活用した選手村機能の確保など、具体的な準備を加速していく段階に入ってきたと認識しております。
先週十五日には、私が会長を務める愛知・名古屋大会組織委員会の理事会を開催いたしまして、私どものこの組織委員会の提案協議といたしまして、野球、ソフトボールと、空手の二競技を選定いたしました。
開催都市契約で実施が定められた競技のうち、未決定の七競技はOCA(アジア・オリンピック評議会)が選定することから、速やかに決定がなされるようにOCAと調整を進めてまいります。
競技会場につきましては、OCAとの調整を踏まえ、水泳のうち、競泳、飛び込みと、馬術を東京の会場に変更し、水球を名古屋市のレインボープールに変更することを決定いたしました。競泳、飛び込み会場につきましては、私から東京都の小池都知事に対しまして、東京アクアティクスセンターの使用を要請し、前向きに検討したいとの発言をいただいております。
会場の仮設整備等に多額の費用をかけず、既存施設を有効に活用することで、持続可能な大会の開催運営を目指してまいります。
あわせて、組織委員会の中に、外部有識者で構成するコンプライアンス委員会を設置し、ガバナンス体制の強化も進めてまいります。
愛知・名古屋大会は、華美、過大ではない新たな国際スポーツ大会の在り方を世界に示すとともに、多くの皆様がスポーツのすばらしさを再認識し、アジアとの交流を促進する大会となるよう、県民、市民の皆様はもとより、県内外の関係自治体や大学、企業等としっかり連携し、オールジャパンで大会を盛り上げてまいります。
次は、社会状況の変化を踏まえた文化芸術施策の推進についてのお尋ねであります。
文化芸術は、豊かな人間性や創造性を涵養し、感動や共感、心身の健康などをもたらすとともに、人々の交流や地域活力の源であると考えております。
本県では、新型コロナウイルス感染症の影響や、少子・高齢化による人口減少をはじめとした、昨今の文化芸術を取り巻く社会情勢の変化を着実に捉えつつ、愛知の文化芸術を未来につないでいくため、昨年十二月に、あいち文化芸術振興計画二〇二七を策定いたしました。
本計画では、文化芸術を未来につなぐための人づくりや、ひとしく文化芸術に関わることができる環境の整備等を基本目標に掲げまして、文化芸術団体の後継者育成への支援や、伝統文化を気軽に楽しみ、触れるきっかけの場を提供するイベントの開催等によりまして、文化芸術の力で心豊かな県民生活と活力のある愛知の実現を目指してまいります。
また、文化施設の課題に対しましては、本県における芸術創造の拠点である愛知芸術文化センター等において、社会状況の変化を踏まえ、文化施設として果たすべき役割や、県民の皆様から求められる機能を再整理することが必要と考えております。
本県では、昨年度から、文化施設やその敷地、空間の有効活用に関する調査を実施しております。今後は、その状況も踏まえまして、愛知県美術館及び県陶磁美術館の地方独立行政法人化の可能性や、芸術文化センターにおける民間活力による活性化など、運営手法や経営形態を含めた在り方を見直すための検討に着手し、地域のにぎわいづくりや、新たな人流、人の流れの創出等につなげてまいります。
私からの最後の答弁となりますが、あいちモビリティイノベーションプロジェクト、空と道がつながる愛知モデル二〇三〇についてお答えをいたします。
このプロジェクトは、人口減少などに起因する交通不便地域の拡大や物流クライシスなどの社会課題を解決するイノベーションといたしまして、二〇三〇年頃を目標に、空のモビリティーであるドローンや空飛ぶ車と、陸のモビリティーである自動運転車両とが融合し、同時一体的に制御される新しいモビリティー社会の実現を目指すものであります。
その実現に向けた取組として、今年度内にプロジェクトの方向性を示す全体プランを策定してまいります。
全体プランでは、県内地域の課題や特性を踏まえたビジネスモデル案を検討しながら、新しいモビリティーの社会実装を、どのような手順で進めていくのかを明らかにするロードマップを示してまいります。
また、ドローンから自動運転車両への荷物の受渡しなど、具体的な活用方法を想定した実証実験を実施するほか、大規模イベントへの出展により、新しいモビリティーの有用性や安全性を広く発信するなど、社会受容性の確保に向けた取組も併せて進めてまいります。
本県は、自動車産業、航空宇宙産業、ロボット産業の世界的な集積地でありまして、新しいモビリティーが実装する社会の実現に必要な技術と人材がそろっております。こうした強みを生かしまして、国や関係する機関の協力も得ながら、このプロジェクトを成功させ、ここ、愛知を新たなモビリティー産業の中核都市としていくとともに、その成果を国内外に発信してまいります。
以上、御答弁申し上げました。
- 5: ◯警察本部長(鎌田徹郎君) 交通死亡事故抑止対策の御質問についてお答えいたします。
本年の交通事故死者数は、昨年に比べ増加傾向にあり、横断歩行者妨害に起因する事故が依然として発生しておりますほか、自転車を含む車両運転者の一時不停止や、歩行者の信号無視に起因する事故が増加しており、飲酒運転に起因する重大事故も相次いで発生しておるところでございます。
五月末の交通死亡事故発生状況につきまして、事故死者の年齢層別では、高齢者が約五割を占め、当事者別では歩行者が約四割を占めておりますほか、交差点における死亡事故が大きく増加しておりまして、全体の約六割を占めております。
県警察といたしましては、こうした特徴を踏まえ、車両運転者に対しましては、事故が多発する時間帯や場所を的確に分析した上で、交差点関連違反や飲酒運転など、重大事故に直結する悪質、危険な違反の取締りを強化してまいります。
また、歩行者に対しましては、横断時における横断歩道の利用や安全確認の徹底、反射材の着用など、自らの安全を守る行動を促す広報啓発活動を推進してまいります。
さらに、交通事故多発交差点における道路管理者と連携した安全対策や、歩車分離式信号をはじめとした交通安全施設の整備等にも取り組んでまいります。
これらの交通死亡事故抑止対策につきまして、自治体をはじめ、関係機関、団体等と緊密に連携の上、季節や社会活動等の変化に応じた交通事故分析に基づいた先制的な対策を講じるなど、より効果的なものとなるよう努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 6: ◯四十番(朝日将貴君) 暫時休憩されたいという動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
- 7: ◯議長(石井芳樹君) 朝日将貴議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 8: ◯議長(石井芳樹君) 御異議なしと認め、暫時休憩いたします。
午前十一時九分休憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後一時開議
- 9: ◯議長(石井芳樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
通告により質問を許可いたします。
鳴海やすひろ議員。
〔三十六番鳴海やすひろ君登壇〕(拍手)
- 10: ◯三十六番(鳴海やすひろ君) あいち民主県議団を代表して、順次質問させていただきます。
質問に先立ち、六月二日の大雨による災害でお亡くなりになられた方の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
我々、あいち民主県議団は、この大雨により家屋の洗浄などに必要となった水道料金の減免や災害見舞金の基準緩和のほか、農地、農作物、農業施設の復旧・復興に向けた支援など、被害に遭われた皆様の声を反映した、きめ細やかな支援を知事に要望したところであり、今後も安全・安心なあいちの実現に取り組んでまいります。
それでは、順次質問をしてまいります。
初めに、五類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症対策についてお伺いします。
まず、新型コロナウイルスに感染した患者の治療に昼夜を問わず、献身的に尽力してこられた医療関係者の皆様をはじめ、地域の医療、福祉の現場を支えてこられた方々に、心から敬意と感謝を申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症が五月八日以降、感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から五類感染症に移行となりました。
これまでの三年半近くの感染状況を振り返りますと、二〇二〇年一月に、県内で最初の新型コロナウイルスの感染者が確認されて以降、八回の波を繰り返し、昨年の夏には新規陽性者数が一日で一万八千九百八十五人、確保病床の入院患者数が千四百六十九人と過去最多を記録しました。
特に、オミクロン株が主流となった第六波以降、若年層での陽性者が多くなる一方、入院患者の割合は七十歳代以上の高齢者が多い傾向となりました。
感染拡大時には病床の逼迫などにより、高齢者施設の入所者が施設内での療養を余儀なくされる状況もあったと聞いております。
高齢者施設では、これまでも高齢の入所者を守るため、職員が感染しない、人にうつさないための手指消毒や個人防護具の着用、また施設内にウイルスを持ち込まないように面会時などの感染防止対策に工夫をされてこられました。
しかし、こうした御努力にもかかわらず高齢者施設のクラスターは第六波以降、多数発生しました。
感染症の位置づけが五類感染症と変更になりましたが、ウイルス自体が消滅したわけではありません。感染症対策に当たっては、県民に寄り添い、誰一人取り残さないようにするためにも、一般の方はもちろんですが、重症化リスクの高い高齢者には特に配慮が必要です。
高齢者の中には基礎疾患を持っている方も多く、一旦医療機関に入院しますと、入院期間が長期化します。また、高齢者施設においてクラスターが発生すると、入院して治療が必要となる入所者の方が多くいらっしゃることから、地域の医療機関において病床が逼迫する可能性がより高くなります。
今後、感染の波が繰り返しやってくることも予想される中で、高齢者施設の入所者をはじめ、重症化リスクの高い方々に対する取組は、今後も継続していく必要があると考えます。
そこでお伺いします。
新型コロナウイルス感染症が五類感染症に移行しましたが、重症化リスクの高い高齢者施設入所者等の方々の生命と健康を守るため、県としてどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、本県行政におけるDXの推進についてお伺いします。
本県では、二〇二〇年十月に愛知県DX推進本部を立ち上げ、県行政のデジタル化等を強力に推進しております。これまでも、パソコンで行う定型業務を自動処理するRPAの導入のほか、テレワーク環境の整備、拡充、行政手続のオンライン化、収納事務のキャッシュレス化など、県行政の効率化、DXの推進に着実に取り組んでおります。
その一方、ICTは急速に進展しています。最近では、生成AIの一種であるチャットGPTが新聞やニュースで話題となっています。これは、質問文を入力すると、それに応じた答えを返してくれるツールでありますが、簡単な質問への回答だけではなく、文章の要約や英語の翻訳、さらには小説や詩の創作など、様々なことに使えるとのことです。
先日、本県においても庁内に生成AI活用検討チームを立ち上げ、庁内における利活用を検討すると発表されました。今後、多くの自治体で、こうした最新のICTを利用する取組が試みられていくのではないでしょうか。
いずれにしても、便利なデジタルツールを有効活用することは、これまで手間がかかっていた業務の省力化につながると考えます。業務時間が短縮するという効果もありますし、オンライン化により対面でなくとも業務を行うことができれば、移動時間の短縮という効果もあります。
さらには、便利なデジタル技術を活用して、業務の生産性を高め、仕事環境をよりよくすることで、職員の働き方改革にもつながるものと考えます。
また、利用者である県民の皆様の立場から考えると、デジタル技術を活用することによって、例えば、わざわざ県庁に出向かなくとも手続が完了するならば、利便性は大きく向上することになります。
そこでお伺いします。
県行政のデジタル化、DXの推進について、今年度はどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、さらなる愛知の発展についてのうち、アジア競技大会、アジアパラ競技大会についてお伺いします。
二〇二六年の第二十回アジア競技大会、第五回アジアパラ競技大会の開催まで三年三か月となり、大会への注目も高まりを見せています。
その一方で、大会主催者のアジア・オリンピック評議会(OCA)等の指摘を踏まえ、先週の木曜日には、大会組織委員会の理事会において仮決定した競泳、飛び込みの競技会場を名古屋市総合体育館レインボープールから東京アクアティクスセンターに変更することが決議されるなど、大会の成功に向けて、解決していかなければならない課題も多いと思います。
また、本年三月末の知事の定例記者会見では、建設費の高騰などにより、大会の収支予算の見通しが厳しさを増していることから、開催経費縮減のため、選手団の規模等を含め大会計画の見直しに向けた協議をOCAと行っていることが明らかにされ、名古屋競馬場跡地で計画をしていた選手村の整備を取りやめて、選手や大会関係者等の宿泊にホテルなどを活用するという大きな方針転換が示されました。
そして、OCAによる視察が、先週の月曜日から火曜日にかけて行われたと承知しております。
既存のホテルを活用すれば、選手村の整備に必要となる多額の経費を抑えることができるとともに、選手や大会関係者等がホテルを利用するため、県内の宿泊施設が大いににぎわい、経済波及効果も期待されます。
しかしながら、私はホテルをはじめとした全ての宿泊施設で、パラアスリートを受け入れることができる環境が整っているのか、また、多くの観客を受け入れる客室の数が十分なのか、不安を抱いております。
大会の準備を進めるに当たっては、様々な工夫により、アスリートにとって最高の環境を用意することが大変重要であり、アジアパラ競技大会は日本で初めての開催となります。
これを契機に、世代、性別、障害の有無、国籍、民族などの違いを理解し、互いに認め合う社会、誰もが安心して生活できる愛知・名古屋の実現に向けて一層取り組んでいく必要があります。
アジアの国々の多様な文化を尊重し、様々な交流を促すための普及啓発活動やおもてなしの機運醸成など、大会を成功に導くためには、競技会場やアクセスルートなど、施設のユニバーサルデザインの推進等の環境整備にもしっかりと取り組んでいく必要があります。
そこでお伺いします。
ユニバーサルデザイン推進の観点から、今後の大会の開催準備にどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、ジブリパークを活用した周遊観光についてお伺いします。
アメリカのタイム誌が今年三月に発表した二〇二三年版の世界の最もすばらしい場所五十選に、日本からは京都と共に名古屋が選ばれ、大変驚きましたが、その決め手の一つとして大きく取り上げられたのは、名古屋市近郊にあるジブリパークであり、世界からも認められたパーク内には、連日、ジブリファンをはじめとする多くの方々が訪れ、にぎわいを見せています。
こうしたジブリパークの高い注目度を、観光関連産業をはじめとする、この地域全体の活性化につなげていくためには、来園された方々が、ジブリパークだけでなく、広く周遊観光することで、その経済効果を県内各地へと波及させていく必要があります。
県では、ジブリパークを愛知県全体で盛り上げるとともに、ジブリパークのオープンを契機として、愛知の魅力を広く県内外にPRするため、ジブリパークのある愛知を合い言葉に、ジブリの世界観に沿って本県の魅力を伝える観光動画の制作や、本県の歴史、産業、自然などをテーマとした県内周遊モデルコースの紹介をはじめ、オープン以来、様々な取組を進めていると承知しています。
しかしながら、パークへの集客は好調な一方で、パークからそのまま帰宅する方も多く、期待したほどの周遊観光につながっていないとの報道もあります。
私自身、名古屋駅周辺では、ジブリパークのお土産を持った方々を見かけ、飲食店関係者からも好影響を聞く一方、少し離れた地域では、パーク来園者が観光に訪れている印象がなく、愛知が誇る強力な集客コンテンツを県内の周遊観光に十分に生かせていないと感じております。
そうした中、今年度には、ジブリパークの第二期オープンが予定されており、新エリアとして、もののけの里と魔女の谷が加わり、いよいよフルオープンを迎えます。
新たな魅力が加わることで、ますます注目度が高まることに加え、エリアが広がることで、パーク内での滞在時間が延び、県内に宿泊する方や、リピーターが増えることが期待されるため、この機会により一層、愛知の魅力を発信するとともに、来園者に周遊観光を促していくことが必要と考えます。
そこでお伺いします。
ジブリパークの第二期オープンに向けて、県内周遊観光のさらなる促進にどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、リニア中央新幹線開業を見据えた名鉄名古屋駅地区再開発についてお伺いします。
リニア中央新幹線が開通した暁には、三大都市圏を包含する世界最大規模の人口七千万人のスーパー・メガリージョンが形成されることが期待され、本県はそのセンターを担う地域となります。
とりわけ、私の地元、中村区にある名古屋駅は、本県の陸の玄関口であり、社会経済活動の回復とともに国内外からさらに多くの方々が訪れると予想されます。しかしながら、名古屋駅は乗換えなどが非常に分かりにくいと言われており、現在、分かりやすい乗換空間の形成や駅前広場周辺の再整備等によるスーパーターミナル化に向け、様々な取組が進められております。
本年一月に開催された名古屋駅周辺のまちづくりシンポジウムにおいて、駅利用者の利便性を向上させるとともに交通結節機能の充実と再編を図る名古屋駅東側の駅前広場の形状などが示されました。また、ターミナルスクエアの整備が着実に進んでおり、新しい名古屋駅に生まれ変わるという実感が少しずつ湧いてきているところであります。
そして、名古屋駅の南側に目を向けますと、本年三月三十一日に、若者のレジャーをジャックするというコンセプトの下、私も子供の頃から何度も訪れた名鉄レジャックが惜しまれつつ約五十年の歴史に幕を閉じました。
この場所は、名古屋鉄道株式会社が中心となって進める名鉄名古屋駅地区再開発エリアに含まれており、今後、この一帯がどのような姿に生まれ変わるのか、大変注目しているところであります。
名鉄名古屋駅地区再開発は、名古屋鉄道株式会社によって二〇一五年に再開発エリアの価値最大化や鉄道駅、バスセンターの再整備などの基本計画の考えが示され、二〇一七年には建物のイメージパースが公表されました。また、その後、名鉄名古屋駅を現行の二線から四線に拡張する計画も示され、二〇二二年度に工事に着手すると発表されておりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化を踏まえ、二〇二〇年十一月に再開発のスケジュールや計画内容の見直しを行う方針が示され、この計画は一旦立ち止まることとなりました。
そのような中、先月五月十一日に駅の四線化を含めた名鉄名古屋駅地区再開発について、関係機関との協議、調整を加速させ、計画を再スタートするとの発表がありました。
この事業によって、名古屋駅を中心とした鉄道ネットワークの充実が図られ、利便性が飛躍的に高まるとともに、名鉄名古屋駅も含めた名古屋駅全体が名古屋のみならず、愛知のにぎわいの拠点、ランドマークとなることに大きな期待感を抱いております。
そこでお伺いします。
リニア開業を見据え、愛知の顔ともなり得る名鉄名古屋駅地区再開発に対して、県としてどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、持続的な本県産業の振興についてのうち、中小企業の人材確保支援についてお伺いします。
少子・高齢化の進展により、本県の人口は二〇一九年をピークに減少に転じており、産業の担い手についても、今後減少していくことが予想されます。企業は三年以上にわたり新型コロナウイルス感染症の影響を受けてきましたが、今後、社会経済活動が本格的に回復することから、人手不足感が今後ますます高まっていくのではないかと思います。
愛知県が実施している中小企業景況調査によると、二〇二三年一月期から三月期では、雇用人員が不足するとした企業の割合は、過剰であるとした企業の割合より二二・一ポイント高くなっており、人手不足の中小企業が多くなっています。また、これを業種別に見ると、不足超過が製造業は二〇・四ポイントですが、建設業は六五・七ポイントと、ほかの業種より高くなっているなど、一部の業種でより人手不足が深刻となっており、事業活動に影響を及ぼす可能性もあります。
企業が継続して安定的に事業運営を行うためには、必要な人材を確保することが求められます。しかし、中小企業は、大企業と比べて採用に携わるマンパワーや経費、採用活動のノウハウが乏しいことから、人材確保に苦慮しているのではないかと思います。また、根本的な課題として大企業と中小企業との賃金格差が挙げられ、就職活動を行う学生などの若者は大企業志向が強いと言われています。
県内には、産業を支える優良な中小企業が数多くあります。こうした中小企業への関心を高め、若者や求職者の職業選びの選択肢に中小企業を加えてもらうためには、中小企業自らが若者や求職者にしっかりとその魅力を情報発信することが必要です。しかし、そうしたノウハウなどの不足により、特に人手不足業界においては、求人を出しても人が集まらないなどの課題を抱えていることから、こうした中小企業に対して、採用活動等への支援を行うことも必要であると考えます。
また、就職氷河期世代や定住外国人のうち、不安定な就労から抜け出し、正規雇用を望む方々が、中小企業で就労できるよう促すことも必要ではないかと考えます。
そこでお伺いします。
中小企業の人材確保に対する支援について、どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、航空宇宙産業への支援についてお伺いします。
本県には、大手航空機体メーカーのほか、中小航空機サプライヤーが数多く立地しており、本県を中心とする中部地域は、日本の航空機、部品の約五割、航空機体部品の約六割を生産する、我が国最大の航空機産業拠点であります。
この地域が、アメリカのシアトル、フランスのトゥールーズと並ぶ世界の航空宇宙産業の一大中心地を目指す中で、大いに期待された三菱重工業のスペースジェットの開発があり、県としても、この新たな完成機事業の実現に向けて、民間航空機生産整備拠点の整備等、様々な取組を行ってきました。
しかし、残念なことに、スペースジェットの開発は、本年二月に開発を取りやめ、撤退すると発表され、また、新型コロナウイルス感染症を背景とした航空機需要の長期にわたる低迷が続くなど、航空宇宙産業を取り巻く情勢は大変厳しい状況となっております。
企業の生産現場では、新型コロナウイルスの影響により、他産業へ流出した人材が戻らず、また、航空機業界自体のイメージ悪化の影響が雇用面にも及び、新規採用も困難な状況であることから、この改善が喫緊の課題であります。
一方、当地域が主に手がけている国際線向けのボーイング787等の広胴型機については、生産レートが徐々に回復しており、今後、本格的な回復基調に入ることが見込まれますので、増産に対応するための体制整備が急務となっています。
今後、人材不足が継続するようなことであれば、増産に対応できない航空機サプライヤーが増加し、当地域の航空宇宙産業のサプライチェーンが寸断されることになりかねません。
このような事態を回避し、今後も当地域の航空宇宙産業を維持、発展させていくためには、県内航空機サプライヤーが海外のサプライヤーとの競争に打ち勝つための生産体制を整備するとともに、生産現場における人材確保につながる取組が急務であると考えます。
そこでお伺いします。
アフターコロナを迎えた今、県内航空機サプライヤーに対して、どのような支援に取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、県産木材の活用方策についてお伺いします。
私の地元である名古屋市中村区では、本年一月に中村区役所の庁舎が移転し、複合庁舎として建て替え整備がされました。待合スペースの天井などに愛知県産の木材を使い、温かみが感じられる空間となっております。整備に当たっては、県産木材を積極的に使ってもらうよう私からも名古屋市に働きかけをしたこともあり、利用者からは好評という声を聞いて大変うれしく思っております。
このほかにも県産木材を使った建物として、昨年、ささしまの新幹線高架下に木造オフィスが完成しました。このオフィスは、これまで使いにくかった高架下スペースの有効利用や、木材とカーボン樹脂とのハイブリッド資材の採用など、先進的な事例として全国的に評価されています。
さらに本年四月には、金山駅付近に、板にした木材を貼り合わせた厚みのある大きなパネル、いわゆるCLTを使用した木造ビルができました。こうした民間建築については、県から支援が得られたことが実現に向けた後押しになったと聞いております。
このような都市部の建築物にも県産木材が使われることが増えてきており、民間建築物に木材利用が広がりつつあることを実感しております。
さて、本県は県土の約四割が森林であり、そのうち六割強をスギ、ヒノキの人工林が占めています。これらは戦後に植えられたものが多く、十分に育ち、建築用として使える状態となっています。
樹木は光合成により、二酸化炭素を吸収、固定して育ちます。その樹木を建築資材などとして長期間利用し続けることは、空気中の二酸化炭素を炭素の状態で固定し続けることができます。また、樹木の二酸化炭素の吸収量は成長につれて変化し、高齢になるに従い減少すると言われています。
そのため、今ある人工林資源を積極的に伐採して活用し、その後、計画的に植え、育て、森林の循環をつくることは、地域経済の活性化だけではなく、SDGsやカーボンニュートラル社会の実現にもつながることから、より一層木材の利用を広げていく必要があると考えます。
そこでお伺いします。
愛知県木材利用促進条例が施行されて一年余りが経過しますが、県として県産木材の活用にどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、特殊詐欺や侵入盗対策についてお伺いします。
二〇二二年における愛知県内の犯罪情勢については、二〇一〇年から減少傾向にあった刑法犯認知件数が十三年ぶりに増加に転じました。中でも特殊詐欺は、二〇二一年に引き続き増加し、被害額も二十億円を超えたほか、侵入盗についても美容院等の事業者を狙った出店荒しが大きく増加しており、最近では闇バイトを通じて集まった若者が白昼堂々と高級腕時計店に押し入る事件が本県でも発生するなど、県民の不安を増大させる犯罪が目立っています。
まず、特殊詐欺については、本年に入り、東南アジアを活動拠点とするグループが逮捕されるという報道がありました。
このグループの逮捕により、特殊詐欺の被害が減少するのではないかと考えましたが、実際には連日のように高齢者の方を狙った特殊詐欺被害に関する報道を目にしています。
地元住民の方々とお話をさせていただく際も、特殊詐欺にだまされるなんて考えられないといった声も聞かれるなど、特殊詐欺被害の実情と県民意識の差を感じているところであります。
他方、侵入盗については、空き巣など、住宅を対象としたものであれば、県民の身近で発生する犯罪であるため、その発生状況が体感治安にも直結するものと考えられます。
また、事業者を狙った出店荒しなどであれば、新型コロナウイルス感染症対策で疲弊した経営者の方たちが、侵入盗の被害に遭うことでさらなる打撃を受けることになるのではないかと心配をしております。
こうした状況の中、新型コロナウイルス感染症の五類感染症への移行もあり、人々の活動が活発になっていくことを考えると、今後ますます侵入盗の被害が増加するのではないかと危惧しております。
そこでお伺いします。
本県における本年一月以降の特殊詐欺並びに侵入盗の情勢を踏まえ、未然防止や犯人の検挙について、どのような対策を進められているのか、警察本部長の御所見をお伺いします。
次に、誰もが活躍できる社会の実現と次代を創る人づくりについてのうち、がん対策についてお伺いします。
本県では二〇〇八年から愛知県がん対策推進計画を策定し、県内のがんの現状や課題を踏まえながら対策を進められており、がんの予防、ゲノム医療を含むがん医療、ライフステージに応じた対策、がんとの共生の四つの観点から幅広い施策を実施しています。
医療面では、日本のがん診療をリードする愛知県がんセンターをはじめ十九の病院が、がん診療連携拠点病院として、さらに、九つの病院が愛知県がん診療拠点病院として指定され、県内のどこに住んでいても、病状に応じた適切ながん治療や緩和ケアを受けられる体制が整備され、大変心強く感じています。
また、先月、知事は米国渡航され、世界最大規模の総合がんセンターである、MDアンダーソンがんセンターを訪問されておりますが、このことは、今後の本県のがん医療の進展に大いに役立つものと期待しております。
一方、生活面では、がんの罹患数と死亡数は、人口の高齢化を背景に増加をしておりますが、がんの死亡率は、がん対策への取組が進んだことや、がん医療の進歩などにより減少しており、がんは、かつての不治の病から長く付き合う病気に変化し、がんと共存する時代となっております。治療と社会参加の両立を図りながら、がんになっても、治療後の将来を見据え、治療を受けている患者さんの希望に配慮した取組が求められております。
昨年度から本県でも、副作用で脱毛した方へのウィッグ購入費補助が開始され、患者さんの社会参加につながるものとして心強く感じております。がん患者さんの不安や悩みが軽減されるよう、こうした支援を継続して実施していかなければならないと考えます。
そこでお伺いします。
こうした現状を踏まえ、今後、どのようにがん対策に取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、少子化対策についてお伺いします。
国立社会保障・人口問題研究所が本年四月に公表した日本の将来推計人口によりますと、二〇五六年には日本の総人口は一億人を割り、二〇七〇年には約八千七百万人、現在の約七割まで減少し、六十五歳以上人口がおよそ四割を占めることとなります。
また、出生数は、二〇二〇年に約八十四万人であったものが、五十年後には約五十万人にまで減少するという大変厳しい推計となっております。
二〇二二年の出生数は、二〇一七年に政府が予測したよりも八年早く八十万人を下回りました。ここ数年の急激な出生数の低下は、コロナ禍による婚姻数の減少、妊娠・出産期の感染に対する不安、物価高騰などによる経済的不安などが影響していると考えられます。
特に結婚については、二〇一九年に約六十万組であった婚姻数が、二〇二二年には約五十万組にまで落ち込んでおります。
また、本県の二〇二〇年における、三十歳代前半の男性の約半数、女性の約三分の一が独身であり、平均初婚年齢も、ここ数年男性が三十歳、女性が二十九歳と、一九七〇年代後半に比べ、男性が三歳、女性が五歳程度上昇しており、未婚化、晩婚化が進んでおります。
少子化の状況については、本県でも全国と同様、合計特殊出生率、出生数の下降、減少が長期にわたって継続しており、早急に対処しなければなりません。
県が、これまで少子化対策として、安心して出産できる周産期医療体制の整備や、保育サービスの充実、放課後児童クラブの整備促進など、様々なきめ細かい施策を実施してきたことは承知をしております。
しかし、これらの支援は子育て支援、つまり、既に子供がいる方への支援であり、その前の段階、未婚の方への支援は少なかったように思います。
そのため、若者が未来に希望を感じ、結婚、出産、子育てに積極的になれるよう、県としてさらなる支援をすべきと考えます。
そこでお伺いします。
県として、特に若者に向けた少子化対策に、今後どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。
次に、中高生の英語力向上についてお伺いします。
先月十七日に文部科学省は、二〇二二年度の英語教育実施状況調査の結果を公表しました。
この調査は、英語教育の実態把握と充実、改善を目的として、全国の公立中学校三年生と公立高校三年生を対象に毎年行われているもので、CEFRという外国語の運用能力を評価するための国際的な指標を用いて、生徒の英語力を評価しております。
今回の結果を見ると、愛知県の中学校三年生の英語力の状況は、CEFRのA1レベルに当たる英検三級以上を取得している生徒数と、教員がそれと同等の英語力を持つと判断した生徒数を合わせた割合が三五・二%で、全国平均の四九・二%と比べると一四ポイントも下回っており、都道府県順位では、島根県、鳥取県に次ぐワースト三位となっております。
また、高校三年生では、CEFRのA2レベルに当たる英検準二級以上を取得している生徒数と、教員がそれと同等の英語力を持つと判断した生徒数を合わせた割合は、四二・六%で、全国平均の四八・七%を約六ポイント下回っており、都道府県順位ではワースト七位となっています。
今後は、中高生になる前の小学生の頃から、さらなる英語教育の充実を進める必要があるのかもしれません。また、生徒の英語力を向上させるために日々努力し、様々な工夫をされている学校現場の先生方へのさらなるサポートが生徒の英語力向上につながるのではないでしょうか。
現在のグローバル社会において、柔軟な思考力や異文化への対応力を持ち、将来に向け、活躍できる人材を育成するためにも、国際共通語としての英語力を高めることが不可欠であると考えます。
そこでお伺いします。
英語教育実施状況調査の結果を受け、今後、中高生の英語力向上にどのように取り組んでいかれるのか、教育長の御所見をお伺いします。
最後に、公立学校における休み方改革のうち、ラーケーションについてお伺いします。
本県では、今年度から休み方改革を通じて、国民全体のワーク・ライフ・バランスの充実と、生産性向上による日本経済の活性化の実現を目指す愛知県休み方改革プロジェクトに取り組むこととしています。
このプロジェクトは、あいち県民の日、あいちウィークを契機とした休み方改革の推進、休暇を取得しやすい職場環境づくり、家族と子供が一緒に過ごせる仕組みづくり、平日や閑散期への観光需要のシフト、地域が一体となった休み方改革の推進という五つの柱が立てられ、行政だけでなく、経済界、労働界、教育界が一体となって取り組んでいくこととされています。
総務省が実施した令和三年社会生活基本調査の結果では、土曜日に働いている人の割合が約四五%、日曜日に働いている人の割合が約三〇%となっています。また、業種や職種によっては、祝日にも仕事がありますので、そうした家庭では、土日や祝日に家族と子供が一緒に過ごす時間をつくりにくい状況があります。
仮に、仕事が休みの平日に子供と一緒に過ごしたいと思っても、学校を休ませることをためらう保護者は多いのではないかと思います。
その意味で、休み方改革プロジェクトの柱の一つである家族と子供が一緒に過ごせる仕組みづくりには大きな意義があると思います。そして、働き方改革の選択肢を増やすことにもつながると考えます。
具体的には、子供の休みを契機に家族が一緒に休める仕組みとして、十一月二十一日から二十七日までのあいちウィーク期間中の一日を学校休業日とする県民の日学校ホリデーと、家族の休みに合わせて子供が学校外で活動できる仕組みであるラーケーションの日の二つの取組を進めようとしています。
ラーケーションの日は、子供たちが保護者と共に、家庭や地域で、体験や探求の学び、活動を自ら考え、企画し、実行する自主学習活動の日であることから、登校しなくても欠席とはならず、公立学校で今年の二学期以降、環境が整ったところから、順次実施すると聞いています。
しかし、家族で旅行や遠出をする余裕のない家庭もありますし、出かけても単なるバケーションで終わってしまう心配や、授業に出ないことで勉強が遅れてしまうのではないかという不安もあります。
一方、学校にとっては、休日の谷間などラーケーションの取得が集中する日には授業を進められなくなったり、給食の必要数の確認が生じるなど、教員の負担増につながるおそれがあります。
今後、教育委員会では、実施に向けた環境整備をしていかれると思いますが、各市町村や学校関係者、そして何より子供たちと保護者の理解を得た上で進めていく必要があります。
そこでお伺いします。
ラーケーションの日の円滑な実施に向けて、どのように環境整備を進めていかれるのか、教育長の御所見をお伺いします。
以上、あいち民主県議団を代表して、県政各般にわたる様々な課題についてお尋ねをいたしました。真摯な御答弁をお願い申し上げまして、壇上からの質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔知事大村秀章君登壇〕
- 11: ◯知事(大村秀章君) あいち民主県議団の鳴海やすひろ総務会長の質問にお答えをいたします。
初めに、五類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症対策についてのお尋ねであります。
五類感染症への移行後におきましても、県民の皆様に寄り添いながら、生命と健康を守ることを最優先して取り組んでいく必要があると考えており、とりわけ重症化リスクの高い高齢者が生活している高齢者施設等における感染防止対策の取組は大変重要であります。
そのため本県では、高齢者施設等の職員の方への定期的なスクリーニング検査を継続実施するとともに、施設内で新規陽性者が発生した際には、入所者等に対するPCR検査を速やかに実施できる体制を維持し、感染拡大防止を図っております。
また、医療体制の逼迫を防ぐための本県独自の取組になりますが、施設内で療養中の入所者に対しまして、緊急の往診、訪問看護を行う医療機関への支援を継続するほか、透析患者で通院が困難な高齢者などの搬送支援にも取り組んでいるところであります。
さらに、高齢者施設等の入所者に加えまして、自宅で療養中の高齢者や、障害のある方への新型コロナワクチンの巡回接種を行う医療機関に対する本県独自の支援策も、来年三月末まで引き続き実施することといたしました。
希望される皆様が速やかに接種を受けていただけるよう、市町村等とも連携を図り、取組を進めてまいります。今後も、重症化リスクの高い高齢者施設等の入所者をはじめ、県民の皆様の生命と健康を守るため、医療提供体制に万全を期するとともに、感染状況と入院患者の状況を注視しながら、新型コロナウイルス感染症対策に引き続きしっかりと取り組んでまいります。
次に、本県行政におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進についてであります。
本県では、私を本部長とする愛知県DX推進本部を司令塔として、県行政に係る業務のデジタル化、DXの取組を進めているところであり、五月十九日に開催をいたしましたDX推進本部員会議において、本年度に重点的に取り組む三つの項目を決定いたしました。
一つ目は、行政手続のオンライン化であります。本県では、この取組を二〇二一年度から進めておりまして、昨年度末までに軽自動車税環境性能割の申告と、千余りの行政手続をオンライン化いたしました。本年度もオンラインで申請可能な手続のさらなる拡充に取り組んでまいります。
二つ目は、収納事務のキャッシュレス化であります。本年四月から愛知県電子申請・届出システムを利用したオンライン上で、行政手続に伴う手数料等のキャッシュレス決済を導入し、納税証明書等の百以上の手続に対応をしております。今年度は、県の公共施設においてキャッシュレス決済を順次導入してまいります。
三つ目は、全庁共通業務のデジタル活用による業務改善であります。本年十月を目途に、全ての契約を対象に、電子契約を導入し、事業者の利便性の向上と業務の効率化を図ってまいります。
加えて、庁内に生成AI活用検討チームを設置いたしました。この生成AIの活用の検討に着手をしたところでありまして、デジタルツールを活用した全庁共通業務のさらなる改善に取り組んでまいります。
今後も、DX推進本部を司令塔といたしまして、行政のデジタル化、DXに、庁内横断的、機動的に取り組みまして、県民の皆様の一層の利便性の向上とさらなる業務効率化に努めてまいります。
続いて、アジア競技大会、アジアパラ競技大会についてのお尋ねであります。
ユニバーサルデザインの推進は、愛知・名古屋大会に参加するアスリートが最高のパフォーマンスを発揮するとともに、年齢や性別、障害の有無などに関わらず、全ての方がスムーズに観戦できる環境を整えるための不可欠な要素であると認識しております。
そのため、本年三月に改定いたしましたアジア競技大会、アジアパラ競技大会を活用した地域活性化ビジョンにおきましても、共生社会の実現に向けた取組の推進を新たに位置づけまして、誰もが安全で快適に移動できるまちづくりを進めていくこととしております。
具体的には、競技会場やアクセスルート等について、ユニバーサルデザインに基づいた整備基準を定めるアクセシビリティ・ガイドラインを今年中に取りまとめるため、学識経験者や障害者団体等で構成する検討会を、今月の六月二十七日に設置いたします。
また、ホテル等の既存施設を活用する選手村につきましては、パラアスリートに配慮した客室の確保や、大会スタッフによる競技会場への円滑な移動のサポートなど、パラアスリートが競技に専念できる選手村機能の在り方を点検しながら、調整してまいりたいと考えております。
ハード、ソフトの両面からの対応により、選手を含めて誰もが快適に大会を楽しんでいただける環境づくりを進めてまいります。大会の準備、開催を通じて、多様性を尊重し合う共生社会の実現に貢献をしていくように、しっかりと取り組んでまいります。
次に、ジブリパークを活用した周遊観光についてお答えをいたします。
国内外から注目されるジブリパークの第二期オープンは、愛知のブランド力をさらに高め、より多くの方々に、愛知を旅の目的地として選んでいただく絶好の機会となります。
このため、人口規模が大きく、多数のジブリパーク来園者が見込まれる首都圏と関西圏に向けまして、渋谷や道頓堀など繁華街の屋外ビジョンをはじめ、東京駅や新大阪駅のデジタルサイネージなどで、スタジオジブリが手がけた本県の観光動画「風になって、遊ぼう。」を第二期オープンに合わせて集中的に放映してまいります。
さらに、ジブリパークに多く来園されている女性やファミリー層をターゲットといたしまして、雑誌やSNSを活用し、愛知の観光情報を効果的に発信してまいります。
そして、ジブリパークを訪れる多くの方々に、県内各地へと足を延ばしていただけるよう、地域と一緒になって、本県ならではの観光プログラムを多数用意し、チケット販売サイト内に設けた特設サイト、ジブリパークのある愛知への旅で紹介してまいります。
第二期オープン後は、パークでの滞在時間が延び、来園前後に、県内で宿泊する方が増えていくものと期待されるため、ジブリの世界観を感じながら各地をじっくりと巡る観光プログラムのさらなる充実と発信を進めてまいります。
こうした取組によりまして、本県へのさらなる集客と、県内各地への周遊観光を一層促し、ジブリパーク第二期オープンの効果を県内全域に広げてまいります。
続いて、リニア中央新幹線開業を見据えた名鉄名古屋駅地区再開発についてであります。
この再開発事業は、名鉄名古屋駅が一九四一年におおむね現在の形で開業して以来のまさに百年に一度の大事業でありまして、リニア開業を見据えた愛知・名古屋のさらなる発展に大きく寄与する極めて重要な事業であります。
本県では、二〇二二年二月に策定をしたあいち交通ビジョンの中で、リニア開業効果の広域的な波及のために、名古屋駅のスーパーターミナル化や、名古屋駅から主要都市への四十分交通圏の拡大などを位置づけて取り組んでまいりました。
この再開発事業によりまして、中部国際空港へのアクセス強化、駅の四線化などに伴う分かりやすい乗換環境の実現、県内各地域へのアクセス利便性の向上が図られ、リニア開業効果を最大限に発揮する総合的な交通ネットワークの形成に向けまして、大きく前進するものであります。
また、この名鉄を含めた新しく生まれ変わる名古屋駅は、スーパー・メガリージョンのセンターを担う中京大都市圏の玄関口となり、新たなにぎわいが創出され、広域的な産業・経済活動がさらに活発に展開される拠点として、大いに期待をされるところであります。
名鉄は、今年度から基本設計を進め、来年度には事業の方向性を判断すると表明しております。
本県といたしましては、名鉄はもちろんのこと、名古屋市など関係者と緊密な連携を図りながら、この事業の具体化に向けまして、広域的観点からの助言、そして、国の補助制度適用の働きかけを含めた資金面での支援など、最大限のバックアップをしてまいります。
次に、中小企業の人材確保支援についてお答えをいたします。
人手不足感が高まる中で、本県が日本の成長エンジンとして社会経済を引き続き牽引していくためには、地域の産業を支える中小企業の人材確保は大変重要であると認識をいたしております。
本県は、これまでも中小企業経営者と学生との交流会や、ヤング・ジョブ・あいちでの若者の就職相談などにおいて、学生等に対し、中小企業への関心拡大と就労の促進を図ってきたところであります。
今年度は、こうした取組に加えて、人手不足を背景に採用活動に厳しさが増している建設、介護、運輸、警備業の中小企業を対象に、求職者の入社動機を高めるための知識及び手法を習得する機会や、業界研究フェアにおきまして、業界や企業の魅力を直接アピールする実践の場を提供いたします。
学生と求職者には、同フェアや一日職場体験を通して、業界の理解を深め、仕事や企業選びの視野を広げるように促してまいります。
さらに、合同企業説明会で中小企業と求職者のマッチングを図るなど、採用活動と求職活動の初期段階から寄り添った支援を実施してまいります。
このほか、正規雇用を目指す就職氷河期世代の方に対する研修や、職場実習、定住外国人に関しては相談窓口での就職相談や企業への伴走型支援を通じて、中小企業等への就労促進を図ります。
人材確保は、地域全体での取組が必要であることから、今後とも、ハローワーク等関係機関と連携しながら、中小企業の人材確保支援にしっかりと取り組んでまいります。
続いて、航空宇宙産業への支援についてであります。
航空宇宙産業は、技術分野の裾野が広い産業であることから、幅広く他の産業に波及することで、我が国の産業全体の技術力、競争力の強化に寄与する重要な産業であります。
残念ながら、三菱スペースジェットは開発中止となりましたが、開発を通じて獲得した知見や試験設備等の資産を今後の航空機産業の発展に向けて大いに活用していただきたいと考えております。
将来に目を向けますと、航空宇宙産業は、今後二十年間で世界のジェット旅客機の運行機数が一・六倍に増加すると見込まれる成長産業であります。しかしながら、足元の業況では、航空機需要の落ち込みを受けて、販路開拓に加え、生産体制の立て直しや人材確保が急務となっております。
このため、さきの五月補正予算におきまして、今後期待される航空機需要の回復期において、県内航空機サプライヤーが競争に打ち勝てるよう、新たな取組を実施することといたしました。
具体的には、航空宇宙産業の商談会における出展支援を拡充するとともに、航空宇宙産業のイメージを回復し、人材確保につなげるため、学生等に航空宇宙産業の魅力を発信する取組等を実施いたします。
加えて、設備投資に対する補助制度である航空宇宙産業応援補助金を新設いたしまして、この六月九日から申請の受付を開始いたしました。
本県といたしましては、これらの取組を通じまして、当地域の航空宇宙産業が、自動車産業に次ぐ第二の柱として大きく飛躍するよう、地域一体となってしっかりと支援してまいります。
次に、県産木材の活用方策についてお答えをいたします。
木材利用の促進は、林業の振興のみならずカーボンニュートラル社会の実現に向けて、大変重要な役割を担っております。
そこで、二〇五〇年に向けて目指す都市の木造・木質化の姿やそれを実現するための長期ビジョンとして、ウッド・シティあいち二〇五〇を取りまとめ、今年の三月に公表をしたところであります。
このビジョンでは、全ての県民が木材のよさを享受でき、積極的に森林と関わっていく社会などを目指しております。
また、先ほど御紹介のありました都市部のオフィスビルをはじめ、商業施設、福祉施設等、民間建築物での木材利用の動きが広がりつつあり、これを定着させるためにも引き続き、木の香る都市(まち)づくり事業によりしっかりと支援してまいります。
加えて、増加が見込まれる木造・木質化のニーズに対応するため、二〇二〇年度から木造建築技術者育成講習を実施し、木造建築に精通した技術者の育成に取り組んでおります。
さらに本年七月には、新たにあいち木造・木質化サポートセンターを設置し、木造・木質化に関心を持つ建築主等からの相談に応えるとともに、建築関連事業者とのマッチングなどを進めてまいります。
県内のスギ、ヒノキの人工林は、林齢六十一年生以上のものが半数以上を占めておりまして、太く立派に育っております。
こうした資源を生かし、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、関係者一丸となって、オール愛知で木材利用にしっかりと取り組んでまいります。
続いて、がん対策についてお答えいたします。
本県におきまして、死因の第一位は依然としてがんでありまして、がんは県民の生命と健康にとって大きな課題であります。
本県では、二十八か所のがん診療連携拠点病院等を指定しておりまして、病状に応じた適切ながん治療や、きめ細かい相談支援を実施しております。中でも、本県のがん医療の中心的な役割を担う愛知県がんセンターは、次世代のがん予防と医療の創出にも取り組んでおり、本県のみならず、日本のがん医療を牽引していけるよう、本年度、将来のがんセンター整備に向けた基本構想調査を実施してまいります。
また、五月の私の米国渡航におきまして、世界最大規模の総合がんセンターであるMDアンダーソンがんセンターのピーター・ピスターズプレジデントと面談をし、愛知県がんセンターとの共同研究、人事交流やイノベーション等について、継続して話し合っていくことで合意いたしました。今後、県がんセンターの再整備の検討にも役立てられるよう、両者の連携に向けた協議を積極的に進めてまいります。
がん医療の進歩により、がんの生存率は改善している一方、がんとの共生に向けた取組もますます重要になってきております。
本県では、がん患者向けサポートブック、ピアサポーターによる相談事業に加え、二〇二一年度から、小児・AYA世代の支援として、妊よう性温存治療の助成、二〇二二年度からウィッグ購入等のアピアランス支援を実施しておりますが、さらに今年度新たに、若年患者在宅療養支援事業を開始し、がんとの共生に向けた取組を一層推進してまいります。
こうした取組を今後も継続して実施し、がんになっても安心して自分らしく暮らせる愛知の実現を目指してまいります。
私からの最後の答弁になりますが、少子化対策についてであります。
少子化対策は、子育て世代だけでなく、より若い世代も対象に、ライフステージに応じて取り組むことが重要と認識しております。
本県ではこれまで、あいちはぐみんプラン二〇二〇─二〇二四に基づきまして、若者が経済的にも精神的にも自立をし、就労や結婚、子育てを前向きに捉えられるよう、学齢期からのキャリア教育の推進、就労支援、保育サービスの充実など、様々な施策に取り組んでまいりましたが、少子化が大変厳しい状況にある中、その主な要因の一つと考えられる未婚化や晩婚化への対策として、結婚を希望する方の出会いのサポートを強化することが急務となっております。
このため、本年、今年の十月七日土曜日に、愛・地球博記念公園で、本県初の大規模婚活イベントを行う準備を進めておりまして、男女四百人というメンバーを、この愛・地球博記念公園にお招きいたしまして、そうした大規模な婚活イベントを行う準備を十月七日に予定をして、準備を進めておりまして、八月に参加者の募集を開始したいというふうに考えております。
また、本県独自の少子化対策パッケージでもお示しをしたとおり、五月臨時議会で御承認をいただきました、計十回のきめ細かな婚活イベント、大体五十人規模ぐらいになろうかと思います。これを十回、県内各地で、市町村の皆さんとも連携をしながら実施したいというふうに考えておりまして、商工会やNPOなどの民間非営利団体の婚活イベントにも補助するなど、結婚を望み、出会いを求める方々への支援を積極的に行ってまいります。
今後も個人の多様な価値観、考え方を尊重しながら、希望する方々が結婚し、安心して子育てができる基盤づくりにしっかりと取り組んでまいります。
以上、御答弁申し上げました。
- 12: ◯警察本部長(鎌田徹郎君) 特殊詐欺や侵入盗対策についてお答えいたします。
初めに、特殊詐欺についてでございます。
本年五月末現在の認知件数は五百十七件と、前年同期比で百八十七件増加しております。
特徴といたしましては、被害者の約八割が御高齢の方々で、被害の多くが固定電話への着信が契機となっております。
未然防止対策につきましては、犯人と直接会話することを避けるため、被害防止機能付電話機の普及に加え、留守番電話設定の促進等に取り組んでおります。
検挙対策につきましては、被害発生時の迅速な対応による現場検挙はもちろん、組織の中枢被疑者に対する突き上げ捜査や犯罪収益の剥奪など、犯罪組織に実質的な打撃を与える取組を推進しております。
次に、侵入盗についてでございます。
本年五月末現在の認知件数は千三百六十一件と、前年同期比で二百八件増加しております。
特徴といたしましては、出店荒らし被害の増加が著しく、その要因として、組織窃盗グループが特定の業種や業態の店舗に狙いを定め、犯行を繰り返していることなどが挙げられるところでございます。
未然防止対策につきましては、店舗などでは現金を保管しないことや、防犯性能の高い金庫の活用を働きかけておりますほか、まちの防犯診断やトライアルカメラの活用を通じ、犯罪の起きにくい社会づくりを推進しております。
検挙対策につきましては、組織窃盗グループの戦略的な取締りに加え、こうした犯行グループの犯行を支える、いわゆる犯罪インフラの供給者の検挙も強力に推進しております。
県内の治安情勢は厳しい状況にございますが、特殊詐欺や侵入盗など、県民の皆様の体感治安を著しく悪化させる犯罪に対し、県警察の総力を挙げた取組を推進してまいりたいと、かように考えております。
以上でございます。
- 13: ◯教育長(飯田靖君) 初めに、中高生の英語力の向上についてお答えをいたします。
議員お示しの二〇二二年度の英語教育実施状況調査の結果は真摯に受け止めております。一方、同じ文部科学省が二〇一九年度に実施をした全国学力・学習状況調査では、本県の中学校三年生の英語は、全国平均よりやや高い成績でございました。
県教育委員会といたしましては、生徒の英語力を的確に把握した上で、さらなる向上に向けた取組を進めていく必要があると考えております。
生徒の英語力を向上させるには、英語に親しみ、楽しく学べるようにすることをはじめ、実際に話したり書いたりする時間を多く取り、スピーキングやライティングのテストを小まめに行って、生徒自身が成長を実感しながら、継続的かつ意欲的に学習に取り組むようにすることが大切でございます。
そこで、昨年度は、特に効果的な取組を行っている小中高校における実際の授業の様子などを二十五本の教員研修用の動画にまとめ、広く県内の学校に提供し、活用を促しております。
また、今年度から、小学校三年生から高校三年生までの十年間の英語教育を一貫したものと捉え、地域の小中高校の教員が互いの授業を参観し、効果的な指導方法や相互の連携について話し合うことで、小中高校の英語教育をスムーズにつなげる仕組みをつくってまいります。
さらに、小中高校生が二日間、英語漬けの共同生活を送るイングリッシュキャンプや、愛知県立大学のネーティブ教員による授業体験、外国人留学生との交流など、英語に集中的に接し、学習意欲と自信を高めるための事業も行ってまいります。
こうした取組を通して、愛知の子供たちの英語力の向上に向け、しっかりと取り組んでまいります。
次に、ラーケーションの日についてお答えをいたします。
子供が保護者の休みに合わせて、ラーケーションの日を取ることで、平日に子供と保護者が一緒に、校外での学習活動を楽しみ、豊かな時間を過ごすことができると考えております。
また、校外での学習活動を子供が自ら計画し、実行することは、主体的に学ぶ力を高めることにつながり、計画の段階から保護者が関わることで、家庭の教育力を高める契機にもなると考えております。
こうした趣旨を十分に理解していただけるよう、保護者向けのリーフレットを作成し、計画から届出、実施までの流れや、活動例を掲載するとともに、専用のウェブページを立ち上げ、県内のラーケーションスポットを紹介するなど丁寧に周知を図ってまいります。
また、学校において、混乱なく円滑に導入をすることができるよう、手引書を作成するとともに、市町村の教育関係者向けの説明会を開催し、各学校が保護者にきちんと説明をできるよう進めてまいります。
ラーケーションの日の導入につきましては、五十三市町村におおむね御理解をいただき、何らかの形で取り組んでいただけることとなりました。
県といたしましては、給食の必要数の変動による会計処理など、増加する学校の教員負担を軽減するため、モデル事業に参画をする十九市町と、全ての県立の高校、特別支援学校に、校務支援員を新たに配置することとし、その補正予算を今議会にお願いしているところでございます。
こうした取組によりまして、ラーケーションの日の実施に向けた環境を整え、愛知発の休み方改革を前に進めることで、子供と保護者が一緒に学び、豊かな時間を過ごせるようにしてまいります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 14: ◯三十九番(山田たかお君) 本日はこれをもって散会し、明六月二十二日午前十時より本会議を開会されたいという動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
- 15: ◯議長(石井芳樹君) 山田たかお議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 16: ◯議長(石井芳樹君) 御異議なしと認めます。
明六月二十二日午前十時より本会議を開きます。
日程は文書をもって配付いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後二時八分散会