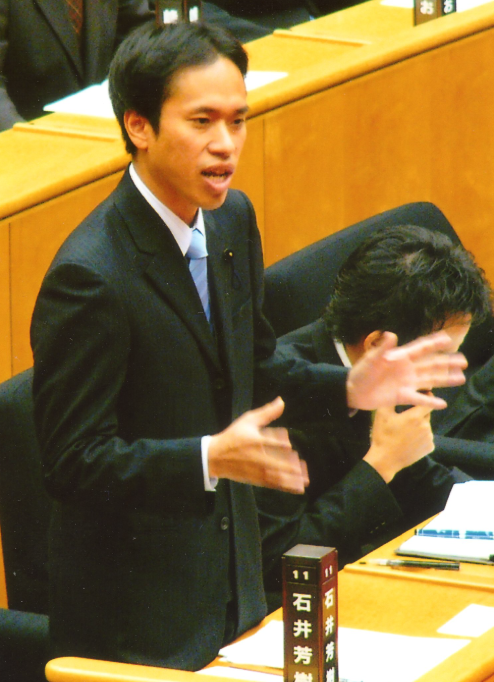県政報告
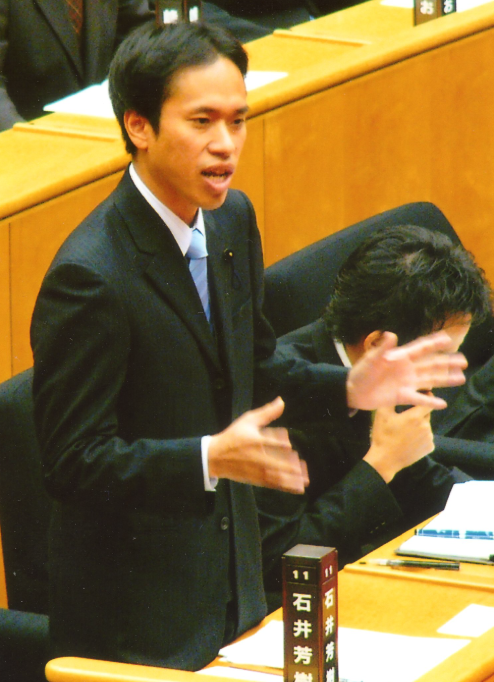
平成28年12月定例会(第2号)
2016年12月5日
(主な質疑)
- 午前十時開議
◯議長(鈴木孝昌君) ただいまから会議を開きます。
直ちに議事日程に従い会議を進めます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
日程第一 一般質問並びに第百四十四号議案平成二十八
年度愛知県一般会計補正予算から第百八十一号
議案愛知県スポーツ会館の指定管理者の指定に
ついてまで
- 2:◯議長(鈴木孝昌君) 第百四十四号議案平成二十八年度愛知県一般会計補正予算から第百八十一号議案愛知県スポーツ会館の指定管理者の指定についてまでを一括議題といたします。
なお、第百五十六号議案愛知県事務処理特例条例及び愛知県教育委員会事務処理特例条例の一部を改正する条例中、第二条愛知県教育委員会事務処理特例条例の一部改正について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十五条第四項の規定により、教育委員会の意見を徴しましたところ、妥当なものと認める旨の回答を、また、第百五十八号議案職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例等の一部改正についてのうち職員に関する事項について、第百五十九号議案職員の退職手当に関する条例等の一部改正について、第百六十号議案職員の給与に関する条例等の一部改正について、以上、三件の議案について、地方公務員法第五条第二項の規定により、人事委員会の意見を徴しましたところ、第百五十八号議案及び第百五十九号議案については、いずれも妥当なものであると認める旨の回答を、第百六十号議案については、趣旨、内容とも妥当なものであると認める旨の回答を受けましたので、御報告いたします。
これより一般質問並びに提出議案に対する質問を許します。
通告により質問を許可いたします。
石井芳樹議員。
〔八十三番石井芳樹君登壇〕(拍手)
- 3:◯八十三番(石井芳樹君) おはようございます。
それでは、自由民主党愛知県議員団を代表いたしまして、質問をしてまいります。
まず、質問に入ります前に一言申し上げたいと存じます。
去る十月二十七日三笠宮崇仁親王殿下が百歳で薨去されました。殿下におかれましては、長きにわたり我が国の平和と国民の福祉のために貢献してこられました。県民の皆様とともに謹んで心から哀悼の意を表したいと存じます。
それでは、県政諸課題について、順次質問をしてまいります。
質問の第一は、行財政運営についてであります。
初めに、県税収入の見通しと今後の財政運営についてお尋ねをいたします。
まず、県税収入の見通しについてお伺いをいたします。
最近の我が国の景気は、アジア向けを中心とした輸出の増加などにより国内総生産が三四半期連続でプラス成長となるなど、緩やかな回復基調が続いており、先行きにつきましても、雇用・所得環境の改善が続く中で個人消費が持ち直し、景気の回復が着実なものとなることが期待されております。
一方で、企業収益の状況に目を転じますと、先般発表された全国の三月期上場企業の九月中間決算では、トヨタ自動車を初めとする輸出関連企業の業績が、円高や新興国経済の減速により悪化したことなどから、全体の連結経常利益は前年の最高益から一転し、上半期としては四年ぶりの減益となっております。また、来年三月期の通期業績予想も、円高が引き続き重荷となり、減益となる見通しとなっております。
さらに、先日のアメリカ大統領選挙では、TPPからの離脱などの保護貿易主義的な公約を掲げるトランプ氏が勝利しました。為替や株価が不安定化しており、今後、本県の産業、経済に影響が及ぶことも懸念されております。
そこでお尋ねをいたします。
こうした昨今の景気動向などを踏まえ、今年度及び来年度の県税収入についてどのような見通しをされておられるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、今後の財政運営についてお伺いいたします。
来年度の地方財政の動向についてでありますが、八月に総務省が示した地方財政収支の見通しを見ますと、地方交付税が前年度から約七千四百億円も減少するなど、地方にとって厳しい内容となっております。
また、本県は本年度の当初予算で、自前の財源でもあります減債基金や財政調整基金について、既に一千八十五億円もの取り崩しを計上しており、基金残高は大幅に減少しております。
これに対して、歳出では、扶助費などの義務的経費が年々増加傾向にあります。十月に発表された平成二十七年国勢調査人口の確定値の集計結果を見ますと、本県の人口は、五年前に比べて全体で約七万人の増加となっておりますが、六十五歳以上人口は約二十七万人増加し、構成比も県人口の二三・八%を占めるまでになりました。高齢化の進行に伴い、医療や介護などに係る経費は今後も増加していくものと考えられます。
このような状況を見ますと、今後の財源確保の見通しは大変厳しいと考えざるを得ません。しかしながら、そうした中にあっても、県は、県民の安全・安心な暮らしを確保するため、防災・減災対策や社会資本の老朽化への対応なども着実に進めていかなければなりません。また、活力ある愛知をつくり上げるため、この地域の将来の発展に資する施策に重点的に取り組むことが必要であり、そうした心構えで積極果敢な政策展開を行っていくべきと考えます。
そこでお尋ねをいたします。
知事は、今年度から来年度にかけての収支状況をどのように見通し、本県の財政運営にどのように取り組んでいかれるのか、御所見をお伺いいたします。
次に、ふるさと納税についてお伺いをいたします。
ふるさと納税は、ふるさとに貢献したいという納税者の思いを実現できる上に、寄附者は個人住民税等からの控除により、実質的な負担をほとんど伴うことなく、地元特産品などの返礼品を得ることができるため好評を博しております。
また、寄附金の受け入れ団体においては、返礼品などの経費を除いた額が純粋な収入増となることから、多くの市町村が地方創生を推進し、地域を活性化するため、知恵と工夫を凝らし、この制度の積極的な活用を図っております。
とりわけ、平成二十七年度改正において、個人住民税等からの控除上限額が約二倍に拡大されるとともに、確定申告が不要となるふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されたことから、平成二十七年度の全国のふるさと納税の受け入れ額は前年度実績の約四・三倍となる約千六百五十三億円まで急激に増加しております。
一方、ふるさと納税によって、寄附者の住所地の自治体側においては、個人住民税から控除された分、税収が減少することになります。交付団体においては、その減収分のうち七五%が国からの交付税措置により自治体へ補填がなされ、残りの減収分の二五%が当該自治体の収入減となります。不交付団体においては、交付税による補填はありません。
そこでお尋ねをいたします。
現在のふるさと納税を取り巻く状況についてどのようにお考えか、知事の御所見をお伺いいたします。
質問の第二は、新しい時代に飛躍する愛知づくりについてであります。
まず、あいち航空ミュージアムについてお伺いをいたします。
本県は、国の国際戦略総合特区、アジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター形成特区の指定を受け、自動車に次ぐ産業として航空宇宙産業の育成、振興に取り組んでいるところであります。
この中核プロジェクトとして、県営名古屋空港及びその周辺地域では、国産初のジェット旅客機MRJの開発、生産が進められております。昨年十一月には初飛行が行われ、本年三月には空港隣接地にMRJ最終組み立て工場が竣工し、七月からは量産初号機の組み立てに向けた作業が開始されたところであります。
そして、本年九月にはMRJ飛行試験機一号機が、十一月には同四号機が、飛行試験拠点であるアメリカのグラントカウンティ国際空港に移送されました。今後、残る二機の試験機も順次移送され、型式証明取得に向け、約二千五百時間に及ぶさまざまな飛行試験が実施されると聞いており、MRJの開発が大きく加速されると思われます。
こうした動きを契機として、本県は、県営名古屋空港に来年十一月三十日のオープンを目指して、航空機をテーマとしたあいち航空ミュージアムの整備を進めております。このミュージアムのコンセプトは、航空機産業の情報発信、航空機産業をベースとした産業観光の強化、次代の航空機産業を担う人材育成の推進の三つであります。
これらのコンセプトを来場者に理解していただく上で、展示コンテンツが果たす役割は大変重要であります。単に見るだけではなく、来場者が航空機の魅力を感じられるような創意工夫を凝らすことが必要と考えます。
また、ミュージアムをこの地域の産業観光の牽引役とするためには、MRJ最終組み立て工場見学コースはもとより、鉄道や自動車等をテーマとした県内外の博物館を初めとする産業観光施設との連携、協力が重要と考えます。
そこでお尋ねをいたします。
あいち航空ミュージアムについて、次代の航空機産業を担う人材の育成にどのようにつなげていくのか、また、産業観光の拠点としてどのような取り組みを行っていくのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、愛知県国際展示場についてお尋ねをいたします。
まず、愛知県国際展示場の運営についてお伺いをいたします。
本県の大規模展示場については、十月に整備事業者が決定され、今議会には、工事請負契約の締結についての議案が提出されております。さらには、民間事業者による自由度の高い公共施設等運営権制度、いわゆるコンセッション方式を採用する愛知県国際展示場条例案が提出されているところであります。
展示会産業は、人口や産業の集積を背景として首都圏に集中しており、我が国を代表する展示場である東京ビッグサイトでは年間約三百件、パシフィコ横浜、幕張メッセでも年間約二百件の展示会やイベントが開催されております。
これらの展示場のうち、幕張メッセでは、施設管理者みずからが催し物を企画したり、展示場の壁面を活用した広告事業を展開するなど、収益の確保に努めております。
また、関西圏においては、インテックス大阪で年間約二百件の展示会やイベントが開催されておりますが、平成二十五年度から民間事業者と財団の共同運営事業体による管理に切りかえるとともに、展示会開催のノウハウを持つ内外の民間事業者との連携を始めるなど、展示会誘致に向けて積極的な取り組みを行っております。
愛知県国際展示場は、これら首都圏、関西圏の主要展示場と競争していかなければならず、工夫を凝らした運営を行い、存在感を発揮していかなければなりません。
そこでお尋ねをいたします。
愛知県国際展示場は、コンセッション方式を採用することとしておりますが、どのような展示場運営を目指しているのか、知事の御所見をお伺いいたします。
続きまして、愛知県国際展示場を核とした地域の活性化についてお伺いをいたします。
愛知県国際展示場は、交流による新たなビジネスマッチングの機会やイノベーションの創出のための産業インフラであります。本県の産業競争力をさらに高めるとともに、我が国の発展に貢献していくことを大いに期待しております。
先週十二月二日には、早速、二〇二〇年に愛知県国際展示場において、ワールドロボットサミットが開催されることが決定いたしました。物づくりや家事手伝いなどでロボットの実用性を競う国際大会とのことであり、開催が大変楽しみであります。
また、中部国際空港において、相次ぐ新規就航による航空旅客が一千万人を突破し、新たな商業施設や新ターミナルの整備をされるなど、大規模展示場が建設される空港島は、今後、展示場を核に大きく変貌し、本県の中でこれまで以上、より大きな役割を担っていくのではないかと思います。
そこでお尋ねをいたします。
愛知県国際展示場を、産業振興とさらなる地域の発展にどのようにつなげていかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、農業総合試験場における研究機能の充実強化についてお伺いをいたします。
農業総合試験場は、明治二十六年、名古屋市東区に農事試験場として発足をいたしました。そして、昭和四十一年には、県内各地で分散していた研究施設を長久手市に統合して、ことしでちょうど五十周年を迎えております。先月五日に農業総合試験場で開催された記念式典には、私も知事とともに出席をさせていただきました。その際、稲や小麦、トマト、カーネーションなどのすぐれた品種や菊の電照栽培技術、水稲のV溝直播技術などの成果について紹介がありました。
しかし、近年の農業をめぐる情勢は大きく変化をしてきております。農業従事者の減少、高齢化、消費者ニーズの多様化、地球温暖化による異常気象の頻発やグローバル化の進展による国内外での産地間競争の激化などを背景として、生産者の方々からは、さまざまなニーズに合った新品種の開発やICTなどの近年著しく発展している先端技術を活用し、生産性を飛躍的に向上させたり、農作業の負担を軽減して大幅な省力化につながる新技術の開発などが強く求められております。
本県は、全国第七位の農業産出額を誇っておりますが、本県の農業のさらなる発展のためには、こうした生産者の要望にしっかりと応え、全国をリードできる新品種や新技術の開発が必要であります。
また、農業総合試験場の近隣には、全国一の物づくり県の技術を支える知の拠点があり、ノーベル賞受賞者を輩出している名古屋大学を初めとする多くの研究機関も立地をしております。農業総合試験場においては、これらの研究機関や企業との連携により、一層の技術開発を進めていただくとともに、これらの研究機関に劣らない研究成果を期待するものであります。
農業総合試験場では、今日までの五十年間においても、次世代施設園芸に関する研究体制の充実や情報発信機能の強化など、時代の要請に沿った研究基盤の整備が進められてきたと伺っております。しかしながら、これからの五十年を考えるとき、ますます多様化、高度化するニーズに的確に応えていくためには、十分な研究費の確保や最新設備の導入などにあわせて、研究機能の一層の充実強化を図っていくことが重要であると考えます。
そこでお尋ねをいたします。
本県農業の品種、技術の研究開発を担っている農業総合試験場の研究機能の充実強化について、どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
質問の第三は、活力と魅力あふれる愛知の実現についてであります。
まず、愛知の山車祭りの保存、継承についてお伺いいたします。
先月、明治用水が世界かんがい施設遺産に登録されたところでありますが、このたび、尾張津島天王祭の車楽舟行事、知立の山車文楽とからくり、犬山祭の車山行事、亀崎潮干祭の山車行事、須成祭の車楽船行事と神葭流しの五件の祭礼が、山・鉾・屋台行事としてユネスコ無形文化遺産に登録されることになりました。
この山・鉾・屋台行事は、全国三十三件の国の重要無形民俗文化財に指定されている祭礼で構成されておりますが、本県からは全国最多となる五件の祭礼が選ばれております。
また、本県には、この五件の祭礼だけでなく、百五十以上の山車祭りがあります。四百両以上の山車があり、そのうち百五十両近くの山車にはからくりが搭載されていると聞いております。まさに、本県は、山車文化の中心地、山車王国と言ってもよいのではないでしょうか。
ユネスコ無形文化遺産登録を契機として、国内外において、愛知の山車祭りへの理解が一層深まり、観光集客につながることが期待されます。
一方で、山車祭りの保存、継承には、後継者不足や山車の維持管理に大きな課題があると聞いております。今回のユネスコ無形文化遺産への登録を一過性のお祭り騒ぎで終わらせることなく、末永く愛知の山車祭りを保存、継承し、さらには、観光資源としての活用に結びつけていくことが大切と考えます。
そこでお尋ねをいたします。
今後、愛知の山車祭りの保存、継承及び発信などにどのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、生物多様性愛知目標の達成に向けた取り組みについてお伺いをいたします。
二〇〇五年に開催された愛知万博は、環境万博とも言われ、本県が環境首都あいちとして歩み始めた契機となりました。その後、二〇一〇年には生物多様性COP10が開催され、二〇一四年にはESDに関するユネスコ世界会議が開催されるなど、本県の環境についての取り組みは、世界中から注目を集めてまいりました。
中でも、COP10では、生物多様性に関する世界目標として愛知目標が採択されており、本県は、その名前にふさわしい取り組みを積極的に進めていく責任があります。
こうした中、本県は、平成二十五年三月にあいち生物多様性戦略二〇二〇を策定しております。そして、緑地や水辺を適切に配置し、生き物の生息生育空間をつなぐ生態系ネットワークの形成と事業者等に対して開発などにおける自然への影響の緩和を求めるあいちミティゲーションの二つの中核的取り組み、いわゆるあいち方式による生物多様性の取り組みを進めているところであります。
このうち、生態系ネットワークの形成については、戦略策定のモデル事業として、県民や大学、事業者、NPO、行政など、多様な主体が協働する三つの生態系ネットワーク協議会が設立されました。
私の地元、長久手市を含む名古屋東部丘陵地域においても、平成二十三年三月に東部丘陵生態系ネットワーク協議会が組織され、この地域に立地する二十三の大学が中心となり、自然再生カレッジと銘を打った連続講演会や、大学キャンパス内へのビオトープの設置などが進められております。
こうした先導事業を踏まえ、県は、生態系ネットワーク協議会の立ち上げを支援しており、先月には、県内九つ目の協議会が尾張西部に設立されました。
今後も、愛知目標の達成に向け、あいち方式による生物多様性の取り組みを着実に推進していかなければなりません。
また、COP10で採択された愛知目標は、世界全体の目標であり、県内で取り組みを推進するだけでは十分ではありません。
現在、メキシコで開催されているCOP13は、愛知目標の目標年度である二〇二〇年に向けて重要な役割を担う会議であります。本県は、愛知目標を決定したCOP10の開催地として、世界中の取り組みをリードしていくくらいの意気込みで会議に臨んでいかなければならないと考えます。
そこでお尋ねをいたします。
愛知目標の達成に向け、今後、県内においてどのように取り組まれていくのか、また、世界に向けてどのような役割を果たしていくのか、知事の御所見をお伺いいたします。
質問の四は、安全・安心な暮らしの実現についてであります。
まず、災害時の産業の早期復旧に向けた強靱化の取り組みについてお伺いをいたします。
さきの熊本地震では、甚大な被害が発生し、その対応について、本県の地震防災対策を進める上でも参考となる現場の実態に即した課題が明らかとなりました。
私も先日、熊本市役所で当時の被災状況を伺ってまいりました。さまざまなお話を伺ってまいりましたが、中でも特に印象に残っていることは、全国から支援物資は送られてくるものの、行政のマンパワー不足により、発災後四日から五日まで水一本すら配ることのできなかった避難地域もあり、日ごろから住民みずから水や食料等を備蓄していただく必要があることを強く認識したとのことであり、公助の限界と自助の必要性を訴えておられました。
本県では、熊本地震の課題について、外部の有識者の意見を踏まえた検討が進められており、今年度中に対応策がまとめられる予定であります。ぜひとも、県民の皆様への水や食料の備蓄についての啓発や支援物資の供給体制の見直しを盛り込んだ内容としていかなければなりません。
また、熊本地震では、工場が被災して操業が一時停止となり、部品の供給が滞り、その影響が被災地のみにとどまらず、日本の広範囲に及ぶ事態となりました。
本県は、昨年度に愛知県地域強靱化計画を策定し、愛知、名古屋を中核とした中部圏の社会経済活動が維持されるよう取り組みを進めているところであります。この地域は、物づくりで我が国の産業、経済をリードしており、大規模災害が発生した際に、産業の迅速な復旧がなされなければ、国全体の産業・経済活動に与える影響は非常に甚大なものとなることが想定されます。
また、災害による被害を最小限に抑え、産業を早期に復旧させることは、雇用、就業を確保し、県民の皆様の生活再建を図る上でも大変重要であります。こうした取り組みには、企業の努力だけではなく、行政の支援が不可欠であります。また、この地域には防災、減災にすぐれた研究を実施し、人材を育成していただいている大学が数多くあり、大学との連携も重要と考えます。
そこでお尋ねをいたします。
本県の産業を守るためには、行政だけでなく、産業界や大学と連携して事前の対策を進めていく必要があると思いますが、どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、重症心身障害児者の施設への受け入れについてお伺いをいたします。
本県の重症心身障害児者が利用できる入所施設は、全国的に見ると大変少ない状況にありました。平成二十五年時点では、国立病院機構が二カ所と県立の二カ所の四カ所だけであり、人口一万人当たりの病床数は、当時、全国最下位でありました。
こうした中、知事は障害者福祉減税基金を新たに設け、民間による施設の整備を積極的に後押ししてこられました。この基金を活用して、県内で初めての民間による重症心身障害児者施設として、平成二十八年一月に一宮医療療育センターが開所いたしました。また、今年度には豊川市内において、県内二カ所目の民間施設となる信愛医療療育センターの整備が始まり、来年の夏にはオープンする予定であります。
さらに、平成二十八年四月には、岡崎市内に県立三河青い鳥医療療育センターが開所いたしました。この施設は、肢体不自由児施設である第二青い鳥学園の移転改築に当たり、従来の肢体不自由児病床に加え、新たに三病棟九十床の重症心身障害児者病床を整備したものであります。
しかしながら、本県においては、まだまだ多くの重症心身障害児者の方々が御家庭で必要な医療や介護を受けておられます。四十代、五十代となられた方々にあっては、介護される御家族も七十代、八十代と高齢化しておりますが、今でも、日々障害のある我が子を支え続けておられると聞いております。
こうした状況の中で、施設への入所の必要性がますます高まっております。この四月に開所した三河青い鳥医療療育センターでは、百名を超える入所希望者がありました。それに対して、医療従事者の確保が困難であったために、新たに整備した三病棟のうち一病棟だけの運用に現在とどまっております。
高齢で介護が困難となっている御家族の中には、一刻も早い入所を希望されている方もおみえになります。建物は既に整備されておりますので、医療従事者を早期に確保し、残りの二病棟の運用を開始することが望まれます。
そこでお尋ねをいたします。
今後、三河青い鳥医療療育センターへの受け入れ体制について、どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、新しい愛知県住生活基本計画の策定についてお伺いをいたします。
本県は、住生活基本法に基づき、平成二十三年度から平成三十二年度までの十年間を計画期間とする愛知県住生活基本計画二〇二〇により、地震に強い住まい・まちづくりや良好な市街地整備の推進など、各種住宅施策に取り組んでおります。
一方、国においては、本年三月に住生活基本計画、いわゆる全国計画が改定されました。
改定された全国計画では、少子・高齢化、人口減少社会を正面から受けとめ、さまざまな支援を通じて若年世帯、子育て世帯が必要とする質や広さの住宅に居住できるようにすることや、放置された空き家が急増していることを受けて、空き家に関する数値目標を初めて設定するなど、新たな住宅政策の方向性が示されております。
ところで、本年は、熊本地震や鳥取地震といった大規模な地震が相次ぎました。本県においても、南海トラフ巨大地震の発生が危惧されております。住まいの安全を考える上で、ますます大規模自然災害への対応が喫緊の課題となっていると強く感じております。
また、先ごろ発表された平成二十七年国勢調査によると、本県は、人口増加を果たしている数少ない県であり、少子・高齢化のスピードも緩やかな県となっております。そして、本県の特徴として、大都市圏でありながら、高い出生率や、三世代同居、近居の多さに伴う、子育て期における家族の支援を受けやすい環境、自然豊かでゆとりある住環境などが挙げられます。
さらに、二〇二七年に予定をされているリニア中央新幹線の開業は、この地域に大きなインパクトをもたらすことから、住まい・まちづくりの分野でも、その効果をうまく生かしていくことが重要だと考えます。
そこでお尋ねをいたします。
本県にふさわしい住まい・まちづくりの実現に向けた、新しい住生活基本計画を策定することが必要だと考えますが、どのような方針なのか、知事の御所見をお伺いいたします。
次に、車両運転中のながらスマホ対策の強化についてお伺いをいたします。
近年、携帯電話やスマートフォンの急速な普及に伴い、画面を見ながら歩いたり、自動車や自転車を運転する行為、いわゆるながらスマホが目立つようになっております。これは、画面に気をとられて、操作をする人の注意力が散漫となるため、思わぬ事故やトラブルを引き起こすおそれがあり、極めて危険な行為であります。
こうした中、スマートフォン向けゲーム用アプリ、ポケモンGOの日本での配信が始まった七月二十二日以降、ながらスマホをする人が激増し、公共マナーや交通ルールを守らないことによるトラブルが多発するなど、ながらスマホが社会問題化しております。
とりわけ車両運転中のながらスマホにつきましては、重大な事故を引き起こす危険性が高く、喫緊の課題となっております。ポケモンGOの操作が原因と見られる交通死亡事故が全国で三件発生しておりますが、大変残念なことに、そのうちの二件は本県で起きたものであります。八月には、春日井市において自転車で横断中の女性がはねられ、十月には、一宮市で下校途中の九歳の小学生が横断歩道上ではねられるという、大変痛ましい事故がありました。
今後、拡張現実の技術を使った新たなゲームの登場も予想されますので、厳罰化を含めた車両運転中のながらスマホ対策の強化が必要と考えます。
我が党本部の交通安全対策特別委員会におきましては、道路交通法等の改正を含む事故防止対策について議論を始めたところであります。
そこでお尋ねをいたします。
車両運転中のながらスマホに関して、県はこれまでどのような対策を取ってきたのか、また、今後どのような対応をしていかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
また、車両運転中のながらスマホに関して、警察本部はこれまでどのような対策を取られてきたのか、また、今後どのように対応していかれるのか、警察本部長の御所見をお伺いいたします。
最後の質問は、次代を担う人づくりについてであります。
子供たちの個性や可能性を伸ばす県立学校づくりについてお尋ねをいたします。
まず、県立高等学校教育推進基本計画(高等学校将来ビジョン)について、お伺いをいたします。
本年二月に策定されたあいちの教育ビジョン二〇二〇では、あいちの人間像を実現する基本的な取り組みの一つとして、個に応じたきめ細かな教育を充実させ、一人一人の個性や可能性を伸ばすことが掲げられ、その取り組みの柱として、多様な学びを保障する学校・仕組みづくりや特別支援教育の充実が挙げられております。
そして、高等学校については、高等学校将来ビジョンと平成三十一年度までを計画期間とする第一期実施計画が策定され、魅力ある県立学校づくりに向けた取り組みが進められていると承知をしております。
この計画に基づいて、来年四月に二部制単位制の定時制高校である城北つばさ高校が開校することとなっており、不登校や中途退学などさまざまな事情を持つ生徒の学びの場となればと期待するところであります。
しかし、本年十月に文部科学省から発表された生徒指導上の諸問題に関する調査結果によれば、平成二十七年度の本県の中学校における年間三十日以上の欠席がある生徒数は七千八十四人、率は三・二六%、高校の中退者は二千百八十八人、中退率は一・〇%であります。
城北つばさ高校一校の新設にとどまらず、引き続き、生徒の多様なニーズに対応した高校の設置を早急に進めていく必要があると考えます。
このほか、実施計画には、長久手高校に看護系の大学や専門学校等と連携して実践的な学習を行う医療・看護コースを設置することを初めとした普通科への新たなコースの設置や社会ニーズに対応する専門学科の学科改編などが示されております。
いずれも時代の要請に応える重要な取り組みであると考えますが、中でも、グローバル化に対応するコースや系統的なキャリア教育で実績を上げている総合学科の新たな設置などは、早期実現が期待されるところであります。
そこでお尋ねをいたします。
高等学校将来ビジョンの第一期実施計画に基づいて、今後、さまざまな学びの場の整備にどのように取り組んでいかれるのか、教育長の御所見をお伺いいたします。
続きまして、愛知県特別支援教育推進計画(愛知・つながりプラン)についてお伺いをいたします。
特別支援学校については、愛知・つながりプランが策定され、この計画に基づいて、現在、半田特別支援学校と春日台特別支援学校の過大化による教室不足解消のため、それぞれ大府市と瀬戸市での新設開校に向け、建設工事等に着手されております。
しかしながら、安城と三好特別支援学校の過大化による教室不足やその他の教育諸条件の整備などの課題が残っております。例えば、特別支援学校には、体温調節も難しいお子さんもおられますが、教室の冷房設備は十分に整備されているとは言えず、夏場の体調管理が難しいとの現場の声も聞いております。また、障害の特性上、洋式トイレしか使用できないお子さんもいらっしゃいますので、これらの早期の改善が望まれます。
そこでお尋ねをいたします。
愛知・つながりプランの推進に向け、特別支援学校の過大化による教室不足の解消やその他の教育諸条件の整備について、今後どのように取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。
以上、自由民主党愛知県議員団を代表して、県政各般にわたるさまざまな課題について質問をしてまいりました。明快な御答弁を期待いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
〔知事大村秀章君登壇〕
- 4:◯知事(大村秀章君) 自由民主党愛知県議員団の石井芳樹政調会長の質問にお答えをいたします。
初めに、県税収入の見通しについてのお尋ねであります。
まず、今年度の県税収入についてでございます。
主要税目である法人二税につきましては、本年三月期の企業収益が比較的堅調でありましたことから、これまでのところ、当初の見込みを上回って推移をいたしております。今後、三月期決算法人の中間申告の状況などを見きわめる必要はございますが、県税全体では当初予算額は確保できるのではないかと考えております。
続きまして、来年度の県税収入の見通しについてでございます。
来年度の法人二税収入に影響を及ぼします平成二十九年三月期の上場企業の連結経常利益は、全産業ベースで減益に転じる見通しでありますが、その中でも本県の主要産業である自動車関連産業は、円高により二割を超える大幅な減益が見込まれております。
こうした企業の厳しい収益見通しに加えて、さらに、法人事業税の外形標準課税が再拡大された影響から、来年度の法人二税収入は大幅な減収が見込まれ、米国の大統領選挙後、為替は現在、企業の想定よりも円安で推移はしておりますものの、県税収入は厳しいものにならざるを得ないと考えられます。今後、主要企業に対する聞き取り調査を初め、景気動向や税制改正による影響なども踏まえまして、来年度の県税収入の見込みを固めてまいりたいと考えております。
続いて、今後の財政運営についてであります。
来年度は、歳入の大宗をなす県税収入が厳しい状況にならざるを得ないと考えられる一方、歳出面では、義務的経費の増加が見込まれることから、多額の収支不足が予想され、これまで以上に困難な状況になるものと見込まれます。
したがいまして、来年度の予算編成に向けまして、まずは、今年度当初予算で取り崩すこととした基金残高を可能な限り回復することが喫緊の課題であります。その上で、今後の県税収入や地方財政対策の動向を慎重に見きわめながら、県債や基金を最大限活用して財源を確保することも検討していく必要があると考えております。こうした対応により、財政調整基金や県が任意に積み立てている減債基金は枯渇することとなります。
また、歳出につきましても、来年度の予算編成を通じて、その全般にわたり、従来にも増して重点化、効率化に努めていかなければなりません。このため、去る十月二十八日には、政策的重要経費の原則一〇%削減の節減を行うことなどを内容とする一段と厳しい予算編成方針をお示ししたところであります。
こうした県としての取り組みに加え、今後も全国的に社会保障関係経費を初めとする義務的経費が増加し続ける傾向にあることを踏まえますと、地方が安定的な財政運営を行うには、地方一般財源総額を増額確保することが必要であります。十一月九日には、私みずから、地方税財源の充実強化について国に要請してきたところであり、これから本格化する国の来年度予算編成に向けた議論を注視するとともに、適時適切に本県の考えを主張してまいりたいと考えております。
今後の本県財政は非常に難しい局面が続きますが、財源の確保と歳出の見直しに全力を挙げ、めり張りのついた予算編成に取り組んでまいりますとともに、日本一の産業力をさらに強くし、将来の税収増加につなげ、活力ある愛知をつくってまいりたいと考えております。
次に、ふるさと納税についてであります。
そもそも、ふるさと納税は、出身地や被災地等を応援しようという、とうとい志を例外として認めようと始まった制度であり、多くの自治体がふるさと納税を活用して地域の活性化や振興に取り組まれていることは承知しております。私は、ふるさと納税の趣旨に沿った取り組みは否定するものではなく、例えば地域の福祉や子育てなど、使い道を明らかにして寄附を募るクラウドファンディングのような活用方法や被災地への寄附は大変意義があることだと考えております。
しかしながら、豪華な返礼品でふるさと納税の獲得競争が行われている今の姿は深刻な問題であると認識しており、私はこれまで、新聞紙面や全国知事会の場においてたびたび意見を申し上げてまいりました。
ふるさと納税は、寄附者の住む自治体から寄附の受け入れ先の自治体へと税が移転されるものでありますが、受け入れ先の自治体が豪華な返礼品を贈るということは、寄附額の一部が返礼品の買い取りに使われているということです。これは、日本全体で見れば、福祉や教育、インフラ整備など本来必要な行政サービスに充てるべき税がその分失われることとなります。
また、返礼品に地元の特産品を使用することで、地域振興に資するという意見もありますが、行政が地元の特産品を税金で買い取ることは形を変えた公共事業であり、返礼品の規模が拡大すれば、本来競争力があるはずの地場産業も自治体の買い取りに依存し、長い目で見れば競争力を弱めることになりかねないという危惧もあります。
そもそも、住民税は地域の行政サービスに係る経費を住民が分かち合って負担するというものであり、要は町内会の会費という性格であるわけでありまして、返礼品によるふるさと納税の獲得競争が拡大し続ければ、受益と負担の原則という住民税の原理原則も大きくゆがめられることにもなります。
本県では、ふるさと納税による寄附の受け入れ額から控除により取られてしまう額を差し引くと、約三十億円の税収の減であり、県内市町村も合わせると約五十三億円の税収の減という状況であります。こうした税の減収分については、地方財政措置という仕組みはあるものの、これだけの税が県内から流出しているということは看過できません。また、それが返礼品に使われてしまい、行政サービスに還元されていないことは大変問題であると認識しております。
全国的に見ても、都道府県単体でいわゆる黒字になっているのは三県だけであり、東北の被災県も全てマイナスというのはいかにもおかしいのではないかと思います。
このようなことから、ふるさと納税の制度をゆがめている原因はまさに返礼品であり、返礼品のあり方を見直さなければ根本的な解決につながらないと考えております。
国は、自治体に豪華な返礼品の自粛を求めておりますが、それだけでは解決につながりません。返礼品については、何らかの具体的な規制が必要であり、私は、例えば返礼品の規模を寄附額の一割までとする制限を設けることについて提案をしているところであります。今後も、根本的な解決に向け、問題提起を続けてまいりたいと考えております。
次は、あいち航空ミュージアムについてのお尋ねであります。
あいち航空ミュージアムについては、現在、来年十一月末オープンに向け、建物の建設及び展示コンテンツの整備に取り組んでおります。
展示コンテンツにつきましては、来場者の方々が航空機の歴史や進化、さらには飛ぶ仕組みを学ぶことができるよう、参加・体験型のプログラムを中心に整備してまいります。
先般、友好交流及び相互協力に関する覚書を締結したワシントン州にあるシアトル航空博物館や青森の三沢航空科学館においても、小中学生から技術者まで幅広い層を対象として、さまざまな教育プログラムが実施されております。
今後、航空機関連産業や航空会社などで活躍できる人材を育成するため、こうした実績のあるミュージアムと連携を図りながら、子供も大人も楽しんで学べる展示コンテンツにしてまいります。
また、産業観光の拠点として、MRJ最終組み立て工場見学コースのほか、トヨタ産業技術記念館、リニア・鉄道館等との連携を図り、共通観覧券の発行や周遊ツアーを造成するほか、海外への情報発信を積極的に行い、訪日客の方々にも物づくり愛知の魅力を体感いただけるよう、しっかりと取り組んでまいります。
次に、愛知県国際展示場の運営についてお答えをいたします。
本県の国際展示場は、物づくりなど愛知の産業力をさらに飛躍させるために不可欠な産業インフラの一つであります。
この展示場の運営に当たっては、愛知の産業特性を生かした展示会、イベントの開催など、幅広い分野で多くの利用をいただき、できる限り高い稼働率を実現していくことが必要となります。そのため、指定管理者制度と比較して、より長期的な視点に立った営業活動や民間の創意工夫を生かした自由度の高い経営が実現できるコンセッション方式を採用することといたしました。
条例案では、展示ホールの標準的な料金を首都圏、大阪の展示場の平均の約六割に設定いたしましたが、コンセッション方式を採用することで、運営事業者みずからの経営判断で自由な料金設定が可能となります。例えば、展示会の種類に応じターゲットを絞った戦略的な料金設定や割引など、柔軟な対応をすることができます。
また、国内外からのアクセスのよさや空港の商業施設等との連携など、国際空港隣接という他の展示施設にはない特色を生かした営業戦略も可能であります。
こうした運営面に加え、今後進める施設整備においても、施設の使い勝手のよさ、光熱水費など低廉な運営コストを実現していくこととしており、施設、運営の両面から競争力の高い展示施設となるよう取り組んでまいります。
続いて、愛知県国際展示場を核とした地域の活性化についてであります。
本県の国際展示場は、後背地に中堅、中小を含めた裾野の広い産業集積があること、国際空港に隣接することに特色があります。この特色を生かして、自動車、航空宇宙、ロボットなどの主要産業分野や、環境、新エネルギーといった新たな分野で展示会、イベントを積極的に誘致、開催してまいります。そうした取り組みにより、新たな交流、ビジネスマッチングを生み出し、本県の産業、経済のみならず、我が国の発展に寄与していきたいと考えております。
国際展示場を整備する空港島及びその周辺地域では、二〇一九年までに新たな複合商業施設や新ターミナルの整備、新規ホテルの立地などが相次ぎます。
本県としても、この地域が国際展示場を核に、新たな交流、にぎわい、集客の拠点となるよう、二〇一九年秋の開業を目標に着実に整備を進めてまいります。
開業後は、二〇二六年のアジア競技大会や、二〇二七年度のリニア開業などを見据え、国際展示場と周辺施設が本県全体の発展に重要な役割を果たしていけるよう、空港会社や地元市町等と連携して取り組んでまいります。
また、そうした中で、先週二日の金曜日、石井県議も触れられたように、大変うれしい決定がありました。二〇二〇年に日本が初めて開催するロボット国際大会、ワールドロボットサミットの開催地を、この愛知県国際展示場とすることを経済産業省が決定し、発表していただきました。
ワールドロボットサミットは、ロボットの研究開発や普及を加速させるために、さまざまなロボットの競技と展示を行う国際大会で、二〇二〇年十月上旬の一週間程度の開催予定であります。
本県は、この空港島に整備する大規模展示場を会場とし、かねてより取り組んでおります、あいちロボット産業クラスター推進協議会のネットワークを最大限に生かし、地域の企業、大学などが一丸となって本大会の運営に協力することを提案いたしました。
また、本大会を盛り上げる独自企画として、研究開発プロジェクトのロボット開発成果を披露するデモンストレーションや地域の企業、大学の施設を視察するツーリズムなどの実施を提案いたしました。我々の提案を高く評価していただき、愛知県での開催を決定していただいたことに対して感謝をいたします。
今回の決定を受け、経済産業省や関係機関と連携しながら、本大会の成功に向けて全力で取り組むとともに、本大会を契機とし、ロボット技術の向上、国内外の企業や大学との交流、さらには、さまざまな場で活躍するロボットの利用促進を図り、本県及び日本のロボット産業の国際競争力強化につなげてまいります。
いずれにしても、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックで世界中が日本に注目するときに、両大会に続いて、ロボットのオリンピックともいうべき第一回のワールドロボットサミットという夢のある国家プロジェクトを本県で開催できることは大変光栄なことであり、私の思いといたしましては、ぜひ、二〇二〇年をオリンピック・パラリンピック、そして、このロボットのオリンピックとしてのワールドロボットサミットの三本柱で大いに盛り上げていきたいと考えております。
これも、その前年、二〇一九年までに国際展示場を整備することによるものであります。これを弾みとして、さらに愛知県国際展示場を本県全体の活性化につなげていけるよう取り組んでまいります。
次に、農業総合試験場における研究機能の充実強化についてであります。
本県は、農業産出額が中部地区最大、全国三番手グループに位置する有数の農業県でありますが、近年、農業を取り巻く環境が大きく変わりつつある中で、本県農業の競争力をさらに高めるには、試験研究の役割がこれまでにも増して重要であります。
このため、本年三月に策定した試験研究基本計画二〇二〇において、百二十の研究目標を設定し、幅広い需要に応える戦略的な品種開発や強い農業経営の確立に向けた技術革新などに取り組んでいるところであります。
具体的には、品種開発においては、他産地に負けない大粒でおいしいイチゴや温暖化によりふえる害虫被害を軽減する稲などについて、農業団体や国の研究機関と共同で開発いたします。また、技術開発においては、先端技術を持つ民間企業等と連携して、収穫補助ロボットによる労働負担の軽減やドローンを用いた農作物の生育診断による生産性向上などに重点的に取り組むこととしております。
今後も、本県農業の発展のため、さまざまなニーズや社会情勢の変化を踏まえ、研究分野を重点化するとともに、全国一の物づくり県である愛知の強みを生かした産学官連携を推進する体制を充実させ、農業総合試験場の研究機能をより一層強化してまいります。
次は、愛知の山車祭りの保存、継承についてお尋ねをいただきました。
山車祭りがユネスコ無形文化遺産に登録されたことは、世界的にも評価されたというあかしであり、大変誇らしく思っております。
来月二十九日には、ウインクあいちにおいて、県と関係六市町の共催で登録記念行事を開催し、各保存団体や県民の皆様と盛大にお祝いするとともに、愛知の山車祭りの魅力を広くアピールしたいと考えております。
昨年十二月には、県内全ての山車祭りの保存、継承、発信を目的に、私が呼びかけてあいち山車まつり日本一協議会を設立いたしました。現在までに三十一市町、七十保存団体に加入いただき、協議会の事業として、本年六月に山車の保存修理に関する研修会を、九月に祭りの伝承についてのシンポジウムを実施するなど、山車祭りのさらなる保存、継承に取り組んでいるところであります。
また、来年二月二十六日には、名古屋市内のショッピングモールにおいて、あいち山車まつりフェスタを開催し、多くの県民の皆様に山車祭りの魅力を体感していただくとともに、協議会のホームページを開設するなど、愛知の山車祭りを広く発信し、観光集客に結びつける取り組みも進めてまいりたいと考えております。
今回の無形文化遺産登録を弾みとして、市町村や保存団体と力を合わせ、愛知の山車祭りの一層の盛り上げを図ってまいります。
続いて、生物多様性愛知目標の達成に向けた取り組みについてお答えをいたします。
愛知目標の達成には、地域の生態系を広域的に管理し、多様な主体に働きかけることができる県の役割が大変重要であります。
本県では、各地域において、NPO、企業、大学、行政等が連携して生態系の保全を図る協議会の設立を支援してきており、先月九つ目の協議会設立をもって県全域をカバーする体制が整いました。
今後は、各協議会の取り組みのさらなる充実を図るとともに、先進的な活動事例を現地で学ぶワークショップや、関係者が一堂に会し成果や課題を共有するフォーラムの開催などにより、協議会の連携強化を図り、本県の生物多様性の取り組みをより一層活性化してまいります。
また、本県は、愛知目標が採択されたCOP10の開催地として、目標達成に向け世界をリードしていく役割があると考えます。そのため、今回のCOP13には私みずから赴き、本年八月に海外の五つの広域自治体と立ち上げた愛知目標達成に向けた国際先進広域自治体連合として、共同声明の採択、国際自治体会議での発表、フォーラムの開催などを行い、世界の取り組みの強化を働きかけてまいります。
こうした国内外の取り組みを積極的に行うことにより、愛知目標の達成に向け、しっかり貢献してまいりたいと考えております。
次は、災害時の産業の早期復旧に向けた強靱化の取り組みについてであります。
本県は、圧倒的な産業集積を誇る日本一の産業県であることから、南海トラフ巨大地震などの大規模災害により本県が被災し、産業の復旧がおくれることになれば、我が国の経済や国民生活に多大な影響を及ぼすことになります。それを防ぐためには、まずは、企業みずからがBCPの策定等により防災力を高めることが必要であります。また、県としても個々の中小企業のBCPの策定を支援するだけでなく、産業界や防災、減災に関する最新の知見を有する大学等の研究機関とも連携し、平時から産学官が総力を挙げ、災害時における産業の早期復旧を実現するための取り組みを進める必要があります。
そのため、本県といたしましては、中部経済連合会や名古屋大学などとともに、産業の早期復旧に必要な対策の立案やそれを担う人材の育成等の取り組みを戦略的に推進する体制の構築に向けた協議を年内にも始めてまいります。そして、来年度には産学官が連携し、産業の早期復旧に取り組む体制を構築してまいりたいと考えております。
このように、産学官の連携をより一層深め、災害に負けない強さとしなやかさを備えた、いわゆるレジリエンスな愛知の構築に向け、しっかりと取り組んでまいります。
続いて、重症心身障害児者の施設の受け入れについてお答えをいたします。
本県では、重症心身障害児者の方を御自宅で献身的に介護されている御家族の半数近くが、ここ数年のうちに六十歳以上になると見込まれております。こうした方々が、身近な地域で医療や介護などの支援が受けられる施設の整備を促進し、地域で安心して生活していただけるようにしたいというのが私の強い思いでございます。
三河青い鳥医療療育センターにおきましては、医療従事者の確保が困難なことから、まずは一病棟三十六床でオープンいたしましたが、西三河地域を中心に百一名の方から入所希望がありました。改めて施設整備に対する地域の期待の大きさと、残り二病棟の早期運用の必要性を認識したところであります。
このため、医師、看護師等の確保につきましては、本県が名古屋大学に設置している障害児者医療学寄附講座等の協力を得ながら、必要な職員の確保に努めてまいりました。その結果、病棟の運用開始に必要な医療従事者の確保のめどがついてまいりましたので、平成三十一年一月に予定しておりました重症心身障害者病棟三十四床の開棟時期を十五カ月早め、平成二十九年十月には開棟できるよう準備を進めてまいります。
今後とも、重症心身障害児者の方々が、地域で安心して生活していただける環境づくりを進めてまいります。
次に、新しい愛知県住生活基本計画の策定についてのお尋ねであります。
日本一元気な愛知と豊かさを実感できる県民生活を実現するためには、生活を送る上で欠かせない衣食住の一つである住まいの安定と充実が重要であると考えております。
中でも、発生が危惧されている南海トラフ地震などの大規模災害に備えるとともに、高齢者などが安心して暮らせる住まいを提供するなど、安全・安心に暮らせる住まいの確保が特に重要であります。
また、本来、住まいは数世代にわたって住み続けられる資産です。本県は、耐久性などにすぐれた長期優良住宅の認定戸数が全国一であり、こうした良質な住まいを未来へつないでいくことも重要であります。
さらに、二〇二六年のアジア競技大会やその翌年度のリニア中央新幹線開業を見据え、住まいの面からも愛知の魅力を高め、大都市圏でありながら広い住宅面積、豊かな自然環境など、愛知の強みを生かした住まい・まちづくりを進めていきたいと考えております。
このように、新たな住生活基本計画については、安全・安心に暮らす、住まいを未来につなぐ、愛知の魅力を高めるを三つの柱として今年度中に策定し、日本一元気な愛知づくりに邁進をしてまいります。
続いて、車両を運転中のながらスマホ対策の強化についてであります。
車両を運転しながらスマートフォンを操作するながらスマホは、見ているつもりでも実際には前方の状況を認識していない極めて危険な行為であり、ポケモンGOの操作によるながらスマホの死亡事故の発生によって問題が顕在化したと考えております。
本県では、これまでポケモンGOの配信が始まった直後の七月二十五日から、いち早くこのゲームで遊ぶときの法令やマナー遵守を県民の方々にお願いしてまいりました。
しかしながら、ポケモンGOが原因の交通死亡事故が全国で三件発生し、そのうち二件が本県という極めて深刻な事態を受け、十一月八日にはこのゲームの運営会社に対して車両運転中にアプリが起動しないなどのシステム上の安全対策を要請したところであります。十一月十七日には、一宮市で発生した本県の死亡事故の御遺族に面会をし、亡くなられたお子様の潰れた水筒、ゆがんだ眼鏡を見て、改めてながらスマホの危険性について認識したところであります。
こうした悲惨な交通事故が二度と起きないよう、十一月二十一日に国へ要請書を提出し、十一月二十二日には自由民主党交通安全対策特別委員長の江崎委員長に、さらに、十二月二日にはこの御遺族と一宮市長にも同行していただき、松本国家公安委員長に車両運転中のながらスマホ行為に対する罰則の強化、交通安全教育や広報の拡充等を内容とする対策強化などについて強く要請をいたしました。松本委員長からも法務省関係部署とも早急に協議し、しっかり検討したいと答えていただきました。
今後も、車両を運転中のながらスマホの根絶に向け、引き続き、その危険性についてさまざまな啓発活動等を通じて訴えてまいりたいと考えております。何とぞ県議会におかれましても御理解と御支援のほどよろしくお願いをいたします。
私からの最後の答弁となりますが、愛知・つながりプランについてであります。
まず、知的障害特別支援学校の過大化による教室不足の解消については喫緊の課題と認識しており、平成二十六年度の県立いなざわ特別支援学校、二十七年度の豊橋市立くすのき特別支援学校の開校に続き、議員お示しのとおり、大府市と瀬戸市においてそれぞれ三十年度、三十一年度の開校を目指して新設校の建設工事等を進めております。さらに、安城特別支援学校の過大化解消については、新設校設置に向け、西尾市において用地の取得を進めていただいており、三好特別支援学校についても、豊田市との間で新設校用地に関する調整を進めているところであります。
次に、その他の教育諸条件の整備についてでありますが、冷房設備の設置については、障害のある子供たちの身体的負担を考慮し、全ての普通教室と特別教室への早期設置に向けて、これまでよりもスピードを上げて計画的に取り組んでまいります。
また、肢体不自由特別支援学校の全てのトイレの洋式化を初めとしたトイレ環境の改善についても、早期に進めてまいりたいと考えております。
今後も、愛知・つながりプランに基づき、障害のある子供たちの教育環境の充実についてしっかりと取り組んでまいります。
以上、御答弁申し上げました。
- 5:◯警察本部長(桝田好一君) いわゆるながらスマホ対策の強化ついてお答えいたします。
県警察といたしましては、自動車や自転車など車両運転中の携帯電話の使用等は道路交通法により禁止されておりますことから、従前より交通指導取り締まりやその危険性を訴える広報啓発活動等を実施しているところであります。
特に、議員お示しのゲーム用アプリが配信されましてからは、いわゆるながらスマホに対する社会的関心が高まりましたことから、携帯電話会社と連携したキャンペーンの実施や県内一斉での携帯電話使用等違反の取り締まりなどを実施しております。
本年十月末までに携帯電話使用等に係る交通違反三万六千七百七十九件、また、ポケモンGOに係る交通違反八十六件を検挙しております。また、当該アプリの運営会社に運転中の使用制限を行うなどの要望書を送付いたしたところであります。
今後、スマートフォンの利用方法等はより多様化し、車両運転時におけるいわゆるながらスマホによる違反や事故の増加が懸念されますことから、こうした行為の未然防止に向け、携帯電話使用等の違反の取り締まりを初め、当該行為の危険性の周知と理解に向けた広報啓発活動を関係機関・団体等と連携し、継続的かつ強力に推進してまいりたいと考えております。
- 6:◯教育長(平松直巳君) 県立高校におけるさまざまな学びの場の整備についてお尋ねをいただきました。
まず、不登校生徒や中途退学者など多様な生徒の受け入れについては、本県初の二部制単位制の定時制高校であります城北つばさ高校を来春開校いたします。また、東三河地域のニーズに応えるために御津高校への昼間定時制の併設を検討するほか、県内の地域バランスに配慮しながら全日制単位制高校の設置についても検討してまいります。
次に、生徒の目的意識や学習意欲の向上などの成果を上げている総合学科については、平成三十年度に緑丘商業高校の商業科を総合学科に改編し、三十一年度には新城高校と新城東高校を統合して、新たな総合学科の高校を開設するほか、知立高校の普通科と商業科をあわせて総合学科に改編することを検討いたしております。
さらに、産業界のニーズを踏まえ、小牧工業高校への航空産業科の新設など職業学科の改編を順次進めるとともに、普通科の教育課程に専門科目等を取り入れるコース制についても、平成二十九年度に一宮西高校の国際理解コースを初め五校に設置するほか、今後、長久手高校への医療・看護コースの新設など、さらなる充実を図ってまいります。
教育委員会といたしましては、高等学校将来ビジョン及びその実施計画に基づき、時代や生徒のニーズを踏まえた魅力ある県立高校づくりを着実に推進してまいりたいと考えております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 7:◯四十番(石塚吾歩路君) 暫時休憩されたいという動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
- 8:◯議長(鈴木孝昌君) 石塚吾歩路議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 9:◯議長(鈴木孝昌君) 御異議なしと認め、暫時休憩いたします。
午前十一時十六分休憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後一時開議
- 10:◯議長(鈴木孝昌君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
通告により質問を許可いたします。
河合洋介議員。
〔十九番河合洋介君登壇〕(拍手)
- 11:◯十九番(河合洋介君) 議長のお許しをいただきましたので、私からは、民進党愛知県議員団を代表して、県政各般にわたり、知事及び県当局のお考えをお聞きしたいと思います。
私ども民進党愛知県議員団は、平成二十九年度施策及び当初予算に対する提言を団員三十二名全員参加で取りまとめまして、九月定例議会の最終日でありました、去る十月十四日に知事へ提出をさせていただきました。
その冒頭には、「命」「雇用」「暮らし」を守り、すべての人に居場所のある共生社会を、と掲げ、県民生活向上に向けたきめ細やかな施策の展開に重きを置いた九十を超える項目について要望、提言をさせていただきました。
今、本県愛知県は、さまざまな国際的スポーツ大会や競技大会の開催や誘致でありますとか、県営名古屋空港、中部国際空港の両空港周辺の整備など、大型プロジェクトが進行をいたしております。引き続き、元気な愛知を継続していくためには、これらの大型事業を成功に向け推し進めていくことが重要でありますと同時に、県民生活により直結をした施策を一つ一つ着実に実行、推進していく必要があります。そういった思いを踏まえまして、順次質問を始めさせていただきたいと思います。
初めに、大規模展示場の運営について質問をさせていただきます。
常滑市にあります中部国際空港、空港島内に整備予定の大規模展示場につきましては、当初、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催によって、その開催期間や準備期間で首都圏の展示場が利用できなくなる、その機会を愛知、名古屋で受け皿となるんだと、そういったことで提案がされ、構想が練られてまいりました。ですので、大村知事は、二〇一九年秋に開業できるように整備をすると、まずスケジュールありきで御提案をされ、時期的にクリアできないようであればプロジェクト自体も白紙にするとおっしゃっておりました。
この十月に整備事業者が決定をし、今議会には実施計画、施行工事請負契約の議案も提出をされ、順調にいけば、来年、二〇一七年の半ばには工事が開始をされ、完成も二〇一九年秋には開業ができるとお聞きをいたしており、当初の開業スケジュールはクリアできそうであると、まずは一安心をしたところであります。
また、このプロジェクトは、整備と運営について、約三百五十億円という大きな整備費のかかる事業でもあります。
建設、土木業界では、まさにオリンピック景気に沸き、本県でも一時期は公共事業の入札不調が続いたり、入札価格の見直しが続いていたこともあったりしましたし、業界の人件費や資材価格は高騰している現状でありますので、事業費用が当初の予定を大幅に上回るような事態にならないかと心配をする県民の皆様も多かろうと思います。
展示場の整備は、設計・施工一括発注方式により行われておりますので、工事費の増加がなるべく生じないよう、設計の取りまとめに際し十分その旨を確認していくことが重要であると考えております。
整備について、何点か述べさせていただきましたが、施設の完成、そして、また開業後の運営についても若干心配をいたしております。今が二〇一六年のもう年末でございますので、二〇一九年秋の開業まで時間があるようで、ありません。施設の整備はもちろんですが、その後のコンテンツ、利用見込みに関しても、ある程度早期に見通しが図れてこられないといけないと思います。箱をつくったはいいが、その後の採算がとれないなどというケースは避けないといけません。
そんな中、さきの御答弁、質問の中でもありましたが、ワールドロボットサミットが二〇二〇年、この本県愛知県で開催が決定をされて、そのメーン会場に大規模展示場が利用されるということで、大変明るいニュースであると思いますし、大いに期待をさせていただきたいと思っております。
本年三月に策定をされました愛知県大規模展示場基本構想の中にあります収支シミュレーションによりますれば、展示場の維持管理費には多額の費用がかかることが想定をされておりまして、その稼働率が一〇%の場合ですと、売り上げに五億七千二百万円、費用に十三億二千八百万円ということで、年間七億五千六百万円の赤字になると示されております。稼働率三〇%でようやく売り上げ、費用がともに約十七億円となり、採算がとれる計算をいたしております。その収支を均衡させるためには、四万平米規模の展示会を少なくとも月に一回、年に十二回開催をして、ようやく収支が合うということになっておりました。
今議会で提出をされております愛知県国際展示場条例の説明の中では、稼働率二五%で損益分岐という数字も示されておりましたが、いずれにしても、決して簡単なハードルではないように感じます。
今後、運営事業者選定に当たり、コンセッション方式が採用されるとお聞きをいたしておりますが、展示場の収支につきましてはどのような見込みであるのでしょうか。
加えて、いよいよ料金設定も決まってまいりまして、プロモーションもこれから本格化してくると思います。本年度から振興部地域政策課内に大規模展示場準備室を設置し、特化をしてさまざまな活動を行っていたり、知事プロモーションを行ったり、全庁を挙げて利用促進プロジェクトチームを設置したりしているともお聞きをいたしております。
しかし、重ねてになりますが、二〇一九年秋開業に当たって時間がありません。今後のプロモーションをより積極的に進めていくことが非常に重要になってくると思います。
そこでお伺いをさせていただきますが、大規模展示場の収支見込み、そして、また今後のプロモーションについて、知事のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
続きまして、有料道路コンセッション事業について質問をさせていただきます。
御案内のとおり、愛知県内の知多半島道路を初めとする有料道路八路線が、国の特区制度を活用し、さきの十月一日、全国で初めて民営化がされました。
運営権譲渡の当日、その式典の場におきまして、山本幸三地方創生担当大臣は、道路は公が管理をするという原則を打ち破る画期的な事業であり、全国に先駆けた愛知方式として広げていくことが地方創生につながると御挨拶をされておりました。
いよいよ運営が開始をされました愛知道路コンセッション株式会社でございます。民間活力を取り入れてインフラを効率的に運営していくことのみならず、さまざまなアイデアのもと、その地域に新たな活力を生み出していくことに私どもも大いに期待をいたしております。
今回、新会社が実施をするさまざまな道路事業以外にも、任意事業として提案をされたさまざまなアイデアには、地元の自治体、地元住民、関係団体の皆様とともに、私も知多半島の住民の一人として、大いに期待をしているところであります。
公表されております民間事業者からの任意事業の提案内容を見ますと、新設の阿久比パーキングエリアに連結をする食と安らぎのリゾート施設などの食の拠点事業、これは愛知多の大地というふうに言われておりますが、そして、セントレアの空港島にはインターナショナルブランドホテルの誘致、そして、酪農が盛んな知多半島地域で牛ふん等を用いたバイオガス発電施設の整備などが任意事業として提案をされております。
しかしながら、これらの任意事業の施設を整備していくに当たっては、さまざまな法規制をクリアしていく必要がございます。一例としまして、阿久比パーキングエリア周辺で想定をされている事業をとりましても、当該の地域周辺は広大な農業振興地域でありまして、土地利用の変更が必要となってきますし、既存の都市計画道路との兼ね合いから見ても、今後新設が予定される施設への取りつけ道路はどうするかなどなど、数え上げれば切りがありません。これは、およそ新会社が単独で解決できることではありませんので、しっかりと愛知県が、建設部門だけでなく、農水部門、はたまた国の国土交通省、農林水産省ともしっかりと連携、調整をしていかなければ実現できる事業ではありません。
そこでお伺いをさせていただきます。
今回提案のありました任意事業に対しまして、建設部門、農水部門、国、地方自治体、特定目的会社との調整について、県としてどのように取り組んでいかれるのか、御所見をお伺いしたいと思います。
もう一つ、お伺いをさせていただきます。
今回、このコンセッション事業は三十年という長い期間にわたっての事業であります。今後三十年間継続して、有料道路を適正に管理していけるのかといった懸念もあります。
例えば、災害時の対応であります。三十年の間に大規模地震などの非常に大きな災害が発生をした際に、迅速に交通規制や道路被害の復旧ができるのかといったところであります。
さらには、社会情勢の変化もございます。さまざまな社会情勢の変化の中で、民間事業者が当初想定をしていた交通量を大幅に下回るですとか、今後整備が予定をされております西知多道路の影響もありますし、収入の面が大きく下振れをしてきた際など、民間事業者が多額の負債を抱え込んでしまうなどということも起こらないとは言い切れません。
そこでお伺いをさせていただきます。
事業計画が、社会情勢の変化などにより、予想していたものより大幅に変更があった際など、県として有料道路の管理運営を行う特定目的会社と今後どのようにかかわっていかれるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
続きまして、あいちトリエンナーレについて質問をさせていただきます。
ことし、第三回目になります、あいちトリエンナーレ二〇一六が、八月十一日から十月二十三日まで開催をされておりました。三年に一度の現代アートの祭典なわけでございますが、今回で第三回、三回という区切りに当たりまして、今後の展開をどのようにお考えであるのか、伺っていきたいと思います。
過去二回の開催報告書によりまして、さまざまな御意見が寄せられておりました。私も地元で、県民、市民の皆様からさまざまな御意見をいただきました。
そのアンケートや御意見によりますれば、愛知が文化創造に貢献をするイベントとして長く続けてほしいですとか、文化や教育の投資効果は数十年から数世紀先のためのものでありますから超長期的政策として継続をしていただきたいといった御意見から、通常時に活動をしている公共施設がトリエンナーレの期間に借りることができなくなり大変困っている、愛知在住のアーティストたちへの視点が欠けている、愛知出身のすぐれたアーティストがたくさんいるので、彼らを起用してあげてほしいですとか、一部の人たちや一部の地域だけが盛り上がっているような印象を受ける、愛知県として開催をする必要があるのか、などなど、非常に好意的な御意見から継続を疑問視するような声までさまざまであります。このような意見を参考に、今回改善をされた点、生かされた点もあろうとも思います。
正直申し上げまして、私も現代アートの芸術祭を評価できる立場にないといいましょうか、それがよきものかどうか、本質的な美術、芸術の目をもって何かしらを申し述べることは残念ながらできません。しかしながら、県民の目線に立ちまして、このような事業を三回行ってみて、今後も多額の税金を投入して続けていくべきなのかどうか考えることはできますし、そうした検証は非常に重要なことであろうと思います。
一体誰のためのトリエンナーレなのか、県民にとってあいちトリエンナーレの開催は本当に必要な施策であるのか、三回のトリエンナーレによって見えてきたものがあるのかもしれません。
そこでお伺いをさせていただきます。
過去三回のあいちトリエンナーレの成果について、県としてどのように捉えていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。また、第四回以降の開催に向けての継続性も含め、知事の思いをお聞かせいただきたいと思います。
続きまして、住宅の耐震化についてお聞きをしたいと思います。
熊本地震から間もなく八カ月が経過をいたします。観測史上において震度七が初めて連発をしたこと、一連の地震で震度六弱以上の地震が七回発生をしたこと、本震と思われた揺れの後にもう一度大きな揺れ、これを本震と表現するのが正しいかもしれませんが、本震、余震という従来の考えが通用をせず、再び想定外という言葉が使われる大きな災害でありました。
本県も、近い将来必ず訪れると言われている大規模地震に向けての対策を、阪神・淡路、中越沖、東日本大震災などの過去の災害の被害状況、復興状況を踏まえ取り組んでまいりましたが、この熊本地震によってもたらされた教訓もその対策に加え、取り組みをより効果的なものへと改良されていると思います。
本県は、愛知県地震対策会議、愛知県防災対策有識者懇談会などにより、この熊本地震にかかわる課題を検証し、その対応について愛知県地域防災計画を初めとする防災にかかわる計画やマニュアル等の見直しを行い、地震防災対策の強化を図るとされております。
九月議会において、我が会派のかじ山幹事長からの代表質問で、熊本地震を教訓とした自助、共助の必要性について質問をいたしました。そのほかにも、一般質問あるいは委員会の場で多くの議員からこの熊本地震の教訓について取り上げられておりますが、今回、私は住宅の耐震化について触れさせていただきたいと思っております。
熊本地震の被害において、直接死者の七割強が住宅の倒壊により命を落とされました。新耐震基準の住宅も一部倒壊をしたとの情報もありまして、その点につきましては、今後の分析を見守る状況にあるとは思いますが、やはり住宅の耐震化率を上げることが直接的に被害を抑える大変効果的な方策であるということを再認識いたしました。
愛知県は、熊本地震以前から二〇二〇年度に住宅耐震化率九五%を目指して、住宅の耐震診断及び耐震改修について積極的に取り組んでいますが、平成二十七年度決算を拝見させていただきますと、住宅の耐震改修等の予算が十分に活用をされていないということもうかがうことができます。
こういった地震がありますと、自然と県民の皆様からの問い合わせがふえるということはもちろんありますけれども、熊本地震、今回の教訓を生かして、今後、より一層住宅の耐震化については加速をさせていってほしいと思います。
そこでお伺いをさせていただきます。
住宅の耐震化について、今後県はどのように取り組んでいかれるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
続きまして、児童相談所の体制強化についてお聞きをしたいと思います。
本年八月に公表をされた厚生労働省の集計によりますと、全国の児童相談所が平成二十七年度に対応した児童虐待の数は、一九九〇年度の調査開始以来二十五年連続で増加の一途をたどっており、初めて十万件を超え、十万三千二百六十件となりました。
愛知県におきましても、県内の十カ所の児童相談センターにおける対応件数は、二十七年度三千七百二十六件と、こちらも過去最高を更新し続けております。
また、県の資料によりますと、虐待を理由とした一時保護件数に関しましても、平成二十七年度八百七十七件で、こちらも増加をしているとお聞きをしております。
児童虐待の相談件数や一時保護の件数が年々増加をしているということで、その現場の児童相談所の業務量も増加をしており、対応に当たる人手不足も深刻化をしてきているということもお聞きをいたしております。相談内容に関しても、時代の流れもあり、多様化をしておりますし、もちろん内容によっては命にかかわる、一刻を争うケースもありますので、児童相談所の体制強化は早急に実現させなければいけない案件であるということは言うまでもありません。
そうした中、国においては、本年四月に児童相談所強化プランを作成し、六月には改正児童福祉法が公布をされ、児童相談所や市町村への専門職員の配置等の体制強化、虐待の発生予防をさらに推進していくという方針を打ち出しました。
本県では、昨年三月に策定をしましたあいち・はぐみんプラン二〇一五─二〇一九の中で、児童虐待防止基本計画を盛り込み、市町村や関係団体との連携強化などを含む児童相談センターの体制強化をうたっており、さまざまな施策を講じてきていることと思います。
一時保護につきましても、昨年、県内で三河地区に一カ所でありました一時保護所を、尾張地域にも一カ所ふやして現在二カ所であるというふうにお聞きもいたしております。
そこでお伺いをさせていただきます。
愛知県として国の法改正を新たな契機として、今後とも児童虐待防止についてより推進をしていく必要があると考えますが、県として、児童の一時保護の体制も含め、児童相談所の体制強化をどのように図っていくのか、考えをお聞かせいただきたいと思います。
続きまして、本県農業のさまざまな経済連携協定への対応についてお伺いをしたいと思います。
世界のGDPの約四割というかつてないほどの規模の経済圏をカバーするTPP、環太平洋経済協力協定につきましては、現在開かれております臨時国会の場において、国会承認を求める議案とその関連法案が成立する見込みとなっております。しかしながら、御案内のとおり、次期アメリカ大統領であるトランプ氏は、TPPに対しまして来年一月の大統領就任初日に離脱を通告すると表明をしております、などなど、TPP発効についての見通しは絶望的であるとの見方が大勢でもあります。
その一方で、アメリカ抜きで発効を目指そうとする動きや、TPPでの合意レベルに合わせて、EUとの経済連携協定やASEAN十カ国と日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドが参加をいたします東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の交渉を加速化する等の報道も出てきております。
こうしたことも踏まえ、いずれにしても、アメリカの動向に関しては注視をしていくことが重要であることには間違いありませんが、TPPであろうがなかろうが、諸外国との経済連携協定によって影響を受けると予想される本県の農業に対してしっかりと対策を講じていくことの重要性は変わりませんので、それについて質問をさせていただきたいと思います。
基本的には、経済連携協定や自由貿易協定でございますので、広い範囲での関税の撤廃が求められます。こういった関税の撤廃による影響で、外国産の農林水産物の輸入の増加が予想され、国内産の農産品を生産、流通する現場では不安の声が広がると、こういう流れは当たり前であります。
国は、昨年末にTPP関連政策大綱を作成し、攻めの農林水産業へ転換をする体質強化といった対策等を講じていく方針を示し、昨年度の補正予算及び本年度の予算でも、主に本県でも大変大きな影響が予想をされる畜産や酪農の収益力強化や国際競争力のある産地の生産力強化などの対策を講じてきております。
大村知事も、従来から、TPPの発効が国内有数の農業生産県である本県の農産品へのマイナスの影響が生じないように、知事みずからが本部長となり、TPP対策本部を立ち上げ、対応について取りまとめられたとも伺っております。実際に、国の方針を受け、愛知県としても本年度さまざまな施策を講じ、成果を上げ、来年度以降へと結びつけていく方向性であると思います。TPPの発効がどのようになろうが、これまでの取り組みが無駄になるとは思いません。
そこでお伺いをさせていただきます。
こうした経済連携協定によりまして影響を受けることが予想をされる本県農業について、実際に取り組んでいる対策の内容及びその成果、加えて、今後の取り組みについてお聞かせをいただきたいと思います。
続きまして、交通事故対策について県当局並びに県警本部にお尋ねをしたいと思います。
年末が近づいてまいりまして、車の運転にはより気を使わなければならない季節になりました。
本県春日井市と一宮市におけますスマートフォンゲーム利用中の運転手によるながら運転での死亡事故を初めとする全国各地でさまざまな痛ましい交通事故のニュースが本年も伝えられました。なくならない痛ましい悲惨な事故に対しまして、深い悲しみと怒りを禁じ得ませんが、少しでも交通事故を減らし、悲しいニュースがなくなるよう期待をし、さまざまな施策についてお伺いをしていきたいと思います。
まずは、道路管理者としてハード対策をお聞きいたします。
国道や県道など、幹線道路の事故危険箇所の対策についてお伺いをいたします。
本県の交通事故の発生状況は、平成十五年以降、十三年連続で交通事故死者数全国ワーストを記録しており、本年も既に年末になっておりますが、昨日、十二月四日現在で百九十三名の方がお亡くなりになられ、依然として全国ワーストを記録しており、極めて厳しい状況が続いております。
また、交通事故の発生状況に目を移しますと、死亡事故の過半数は、国道や県道などの幹線道路で発生をいたしております。道路の総延長の一割、一〇%にすぎない、そうした幹線道路で死亡事故の半分が発生をしているということになります。また、なおかつ、交差点での交通事故が発生する割合は、その他の区間の約三倍に達するなど、特定の区間に集中して死亡事故は発生をいたしております。
そのため、交通事故を減らしていくためには、幹線道路の事故発生状況を分析し、特に交通事故が多発をしている箇所を抽出して、集中的に対策を講じていくことが重要であります。
全国的にも、国土交通省と警察庁とが連携をし、社会資本整備重点計画において事故危険箇所を指定し、交通事故の三割削減を目標として計画期間内に交差点改良などの対策を実施することといたしております。
現在本県で進められている計画は、平成二十五年七月に本県の管理をする道路のうち百三十カ所を事故危険箇所と指定して、本年度末までに対策を完了する予定で取り組みを進めております。その百三十カ所の対策を目標どおり早急に取り組んでいってほしいのは言うまでもありません。しかしながら、時代の流れによりまして、新たな道路の整備、沿道の開発などにより、事故危険箇所というのは新たに生じてくるものでもあります。ですので、現在進めています百三十カ所の対策が終わればそれで全てが終了ということにはなりません。
昨年度、国が平成三十二年度を計画期間として策定をした第四次社会資本整備重点計画におきましても、幹線道路における事故危険箇所対策の継続実施が決定をされております。
このため、本県といたしましても、いま一度、幹線道路における交通事故の発生状況をしっかりと分析し、対策を継続していくことが不可欠であります。
そこでお伺いをいたします。
本年度、最終年度を迎えました事故危険箇所対策の進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。加えて、平成三十二年度を目標とする新たな第四次社会資本整備重点計画におけます事故危険箇所対策に、今後県としてどのように取り組んでいくのか、お聞かせをいただきたいと思います。
次に、高齢運転者への対応について県警本部にお伺いをいたしたいと思います。
十月末に、神奈川県横浜市内で高齢の男性が運転をする軽自動車が前方の車両に追突、横転をし、通学中の小学校一年生男児がその下敷きとなり死亡をするという大変痛ましい事故が起こりました。
再び繰り返されました通学中の児童生徒が犠牲になった事故であるということに加えまして、加害者である男性が八十七歳という高年齢で、なおかつ認知症の疑いもあるということでございました。その高齢男性が自動車運転過失致死傷の罪で逮捕をされる姿には、何とも言えない悲しい気持ちにさせられたところであります。
高齢化社会が進む中で、高齢ドライバーの数は当面ふえ続けます。現状、七十歳以上のドライバーの皆さんには、免許更新の際に、高齢者講習を受けることが義務づけられ、また、七十五歳以上のドライバーの皆さんには、認知機能検査も行われているとお聞きをいたしております。また、免許証の自主返納制度を案内し、活用をしてもらうように促すこともあるということもお聞きをいたしております。
国においては、高齢者が第一当事者となる交通事故の増加の現状に鑑み、来年三月十二日には改正道路交通法が施行され、この法改正によりまして、七十五歳以上のドライバーの免許更新時の認知機能検査で認知症の疑いがあると判定をされた方には、一定の交通違反がなくても臨時適性検査を受ける、あるいは医師の診断を受け、その結果により免許取り消しや停止処分となる可能性が生じるようになります。
さらに、免許更新時でなくても、一時停止違反や一方通行の逆走など、一定の違反を行った際には、新たに臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けることが義務づけられるなど、より厳しい対応となるとお伺いをいたしております。
もちろん、高齢化社会の中で、高齢者の皆様から正しく安全な移動の手段である車の運転を奪うということを目的に行うわけでは全くありません。さきに起こったような高齢ドライバーによって引き起こされる悲惨な交通事故を抑止するということが本来の目的であるということをしっかりと念頭に置かなければなりません。
そこでお伺いをさせていただきますが、愛知県警察本部としてどのように高齢運転者対策を推進していくのか、お伺いをしたいと思います。
次に、教員の多忙化解消について教育長にお伺いをさせていただきます。
教員の多忙化が叫ばれ続けております。文部科学省の教員勤務実態調査によりますれば、過去四十年間で教員の残業時間は大幅に増加をしており、授業以外での生徒指導や学校経営にかかわる事務的な業務、授業準備や成績処理、保護者への対応、部活動の指導など、多様化をする教育現場への課題と相まって、ありとあらゆる場面で教員の皆さんの負担はふえ続けております。
私ども民進党愛知県議員団は、かねてより、子供たちの健やかな成長のためには、教育現場におけるきめ細やかな対応が必要であり、そのためには、とりわけ学校の先生、教員の皆さんが、子供たち一人一人に向き合うために十分に時間を充てることのできる、豊かな時間が必要である旨を訴え続けてまいりました。
県は、あいちの教育ビジョン二〇二〇、第三次愛知県教育振興基本計画に教員の多忙化解消に向けた取り組みの推進としっかりと位置づけられ、教員の多忙化解消プロジェクトチームを設置、より詳細な実態の把握と多忙化解消に向けての具体的な取り組みをまさに検討されておりました。
そして、本年度、教員の多忙化解消プロジェクトチームは、六月に第一回検討会議を行い、今までに七回、在校時間の実態把握のあり方についてや学校マネジメントのあり方について、部活動指導のあり方について等が具体的に検討をされ、直近では十一月二十九日に教員の多忙化解消に向けての提言について取りまとめをされたとお聞きをいたしております。
その中での勤務実態調査、在校時間実態調査によりますれば、月に八十時間を超える、いわゆる残業を行っていらっしゃる学校の先生が、小学校では一〇・八%、高等学校では約一四%、そして、中学校では最も多く三八・七%の割合で存在をいたしており、さらに、月に百時間を超えて在校している先生が中学校で二〇・七%もいるという実態がデータで示されました。かねてより多忙化という認識を持ってはおりましたが、多忙をきわめる教員の皆さんの実態に、改めて多忙化解消の必要性を感じたところでもあります。
そこでお伺いをさせていただきます。
今回取りまとめた教員の多忙化解消に向けた提言を、教育長としてどのように捉えていらっしゃいますか。また、この提言を受けて、子供たちに真摯に向き合う教員の皆さんの多忙化解消に向け、具体的にどのように生かしていくのか、今後どのように取り組んでいくのか、お聞かせをいただきたいと思います。
私からは、最後に、骨髄バンク事業と骨髄バンクドナー支援事業についてお伺いをさせていただきたいと思います。
骨髄バンク事業とは、白血病や再生不良性貧血等の治療法としての造血幹細胞移植、いわゆる骨髄移植や末梢血幹細胞移植を実施するに当たって整備をされた制度でございます。患者さんと骨髄提供者、いわゆるドナーと呼ばれますが、患者さんとドナーとの白血球の型を一致させることが必要でありますので、その骨髄バンクの登録者の数をふやしていこうという動きは今に始まったことではございません。
骨髄バンク制度が始まってことしで二十五年ということであります。着実にその登録者数はふえ、さらに、骨髄移植に至る数も年々ふえているとお聞きをいたしております。本年十月には、移植が二万例を超えたと公益財団法人日本骨髄バンクからの発表もございました。本年十月時点での全国の骨髄バンクドナー登録者数は四十六万七千百人、愛知県内では一万九千五百五十四人ということでありまして、愛知県内の登録者数は全国で七番目ということで上位に位置をしておりますが、ここ五年余りはほぼ同数で推移をしております。全国的には増加傾向にありますが、今後を考えると楽観視できません。
なぜ楽観視ができないかと申し上げますと、登録者の平均年齢が上がっているということが挙げられます。骨髄バンクドナー登録は十八歳から五十四歳までで健康な方が対象であります。実際の骨髄移植は二十からなんですが、ドナー登録自体は十八歳からなわけであります。ですので、五十五歳を超えた方は登録者の数からカウントされなくなります。事実、現在四十代の登録者の割合が最も高く、このままでいきますと十年、二十年先には全体として減少をしていくということがわかっております。今後も登録者数を維持、増加させていくには、若い世代を中心に継続をして啓発活動を行っていかなければいけません。
そこで、まずお伺いをさせていただきます。
骨髄バンク事業について、今後どのように周知、啓発を続け、骨髄バンクドナー登録者数を確保していくのか、県としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
もう一つ、ドナーへの支援についてお伺いをしたいと思います。
先ほどから御紹介をさせていただいておりますとおり、現状全国で約四十七万人の骨髄バンクのドナー登録者がいて、提供を希望する患者さんが年間約二千人以上いらっしゃいます。実は、その患者さん、二千人以上の患者さんのほとんどの方に骨髄移植可能な、要するに、白血球の型が一致をしているドナーの候補者が一人以上存在をしております。約九五%という数字も出ておりますが、白血球の型が一致をいたしております。
しかしながら、それが骨髄移植、提供に至っていない現状というものもあります。さまざまな原因はございますが、その理由の一つに、ドナーの経済的な問題が挙げられます。ドナーは、その入院費用と直接の交通費こそ自己負担はないものの、四日間から六日間ほどの入院期間が必要でありまして、ドナーには経済活動の停止期間ができてしまいます。患者さんと同じ地域に住んでいるケースだけではありませんので、移動時間についても大きな負担となります。
また、ドナーの皆さんは二十から五十四歳の方ですので、現状休暇制度等が十分に整備をされていない状況でありますので、その勤務先からの理解が得られないことには、どだい無理な話となってしまいます。
せっかく白血球の型が一致をし、移植可能なケースがあったとしても、ドナーが骨髄提供を断念せざるを得ない理由に経済的な問題が少なからずあっては、移植を希望する患者にとっても、その御家族にとっても大変残酷な話でございます。
全国的にドナーに対しての休暇制度や経済的負担の解消を図るような助成制度の創出を国へと求めていくことも大変重要であろうかと思います。しかしながら、実際に自治体レベルで率先して環境整備を行っている事例もあります。
本年十一月十五日現在で、全国百九十一の市町村が独自にドナーに対する助成制度を設けております。愛知県でも、犬山市が平成二十六年度から、そして東浦町が平成二十八年度から、この二つの市町でドナーに対し、最大七日間を上限といたしまして一日当たり二万円の助成を行うという制度が設けられております。
また、都道府県レベルでも、埼玉県、京都府を初め、八都府県でドナー支援助成制度があり、市町村負担の二分の一を都府県で負担いたしております。埼玉県に至っては、県内六十三の市町村全てで助成制度があります。京都府もそのほとんどの市町村で助成制度が設けられております。
そこでお伺いをしたいと思います。
骨髄ドナーに対する経済的なバックアップ体制について、県としてどのように捉えて取り組んでいくか、お聞かせをいただきたいと思います。
ここで、触れさせていただきたい事柄がございます。
去る十一月三日に、お隣、名古屋市議会の議員であります日比健太郎さんが急性混合性白血病で三十五歳という若さでお亡くなりになられました。彼は本年五月に白血病の診断を受けられ、壮絶な闘病生活を送る中で、一般的に、とかく病気を隠したがる政治家が多い中、みずからその病気を告白し、そこで得た多くの気づきを世に問うていきたいと生前語っておりました。
骨髄バンクドナー登録者の高年齢化に危機感を感じ、ドナーと患者さんとが白血球の型の一致に至りながら、骨髄移植に至ることのできないミスマッチの状況、あるいはドナーへの支援体制についても我々仲間にたくさん問題提起を投げかけてくれました。事実、彼の白血球の型に適合する方は全国に四名おいでになりましたが、実際、骨髄移植に至りませんでした。私も、そして私の仲間も、彼の死に対して返す返すも無念で、残念でなりませんが、彼が命を賭してまで投げかけたそのことを我々はしっかりと引き継いでいかなければいけないと思っております。
現在、民進党本部では、骨髄ドナー登録推進プランを通称日比プランとして策定をし、若年層のドナー登録者をふやしていくような普及啓発や患者とドナーとのミスマッチの解消、ドナーや患者家族に対する助成制度の創出を目指し、超党派に呼びかけをさせていただき、また、全国の多くの仲間にアプローチをさせていただいております。
このような動きも申し添えつつ、骨髄バンク事業とドナー支援事業について、本県としてもぜひとも積極的に取り組んでいただきたいと強く要望をさせていただきたいと思っております。
以上、県政各般にわたります重要施策につきまして質問をさせていただきました。知事及び理事者各位の誠実なる御答弁をお願い申し上げまして、私から民進党愛知県議員団を代表しての質問を終わらせていただきたいと思います。御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔知事大村秀章君登壇〕
- 12:◯知事(大村秀章君) 民進党愛知県議員団の河合洋介政策調査会長の質問にお答えをいたします。
初めに、大規模展示場の運営についてお答えをいたします。
本県展示場は愛知の産業力を高めるためのインフラであることから、低廉な利用料金で収支のバランスをとりながら、幅広く御利用いただくことが必要な施設であると考えております。
そのため、料金につきましては、首都圏、大阪の展示場の料金よりも安く、かつ、稼働率が大阪並みの二五%であっても収支均衡できる水準に設定をいたしました。まずは、この稼働率二五%を念頭に、収支均衡を目指してまいります。
今後、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックにより、首都圏の展示場が利用できない展示会も明らかになる予定でありますので、本県展示場の低廉な料金や使い勝手のよさなどをアピールしながら、プロモーションを本格化させてまいります。とりわけ、自動車、航空宇宙、ロボットなど本県が強みを持つ物づくりの分野の展示会や、空港のアクセス性のよさを生かして国内外から出展者、参加者が見込める展示会をターゲットにするなど、戦略性を持った営業活動を進めてまいります。
開業後は、本県展示場の使い勝手のよさを実感していただいて、その後の継続的な開催につなげていく、あるいは、新しい展示会の開催を展示会主催者等に働きかけ、交流、ビジネスマッチングの機会をふやすことが重要と考えております。こうした取り組みを積み重ねることにより、愛知の産業力の強化とともに、我が国全体の産業、経済の発展にも寄与していきたいと考えております。
また、そうした中で、河合議員も触れられましたが、先週二日の金曜日、二〇二〇年に日本が初めて開催するロボット国際大会、ワールドロボットサミットの開催地を、この愛知県国際展示場とすることが決定をされました。
ワールドロボットサミットは、ロボットの研究開発や普及を加速させるために、さまざまなロボットの競技と展示を行う国際大会で、二〇二〇年十月上旬の一週間程度の開催ということであります。
本県は、この空港島に整備する大規模展示場を会場とし、私どもが取り組んでおりますあいちロボット産業クラスター推進協議会のネットワークを最大限に生かし、地域の企業、大学などが一丸となってこの大会の運営に協力することを提案いたしました。我々の提案を高く評価していただいて、愛知県での開催を決定していただいたことに感謝をいたしたいと思います。
今回の決定を受けて、経済産業省や関係機関と連携しながら本大会の成功、そして、この大会を契機とし、ロボット技術の向上、国内外の企業や大学との交流、ロボットの利用促進を図り、本県及び日本のロボット産業の国際競争力の強化につなげてまいります。
そして、二〇二〇年は、東京オリンピック・パラリンピックで世界中から日本が注目をされます。この大会に続いて、ロボットのオリンピックともいうべき第一回のワールドロボットサミットという夢のある国家プロジェクトを愛知で開催できることは大変光栄なことでありまして、私の思いとしては、ぜひ二〇二〇年はオリンピック・パラリンピック、そして、このロボットのオリンピックであるワールドロボットサミットの三本柱で大いに盛り上げていきたいと考えております。
これも、その前年、二〇一九年までに国際展示場を整備するということの効果と言っていいと思います。これを弾みとして、議員も御指摘のように、さらにプロモーションを活発化させて、愛知県国際展示場が、この愛知、そして日本の活性化につなげていけるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
次に、有料道路コンセッション事業についてお尋ねをいただきました。
まず、任意事業に対する調整についてお答えをいたします。
有料道路のコンセッションは、全国初の試みとして、民間の創意工夫による低廉で良質な利用者サービスの提供と沿線開発を含む地域の活性化を目指すものであります。八月三十一日に道路公社と有料道路の管理運営を行う特定目的会社である愛知道路コンセッション株式会社との間で、運営に係る実施契約を締結し、一カ月の準備期間を経て、十月一日から事業が開始されております。
事業開始と同時に通行料金の割引を実施するなど、利用者サービスの向上を図るとともに、現在まで順調に特定目的会社による管理運営が行われております。
また、有料道路の利用促進と地域活性化の相乗効果を狙う有料道路コンセッションにおいては、道路の区域外における任意事業の実現も大変重要であると考えております。これは議員御指摘のとおりでございます。
このため、道路区域外の任意事業につきましては、民間事業者からの提案の実現に向けまして、道路公社は特定目的会社の構成企業との間で事業実施に向けた協定を締結しておりまして、この協定に基づいて、県と道路公社が進捗状況を定期的に確認していくことといたしております。
さらに、任意事業の実施に当たっては、さまざまな法規制が関係するのは議員も御指摘のとおりでありますので、県庁内の関係部局で連携を図り、地元の自治体や国の関係機関などとの調整が円滑に進むように、県としてもしっかりと支援をしていきたいと考えております。
続いて、事業計画が大幅に変更があった場合の特定目的会社との今後のかかわりについてであります。
特定目的会社による長期にわたる道路施設の管理運営につきましては、コンセッションの運営に係る実施契約において、これまで道路公社が実施してきた日常及び災害発生時の管理の水準を要求水準として定め、この特定目的会社、SPCがこの水準を遵守することを義務づけております。
また、西知多道路など競合路線の供用に伴う料金収入の減少につきましては、あらかじめ計画に見込んでおりまして、今後の社会情勢の変化などやむを得ない事情により、料金収入が計画に対し一定の率を超えて減少した場合には、道路公社がその一定の率を超える減少分を運営権対価の中から特定目的会社に負担する契約といたしております。
さらに、大きな収入減が続くような場合は、計画料金収入自体を見直すことも契約に定めておりまして、特定目的会社に起因しない収入減のリスクを軽減するようにいたしております。そういうふうな制度設計にしているということでございます。
その上で、道路公社と特定目的会社が設置した管理運営に係る協議会に県も参画をし、管理運営状況や財務状況を定期的に報告させ、必要に応じて指導や是正指示を行うことといたしております。
このように、県と道路公社が一体となって、特定目的会社が安定して適正な管理運営を継続できるようにしっかりと取り組んでまいります。
次に、あいちトリエンナーレの成果と今後についてであります。
今回のトリエンナーレは、前回に引き続き六十万人を超える方々に御来場いただいて、名古屋、豊橋、岡崎の三都市で開催したことで、県内の幅広い地域で現代アートに親しんでいただけたものと考えております。
私も何度か会場に足を運びましたが、大巻伸嗣さんの県美術館の一室を花や鳥の文様で埋め尽くした作品や岡崎公園で展示されたイギリスのアーティストグループのドームの中からカラフルな色彩を楽しむ作品などが大変見応えがあって印象に残ったところでございます。
また、どの会場でもお子様から御年配の方まで幅広い年齢層の方々が楽しみながら作品に見入り、現代アートをより身近に感じていただける姿を拝見いたしました。トリエンナーレはこれまで三回継続して開催することで多くの方々にお越しをいただき、運営にボランティアが携わることも定着してきており、回を重ねてきたことで、この現代アートの祭典が愛知に着実に根づきつつあると実感をいたしております。
あいちトリエンナーレは、この地域の文化芸術を活発化させ、経済面のみならず、文化面でも世界に貢献する魅力的な愛知をつくるために始めた事業でありまして、今後も継続することで本県から新しい文化芸術を発信し、国内外から人を引きつける魅力的な地域づくりを目指してまいります。
今後は、来場者アンケートの分析や専門家からの意見聴取による評価等をもとに事業をしっかりと検証し、さらににぎわいがあり、発信力のある事業に進化させることにより、この地域の存在感を高める事業として育ててまいりたいと考えております。
続いて、住宅の耐震診断と改修についてお答えをいたします。
南海トラフ地震が想定、危惧をされる中、住宅の耐震化の促進は喫緊の課題でありまして、第三次あいち地震対策アクションプランにおいても、特に重要なアクション項目の一つとしております。
本県では、平成十四年度から木造住宅の無料耐震診断を、平成十五年度からは耐震改修費補助を始めており、耐震診断につきましては全国第一位、耐震改修につきましては全国第二位の実施件数となるなど、県民の皆様の安心・安全の確保に積極的に取り組んでまいりました。
また、県内三つの国立大学法人や建築関係団体と連携して、安価な耐震改修工法の開発、普及や地域に専門家を派遣する地域ぐるみ耐震化支援事業を実施するなど、耐震改修等に係る費用負担の軽減や周知啓発にも力を入れてまいりました。
今年度は熊本地震の影響もあると考えられますが、耐震診断、耐震改修ともに昨年度より申し込みがふえております。県民の方々の耐震化への意識が高まっていると感じられますので、補助制度の周知などを今後ともしっかりと行ってまいります。
さらに、本県では、住宅の倒壊から命を守るための取り組みとして、寝室などに安全な空間を確保する耐震シェルター整備費補助や、倒壊しにくいレベルまで耐震補強をする段階的耐震改修費補助を実施しているところでございます。
熊本地震の教訓を踏まえて、これまで進めてきた施策に加え、命を守るための新たな減災化施策の検討をするなど、今後も住宅の耐震化にしっかりと取り組んでまいります。
次に、児童相談所の体制強化についてのお尋ねであります。
六月の児童福祉法の改正では、新たに児童相談所に児童心理司や保健師などの専門職を配置することや児童福祉司は国の定める研修を受講しなければならないことが位置づけられました。
本県におきましても、児童虐待相談対応や一時保護の件数は年々増加しておりまして、また、相談内容も複雑、困難な事案が多くなっております。こうした相談や通告、児童の一時保護に迅速かつ的確に対応するため、児童相談センターの体制強化は急務と考えております。
そこで、本年九月に児童相談センターの職員を中心に、人材の育成や相談体制のあり方などを検討するため、機能強化検討委員会を立ち上げました。今後も深刻かつ対応の難しい児童虐待が増加することが見込まれますので、緊急に児童を一時保護する初動体制の整備や虐待を受けた児童への継続的な支援など一連の対策をより一層強化するため、児童福祉司、児童心理司等の必要な人員を確保してまいります。
さらに、法的な対応の強化として弁護士による相談体制の充実を図るとともに、児童福祉司に対する研修内容の充実や国の研修への派遣を通じて、専門性や資質の向上を図ってまいります。
本県といたしましては、このように量と質の両面から児童相談センターのさらなる体制強化を図り、未来を担う子供たちを守るため、児童虐待防止対策にしっかりと取り組んでまいります。
次に、本県農業の経済連携協定への対応についてであります。
経済連携協定による自由貿易圏の構築は、日本一の産業県である本県にとって商工産業分野におけるメリットが大きい一方で、農業分野では関税の撤廃等による輸入品の増加などの影響が懸念されることから、本県農業の生産性向上やブランド化などの競争力を強化し、常に備えておく必要があると考えております。
このため、本年三月に策定をいたしました食と緑の基本計画二〇二〇において、経済連携協定等によるグローバル化を見据えた推進方策を盛り込み、取り組みを進めております。
具体的には、影響が特に懸念される畜産分野において、名古屋コーチンの生産体制強化とさらなるブランド力の強化、肉質と発育にすぐれた新たな系統豚の開発、性判別精液による乳用雌牛の増産、畜産クラスター事業による地域が一体となった施設整備への支援など、さまざまな施策を講じ、未来につながる高収益型の畜産を実現できるよう、着実に取り組みを進めているところであります。
また、既に関税が低く設定されている野菜、花卉等についても、持続的な成長のために競争力の強化は喫緊の課題であり、産地が描く生産拡大などの戦略について、産地パワーアップ事業等により支援をいたしております。
今議会にも畜産クラスター事業、産地パワーアップ事業、さらには抹茶の輸出拡大のための集出荷貯蔵施設整備への支援や農業総合試験場におけるあいち型植物工場の高度化に必要な研究機器等の整備など、県産農産物の競争力強化のための補正予算案を提案しているところであります。
今後とも、こうした攻めの対策に積極的に取り組むとともに、国に対しては農業者の不安を払拭するセーフティネットの整備など、引き続き万全の措置を求めてまいります。
続いて、事故危険箇所の改良についてお答えをいたします。
本県におきましては、幹線道路において集中的に対策を講じるべき交差点など、国の指定を受けた事故危険箇所について、従来から道路を拡幅して右折車線などを整備し、交通の流れを円滑化する抜本対策を進めてまいりました。さらに、平成二十年度からは、既存の道路幅員の中で、カラー舗装や路面表示によりドライバーに直接注意を喚起する県独自の速効対策を導入するなど、広範かつ機動的に取り組みを推進してきたところであります。
平成二十五年度に国の指定を受けた百三十カ所につきましても、抜本対策として、整備中の四カ所を除き、本年度末までに全ての対策を完了させる予定であります。
また、国の指定箇所に加え、県独自の強化策として、毎年、新たに生じる危険箇所についても速やかに対策を実施するとともに、その効果を検証し、次の対策に反映するなど、着実に事故の削減を図ってまいりました。
これらの取り組みにより、対策を実施した箇所では、事故件数を三割以上削減するなどの成果を上げてきております。
さらに、国が昨年度、継続実施を決定した事故危険箇所対策につきましても、県独自の取り組みとして自動車の走行データを活用し、急ブレーキが多発している潜在的な危険箇所を加えることにより、箇所数を約二割拡充し、事故を未然に防ぐ予防対策へと強化を図るなど、新たな交通事故対策の立案を進めているところであります。
今後、国の指定が行われ次第、対策に着手し、幹線道路における交通事故の一層の削減に向けてしっかりと取り組んでまいります。
次に、骨髄バンク事業についてのお尋ねであります。
まずもって、河合議員も触れられましたが、日比健太郎前名古屋市議が亡くなられたこと、大変悲しいことでありまして、まずは御冥福をお祈り申し上げたいというふうに思っております。
さて、骨髄バンク事業は、白血病等の骨髄移植が必要な患者さんと骨髄提供するドナーとの間で命をつなぐ善意の公的事業でありまして、さらに推進していくことが必要であると認識しております。
移植を希望する全ての患者さんがそのチャンスを得るためには、一人でも多くの方のドナー登録への協力が必要であり、特に安定的な骨髄提供体制を維持してくためには、次代を担う若い世代の幅広い理解と共感が求められるところでございます。
そこで、十月の骨髄バンク推進月間に実施している街頭啓発キャンペーンなど、従来からの啓発活動に加え、今年度は、新成人や高校一年生にドナー登録を呼びかけるリーフレットを配布し、若い世代への啓発を強化することといたしております。
また、ドナーの登録機会を充実させることも重要でありまして、近年はイベント会場等において開催する登録会の回数をふやすとともに、昨年一月からは県内に七カ所ある献血ルームにおいて、NPO団体の協力を得て、休日にドナー登録受け付けの呼びかけをしております。
この呼びかけは大きな成果が得られておりまして、昨年度の県内の新規ドナー登録者数は四年ぶりに増加に転じ、今年度も、今までのところ、昨年同時期の登録者数を上回っております。今後とも、関係団体との協力を得ながら、若い世代を中心にした啓発や登録機会の充実により、ドナー登録者数の増加に努めてまいります。
そして、私からの最後の答弁になりますが、骨髄バンクドナー支援事業についてお答えをいたします。
骨髄バンク事業によりまして、移植を希望する患者さんの九割以上にドナーが見つかるようになったものの、実際に移植に至る患者さんは、ドナーの仕事等の都合などから約六割にとどまっているのが現状であります。
このように、ドナーが見つかっても移植に至らないケースを少しでも減らすため、ドナーが骨髄提供しやすくする環境づくりが重要であると認識をいたしております。
環境づくりの一つとして、市町村や都道府県が骨髄提供の際の助成制度を設けるなど、経済的な支援を行うことが考えられます。
そこで、既にこのような支援を行っている自治体の制度やその事業効果を検証するなど、本県といたしましても、骨髄提供への経済的支援について研究を進めてまいりたいと考えております。
また、自治体や一部の企業等が導入しているドナー休暇制度をさらに普及させていくことも必要な対策と考えられますことから、経済団体を通じて企業等に同制度の普及を働きかけてまいります。
愛知県といたしましては、今後ともドナー登録者数の確保及び骨髄提供しやすい環境づくりを進めることで、一人でも多くの患者さんの命が救われるようにしてまいりたいと考えております。
以上、御答弁申し上げました。
- 13:◯警察本部長(桝田好一君) 高齢運転者の交通事故抑止についてお答えいたします。
議員お示しのとおり、高齢運転者によって引き起こされる交通事故の抑止は、県警察にとりまして喫緊の課題であると考えております。
県警察におきましては、高齢運転者に対しまして、加齢に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響等を理解していただくため、各種シミュレーターを活用した参加・体験・実践型の交通安全教育や一定期間内に繰り返して交通事故の当事者となった高齢運転者に対する個別訪問指導を実施しております。
また、運転に不安を覚える高齢運転者の方々が安心して運転免許を返納していただける環境を整えるため、各警察署に運転免許の自主返納の相談窓口を設置しておりますほか、運転経歴証明書の保有者に対する公共交通機関利用時における優遇制度の拡充等に向けた企業等への働きかけ等を強化してまいります。
さらに、来年三月十二日には、免許更新時における認知機能検査により、判断力、記憶力が低くなっている者と判定された場合における臨時適性検査または医師の診断書の提出義務化、また、七十五歳以上の高齢運転者が信号無視や指定場所一時不停止を初めとした十八類型の交通違反を行った場合における臨時認知機能検査の原則受検義務化など、高齢運転者対策の充実を主な内容といたしました改正道路交通法の施行が予定されております。
県警察といたしましては、同法の円滑な施行と県民に対する新制度の周知に向けた取り組みを強化することにより、高齢運転者によって引き起こされる悲惨な交通死亡事故を一件でも減らしてまいりたいと考えております。
- 14:◯教育長(平松直巳君) 教員の多忙化解消についてお尋ねをいただきました。
今回の教員の多忙化解消に向けた取り組みに関する提言におきましては、勤務時間管理や学校マネジメント、教員の在校時間の長時間化の大きな要因である部活動指導のあり方に関して労働安全衛生管理や働き方の見直しなどの観点から、県・市町村教育委員会や学校にそれぞれ求められる取り組みをまとめていただきました。
具体的には、教員の勤務時間外の在校時間の削減に向けた明確な数値目標を設定する、また、部活動指導については、高校や小中学校の体育連盟などの関係団体とも協力して、休養日にかかわる全県的なルールを設定し、それを遵守するための仕組みづくりを進める、さらに、業務量に見合った教職員定数の確保やスクールソーシャルワーカー、部活動指導員等の専門スタッフの拡充を図るなどといった取り組みを御提言いただいております。
教員には、ふえ続ける多種多様な課題への対応に加え、現在、国において検討されている学習指導要領の改訂により、さらなる指導力の向上が求められます。
こうした中、教員が教科指導を初めとする本来業務に専念しつつ、研さんを積むことのできる環境を整えていくことは、学校の設置者、任命権者としての責務であり、県教育委員会といたしましても、今回の提言を重く受けとめております。
この提言を踏まえ、今年度中に取り組む項目を短期と中長期に整理した上で、多忙化解消に向けた県の計画を策定し、保護者や地域の方々を初め、広く県民の御理解を得ながら、市町村教育委員会、学校とも協力し、実行に移してまいりたいと考えております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 15:◯四十一番(中根義高君) 本日はこれをもって散会し、明十二月六日午前十時より本会議を開会されたいという動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
- 16:◯議長(鈴木孝昌君) 中根義高議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 17:◯議長(鈴木孝昌君) 御異議なしと認めます。
明十二月六日午前十時より本会議を開きます。
日程は文書をもって配付いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後二時十二分散会