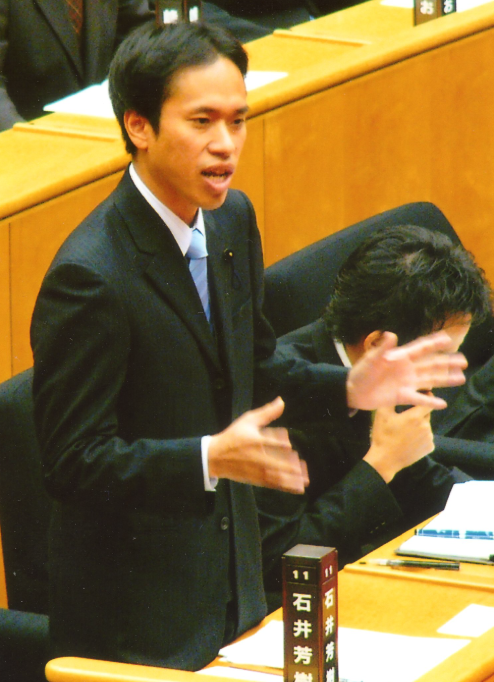
2011年3月8日
◯副議長(奥村悠二君) ただいまから会議を開きます。
直ちに議事日程に従い会議を進めます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
日程第一 第一号議案平成二十三年度愛知県一般会計
予算から第四十七号議案包括外部監査契約の
締結についてまで及び第六十七号議案平成二
十三年度愛知県一般会計補正予算
第一号議案平成二十三年度愛知県一般会計予算から第四十七号議案包括外部監査契約の締結についてまで及び第六十七号議案平成二十三年度愛知県一般会計補正予算を一括議題といたします。
なお、第十八号議案知事等及び職員の給与の特例に関する条例の制定についてのうち、職員に関する事項、第二十五号議案職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正について及び第二十六号議案職員の給与に関する条例の一部改正について、以上三件の議案について、地方公務員法第五条第二項の規定により、人事委員会の意見を徴しましたところ、第十八号議案については、この条例案は、教育長、指定職給料表適用職員及び管理職手当受給職員の給与の減額措置を本年度に引き続き実施しようとするものであるが、本委員会としては、一般職の職員の給与は地方公務員法に定める給与決定の原則により決定されるべきものと考えているので、この措置は残念であると言わざるを得ない。
しかしながら、今回の措置は、本県の極めて厳しい財政状況にかんがみ、時限的措置として実施されるものであると理解されるので、現下の諸情勢を勘案すればやむを得ないものであると考える旨の回答を、第二十五号議案及び第二十六号議案については妥当なものであると認める旨の回答を受けましたので、御報告いたします。
この際、第一号議案平成二十三年度愛知県一般会計予算のうち、第一条中歳出第一款議会費から第五款環境費までの質問を許します。
通告により質問を許可いたします。
鈴木喜博議員。
それでは、歳出第四款県民生活費第五項防災費についてお伺いいたします。
この冬は、非常に寒いということが影響してか、マスコミ報道等を見ておりますと、全国的に年末年始から火災のニュースが多く見られ、その犠牲者も多数出ています。
二月十日に愛知県が行った発表では、一月中の火災の発生件数及び死者数は、ともに前年同期と比較して増加しております。特に死傷者については、県内の交通事故による死者数と肩を並べる十六名となっております。
火災による痛ましい犠牲者は、二月に入っても後を絶たず、また、犠牲者の多くが一般住宅の火災によるものです。国の調査によれば、住宅火災による死者の約六割が逃げおくれによるものであり、また、就寝時間帯の犠牲者が多いのが特徴となっているようです。
こうしたことから、国においては、住宅火災による死者を減らすための切り札として、平成十六年六月に消防法の改正を行い、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置を義務づけしました。
具体的な設置の時期や設置場所については、市町村の火災予防法条例で定めることとされています。設置期限については、設置の早期普及を図るということから、県内の市町村では、全国に先駆け、平成二十年六月を設置期限としています。設置場所については、消防法で定められています寝室及び階段のほか、市町村によっては台所にも設置が義務づけられているとのことです。
つい先日、二月十五日でありますが、私ども丹羽郡におきまして、防災ボランティアD・サポート丹羽の主催で火災訓練が開催されました。ボランティアの方や地元防災委員会の方々が百人ほど参加されております。
その中で、ちょうど五百ミリリットルのペットボトルぐらいの大きさのものでありましたが、火元に投げられるだけで消火ができる投てき型消火用具での訓練を体験しました。
出火で動揺してしまっているときでも、投げるという簡単な動作だけで、女性の方でも、車いすに乗った方でも素早く消火活動ができると大変好評でありました。消火器具も進化しているんだなと感動を覚えたわけですが、このような最新なものも調査研究をしていただくといいのではないでしょうか。
さて、折しも三月一日から七日、きのうまでの一週間は、春の全国予防運動が全国的に展開されておりました。私どもの丹羽郡においては、期間中、広報紙による啓発を初め、消防団の巡回、啓発活動などを実施しておりました。県内各市町村においても、それぞれに啓発活動を展開し、火災予防に取り組んでおられるところであります。
そこでお伺いします。
こうした状況を受け、住宅用火災警報器の設置促進を含めた今後の火災予防対策についてお聞かせください。
以上です。
火災予防対策についてお答えいたします。
議員御指摘のとおり、県内では、本年に入り、火災死者数が増加しており、特に六十五歳以上の高齢者が三分の二を占める憂慮すべき状況となっております。
こうしたことから、愛知県では、二月十八日に県民に対する緊急アピールを発し、各消防本部に、火の取り扱いについて住民の皆様に対する一層の注意の喚起を促すとともに、緊急の街頭キャンペーンなどを行ったところでございます。
また、各消防本部におきましては、春や秋の全国火災予防運動の期間を中心に、ひとり暮らしの高齢者世帯への住宅防火訪問や、防火パレードなどの取り組みを消防団、婦人消防クラブ、少年消防クラブなどと協力して行っているところでございます。
住宅用火災警報器につきましては、平成二十一年度から緊急雇用創出事業基金を活用したキャラバン隊を編成し、消防本部とともに街頭キャンペーンを行うなど、その設置促進を県として支援してまいりました。こうしたことにより、平成二十二年十二月の国の調査結果では、本県の住宅用火災警報器の推計設置率は七〇・九%となっております。
ことしの六月には、消防法による住宅用火災警報器の設置義務化の期限が到来いたしますので、キャラバン隊を集中的に展開するなどの方法により、効果的な啓発活動を各消防本部と連携して実施してまいります。
以上でございます。
進行いたします。
中村すすむ議員。
歳出第二款総務費第二項総務管理費第一目一般管理費のうち、行政改革推進費について質問をいたします。
予算の概要参考資料によりますと、平成二十三年度当初予算案における行革効果額を百九十億円としておりまして、その内訳は、一、未利用財産の処分や県税徴収率のアップによる自主財源の確保三十五億円。二つ、事業の廃止、縮減や事務事業の工夫、改善百二十三億円。三、住居手当の見直しなどによる給与の適正化三十二億円という内訳になっております。
この三つの取り組み内容について、順次お聞きをしていきたいというふうに思います。
まず、自主財源の確保策についてでありますけれども、この二十三年度の目標として掲げた未利用財産の処分の具体的な内容と金額、これをお示しいただきたいと思います。
あわせて、二十四年度以降、処分を検討している未利用財産は何があるのか、これもあわせてお聞きをしたいと思います。
次に、県税徴収率のアップ、このことについて、ここ五年間の県税徴収率の推移について、その実績をお聞かせください。この期間の数値、上下変動があったと思いますが、その変動要素についても、あわせてお聞きをしたいと思います。
二つ目に、事務事業の廃止、縮減について伺います。
先ほど申し上げましたように、二十三年度の行革目標百二十三億円ということで見込んでおられますけれども、二十二年度の比較でどのような特徴があるのか、これをお聞きします。
そして、この二十三年度、どんな事業が廃止、縮減の対象になるのか、お示しをいただきたいと思います。
三つ目、給与等の適正化では、住居手当の見直し等で三十二億円の行革効果を見込んでいるということでございましたが、第五次行革大綱の中では、各種手当などについては、趣旨や社会情勢の変化を踏まえ、そのあり方を見直すという取り組み方針を掲げております。住居手当のほかに今後見直しを検討されている手当などがありますか、お聞かせをください。
また、給与制度の適正化という行革大綱の方針では、民間給与との均衡を図ることを基本とする人事委員会勧告制度を尊重して、給与制度の適正化に取り組むと、こういうふうに掲げておりますが、現状の給与制度にどのような課題があると認識され、どのような方向で適正化を進めようとしているのかお聞きをしたいと思います。
続いて、歳出第二款総務費第三項徴税費第二目賦課徴収費のうち、県税確保特別対策費について質問をいたします。
私は、二年前の議案質疑の場でも、個人県民税をいかに確保するかという質問をさせていただきました。当時は、急激な景気後退を受けて、個人県民税の滞納が想定されたときでありました。
その滞納抑止策をどのように進めるおつもりかという質問をしましたところ、実際に徴収業務を行う市町村と連携して四つの取り組みを進めるという答弁をいただきました。その一つは、市町村職員とともに研修会を実施するということ。二つ目、県と市町村が一緒になって滞納整理業務を行って、ノウハウを共有するということ。三つ目、県庁税務課にアドバイザーを置いて、市町村の相談に乗るということ。四つ目、高額滞納者に対しては、県が市町村民税も含めて徴収を実施するという回答でございました。
この徴収実務、実は私も地元で聞きましたけれども、新しいノウハウを活用して徴収成果が上がったという声も聞いております。
そこで、一つ目の質問です。
県と市町村が協力、連携して進めている、今申し上げた四つの取り組み、どのような成果をあげられたのか、この実績についてお尋ねをいたします。
また、実務を行う市町村の反応、あるいは新たな要望等がありましたら、これもお聞かせをいただきたいと思います。
二つ目、こうした実績が上がっているだろうというふうに思うんですが、こうした状況の中で、今回、県内六ブロックに分けて、新たに地方税滞納整理機構を立ち上げて、県税収入確保に向けてさらに進めていくという提案がございます。
先ほど申し上げました市町村と連携したこれまでのさまざまな取り組みに加えまして、今回のブロックに分けて組織を立ち上げて取り組むことのねらい、そして、従来に比べてどのような効果を想定されておるのかお聞きをします。
以上です。
自主財源の確保策についてお尋ねをいただきました。
まず、未利用財産の処分についてお答えをいたします。
平成二十三年度は、廃止しました県職員住宅、県営住宅、警察署、交番等の用地、計十一件と廃川廃道敷地の売却を予定しておりまして、二十九億八千万円の収入を見込んでいるところでございます。
二十四年度以降の未利用財産の処分につきましては、売却に向けての条件整備を行い、順次処分を進めてまいります。
処分を予定している主なものといたしましては、今年度末に用途廃止を予定しております教職員住宅や、行革により廃止いたしました施設用地などがございます。
次に、県税徴収率についてお答え申し上げます。
まず、最近五カ年の徴収率でございますけれども、平成十七年度が九七・三%、十八年度が九七・七%、十九年度が九七・八%、二十年度が九七・七%、二十一年度が九六・二%、このようになっております。
平成十七年度から十九年度まで徴収率が向上しているのは、この間、景気が回復傾向にあり、徴収率の高い法人二税の税収がふえたことや、平成十八年度のコンビニ納税の導入によりまして、自動車税の徴収率が向上したことが要因でございます。
また、平成二十年度以降低下しておりますのは、十九年度に行われました所得税から住民税への税源移譲による課税額の増加に伴いまして、個人県民税の収入未済額が増加したことや、法人二税収入が大幅に減少したことによるものでございます。
次に、事務事業の廃止、縮減についてお答えいたします。
二十三年度当初予算においては、施策の見直しや事務事業の工夫改善による効果を百二十三億円と見込んでおります。これを二十二年度当初予算と比較いたしますと、二十二年度予算における効果額は五百四十八億円であり、規模が大きく相違しております。これは、二十二年度の効果額に投資的経費の縮減額三百三億円が含まれている一方、二十三年度当初予算は骨格予算であり、例えば投資的経費の道路、河川の整備等は、前年度の五〇%程度の計上としているため、今回は投資的経費の縮減額を算定していないことなどによるものでございます。
また、廃止、縮減の対象についてお答えをいたします。
二十三年度当初予算案におけます効果額百二十三億円のうち、事務事業の廃止、縮減による歳出削減額は九十億円であり、このほか、職員の削減や県が単独で措置している教職員定数の見直しによるものが三十三億円でございます。
廃止する事業といたしましては、例えば近年の金利の低下など社会経済状況の変化から、市町村からの貸付要望が減少している市町村振興資金貸付金を廃止するものなどがございます。また、縮減する事業といたしましては、例えば公の施設の指定管理者の選定に当たりまして、公募を拡大したことにより経費を縮減する事例などがございます。
次に、個人県民税の徴収確保対策のお尋ねのうち、県と市町村が協力、連携して行っております四つの取り組みの実績についてお答えいたします。
一点目の市町村職員向けの徴収の研修会につきましては、平成二十一年度は七回実施し、延べ三百九人の市町村職員が参加しております。
二点目の県と市町村職員が一緒に滞納整理業務を行います税務職員の交流制度につきましては、平成十四年度から二十一年度までの八年間で、延べ百三十五団体に対しまして、県の職員を延べ二百二人派遣し、滞納整理に関する実践的な指導を行っております。
三点目の徴収支援アドバイザーにつきましては、平成十九年度から税務課内に経験豊富な税務職員六名を配置しまして、徴収業務全般にわたりまして市町村からの相談に応じております。
四点目の地方税法第四十八条の規定に基づきます県による個人住民税の直接徴収でございます。平成十六年度から二十一年度までの六年間で、市町村から約十五億七千八百万円の徴収困難な滞納事案を引き受けまして、約八億七千百万円を県が直接徴収いたしました。
なお、これらの取り組みに対しましては、市町村の担当職員からは、徴収事務を行う上で非常に役立つものであった、自分のスキルアップにつながったとの声を聞いております。また、市町村からは、収入未済額の縮減に向けて、県と連携、協力をさらに強化してもらいたいとの要望をいただいているところでございます。
最後に、地方税滞納整理機構の設立につきましてお答えいたします。
収入未済額の縮減は、県と市町村共通の喫緊の課題であり、先ほど申し上げましたとおり、さまざまな取り組みによりまして、一定の成果をあげているところではございますが、さらにこれに加えまして、地方税滞納整理機構を設立することといたしました。
今回設立する機構は、県と市町村の徴収職員が一つの組織の中で、年間を通じて継続的に滞納事案の処理を行うことによりまして、収入未済額の縮減と市町村職員の徴収技術の向上を図ることをねらいとしております。
二十三年度は、県内五十四市町村のうち四十三の市町村が参加し、個人県民税のほか市町村の固定資産税などを含めまして、四十億円程度の滞納事案の引き継ぎを受けまして、引き継ぎ額の三〇%以上を徴収することを目標としておりますが、このうち、個人県民税といたしましては二億四千万円の収入を見込んでおります。
市町村と連携、協力しながら、目標達成に向けましてしっかりと取り組んでまいります。
以上でございます。
給与等の適正化につきましてお答えをいたします。
まず、手当の見直しについてでございますが、御質問にありました住居手当のほか、さまざまな手当の見直しを行ってまいりました。
見直しを行いました主な手当といたしましては、地域の民間給与水準と均衡を図るために支給をしております地域手当につきまして、従来の一〇%支給を二十一、二十二年度の二年間で六・五%まで引き下げたところでございます。また、特殊勤務手当につきましては、月額支給の手当を日額支給に見直しを行ったほか、支給基準などを見直したことで、平成十一年度、四十四手当を平成二十二年度までに二十手当としたところでございます。さらに、教員の人材確保を目的として支給をしております義務教育等教員特別手当の支給額を二十年度から三年間で約六割を削減いたしました。
これまで、こうしたさまざまな見直しを行ってまいりましたが、特殊勤務手当の一部には日額支給となっていないものもございまして、こうした手当も含めまして、今後とも計画的に見直しを行ってまいります。
次に、人事委員会の勧告制度に対する課題認識と給与制度の適正化への取り組みについてでございます。
人事委員会の勧告は、公務員の労働基本権の制約に対する代償措置でございまして、まずは、この勧告を尊重してまいりたいと考えているところでございます。
この勧告制度は、かねてより中小企業の従業員の給与実態が反映されていないという指摘がございまして、平成十八年度から、調査企業の従業員の規模を百人から五十人へ引き下げたところでございます。
さらに、高齢層職員の給与が民間と比べまして高いことを踏まえまして、平成二十三年度から五十五歳以上の職員給与を一・五%削減する制度改正を行ったところでございます。
今後とも、県民の皆様方の理解と納得が十分得られるよう、給与制度の適正化に向け努力をしてまいります。
以上でございます。
進行いたします。
峰野修議員。
冒頭、私の地元で発生しました高病原性鳥インフルエンザの発生に当たりまして、大村知事には、就任直後の大変お忙しい中を陣頭指揮に駆けつけていただき、また、その後も適切な御指示をいただき、大変感謝いたしております。冒頭、お礼申し上げます。
また、県当局におかれましても、農林水産部長を初め、非常に不眠不休の御検討をいただきましたこと、地元民を代表いたしまして、重ねてお礼申し上げます。
また、三月十二日には、大村知事のお約束で、卵ぶっかけ御飯の試食をやっていただけると、風評被害の防止に知事みずから陣頭に立ってがんばっていただけることを重ねてお礼申し上げます。
それでは、私からは、歳出第三款地域振興費第一項地域振興総務費のうち、山村振興施策についてお伺いします。
私の地元の新城市と北設楽郡は、人口六万人でありますが、県土の面積の約二割強を占めております。その約九割が森林であり、水や空気の供給、県土保全などの多面的機能を持ち、都市地域を含めた県全体の生命を支える極めて重要な役割を担っております。
しかしながら、近年、急激な少子・高齢化、若年層の都市部への流出、そして、地元の産業・経済活動の低迷により、地域社会の活力が低下する極めて深刻な状態に陥っております。
具体的には、例えば放棄された山林や農地の拡大、鳥獣害被害や集落機能の喪失など、さまざまな問題に直面しておりますが、居住する者が減少すればするほどこの傾向に拍車がかかり、その結果、山村の持つ重要機能が損なわれていきます。
山間地域に人間が住み続けていかなくてはなりません。たとえ少ない人でも、そこに住んでいただくことで大事な環境が守られるのです。しっかり整備していく必要があります。
そうした中、県におかれましては、平成二十年度に、三河山間地域の振興を総合的に推進するため、本庁に部局横断的な組織である山村振興推進本部を立ち上げ、さらに地域振興部に山村振興室、現地に新城設楽山村振興事務所を設置するなど組織整備を図り、積極的に山村振興を推進する体制をつくられました。
さらに、三河山間地域の将来像を描くとともに、その実現に向けた重点的な取り組みの方向性を明らかにするあいち山村振興ビジョンを平成二十一年三月に策定され、その推進を図ってこられました。このことに対し、まずもって厚く御礼申し上げます。
ビジョンの重点施策には、各部局とも多くの事業を盛り込んでいただいておりますが、特に地域振興部に関して言えば、予算にもありますように、県と三河山間市町村で構成される愛知県交流居住センターを平成二十年度に開設し、都市と農山村間の交流、居住の推進に積極的に取り組まれてきました。
この三河山間地域は、自然、歴史、伝統文化や特産品など、世界に誇れるすばらしい地域資源を多く保有しております。こうした奥三河の魅力の発信と新たな観光資源の発掘を目的に、来年度、新城市では、観光交流サミットが開催されます。
また、今後、新東名の新城インターチェンジ予定地周辺に道の駅を整備し、観光情報の発信及び地域産品の販売拠点として活用する計画があるなど、地元では積極的な交流人口の拡大を図っています。
折しも、新東名高速道路や三遠南信自動車道の開通など、交流人口の拡大の起爆剤となる基盤が整いつつある中、県においても積極的な取り組みが望まれるところであります。
さて、もう一点触れておきたいのは、近年、深刻化が懸念される小規模で高齢化が著しい集落についての対策であります。
予算にありますように、これまで集落機能の維持を図るための集落支援対策がとられてきました。特に、最近よく報道で取り上げられておりますが、こうした集落で、いわゆる買い物弱者や交通弱者対策、地域の見回り対策など、新たなニーズが発生しているのも事実です。
この間もニュースで取り上げられましたが、山間地域の高齢者世帯や独居高齢者にあって、車を所有しない方がふえており、買い物、通院など、日常生活の必要最低限の移動にさえ支障が生じています。
また、集落の居住者間のコミュニケーションが喪失するという危機にも見舞われております。私の住む集落でも、将来に大変な不安を抱えておられるのをよく耳にします。いち早い対策が緊急に求められております。
厳しい県財政の中で、山村振興の中心的存在としての地域振興部の予算は、こうした山間地域の要望に的確にこたえる地域の活性化対策について、どのような内容を新年度予算に盛り込んでおられるのか、非常に注目するところであります。
そこで伺います。
第一点、奥三河地域の活性化を図るためには、都市と山村の交流を一層促進することが重要であると考えますが、交流人口を拡大するためにどのような取り組みをされるのかお伺いします。
第二点、小規模高齢化集落に暮らす人々が安心して暮らしていけるよう、県はどのように支援していくのかお伺いします。
続いて、第五款環境費第一項環境対策費、あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業費についてお伺いします。
本県では、平成二十一年度からあいち森と緑づくり税を導入し、その税収を財源として、森や緑の持つ公益的機能の整備保全を図るため、森林や里山林の整備、都市緑化などの施策に取り組まれております。そして、その一環として、市町村やNPO、ボランティア団体が行う環境保全活動や環境学習活動を支援するあいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業を推進しています。
例えば私の地元の新城市でも、お寺の裏山にヤマザクラ、落葉広葉樹を植樹し、里山林として整備する事業が始まりました。これは、地元の檀家の方、小学校の生徒さん、地域を代表する企業の方々、地域外の方々の支援をいただいて、大変大きな広がりを持った事業となっております。こうした活動を通じて、地域の環境力を高めるという点で、この支援事業は大いに意義があります。
さて、昨年十月には生物多様性条約第十回締約国会議(COP10)がこの地域を会場として成功のうちに開催されました。
COP10の成果として、名古屋議定書、愛知ターゲットといったこの地域の名を冠した国際的な取り決めが採択されたことは、安全、円滑な会議運営に貢献した開催地の開催県の努力が世界から高い評価を受けたものと大変喜ばしく思います。
一方で、本県は、COP10の開催を通じ、生物多様性に関するさまざまな取り組みが展開され、多くの方々がその重要性を再認識し、自分たちのできる行動について考える機会となりました。この環境意識の高まりをこれからの地域の中でしっかりと受け継ぎ、総動員し、活動に結びつけていくということが大切ではないかと考えております。
こうした県域を巻き込んだ全体の大きな流れをつくっていくために、あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業はまさにうってつけの事業であります。これからもさまざまな地域からの提案、アイデアを受け、多くのものが出てくると期待されております。
そこでお伺いします。
このように、二年間事業を実施してきたわけですが、この成果をどうとらえているのかお伺いします。
次に、COP10の開催を受け、地域の多様な主体による自主的な環境学習・環境保全活動を全県に広めていくことが重要であると考えますが、今後どのように取り組んでいかれるのかお伺いします。
山村振興施策についての御質問のうち、まず、交流人口の拡大に関する取り組みについてお答えをいたします。
人口の減少が続いております奥三河地域の活性化を図るためには、豊かな自然や伝統文化、特産品などの地域資源を最大限に活用して、交流人口を拡大することが極めて重要でございます。
そのため、平成二十三年度においても、今年度に引き続き、市町村と連携しながら、交流人口の拡大に向けたさまざまな取り組みを実施してまいります。
主な取り組みとしまして、特産品販売や伝統工芸品の製作体験などを通じて山村の暮らしを紹介する三河の山里体験プラザを開催いたします。多くの集客が見込める名古屋市内で開催し、山里のさまざまな魅力発信に努め、都市部の方々の山村に対する関心を高めてまいります。
また、都市部の方が繰り返し山村を訪問していただけるように、愛知県交流居住センターを通じて、三河山間地域で行う農林漁業体験や祭りなどの交流イベントに積極的に取り組んでまいります。
さらに、ふるさと雇用再生特別基金事業を利用し、廃校となった校舎や温泉街に現代アートを展示するイベント「きてみん!奥三河」を開催し、交流人口の一層の拡大を図ってまいります。
次に、小規模高齢化集落の人々が安心して暮らしていける支援策についてでございます。
高齢化が進んだ小規模な集落では、集落機能の維持が困難になってきておりますので、集落の現状や課題について、住民の間の話し合いを促進し、課題の解決に向け支援を行う集落支援員の育成が重要でございます。
そのため、今年度から集落支援員の育成を豊田市の三集落で開始したところでございます。ひとり暮らしの高齢者の安否確認や遊休農地の活用など、課題解決に中心的な役割を果たしており、集落の方々に大変喜ばれておりますので、来年度は、他の市町村の集落にも拡大し、育成してまいります。
また、三河山間地域では、議員の御指摘のとおり、地元商店の減少と高齢化の進展により、日常の買い物に不自由を感じている方がふえております。こうした状況に対応するため、緊急雇用創出事業基金事業を活用して、今年度、県としては初めて宅配や移動販売する事業を実験的に新城市作手地区で行いました。
利用実績や住民の御意見をもとに、地元ニーズを的確に把握し、より改善した内容で来年度も取り組み、あわせて地元による継続可能な手法を市町村や商工団体等と検討してまいります。
以上でございます。
あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業について、まず、その成果でございます。
この事業により助成いたしました団体数は、平成二十一年度、四十五、二十二年度、八十七の計百三十二団体に上っております。そして、その活動でございますけれども、間伐など里山の保全、再生活動、森や緑による水質浄化の学習活動、緑のカーテンの設置など、さまざまな取り組みが県内各地で実施されました。
また、そうした取り組みに参加された方々からは、森と緑の重要性について大変理解が深まって、今後植樹などに参加したい、あるいは自分たちもグループをつくって活動したいといった声が多く寄せられておりまして、この事業が県民の皆様の理解を深め、意識から実践活動へ一歩踏み出していただく上で大変役立っているものと認識いたしております。
次に、こうした活動を広めていくための今後の取り組みについてでございます。
生物多様性の保全など実践的な取り組みを全県に広めていくことが大きなCOP10の成果の継承でありますので、この環境学習、環境活動・学習推進事業を活用いたしまして、積極的に取り組んでまいります。
具体には、これまでの取り組みを事例集として取りまとめ、イベント等で配布、インターネットで情報発信いたしますとともに、活動団体の一年の成果報告会を一般の方々の参加を得まして定期に開催するなど、活動の広がりに努めてまいります。
また、あいち森と緑づくり税を生かしたこの支援事業の予算につきましても、今年度はCOP10の開催に合わせ、その規模を大幅に拡大したところでございますけれども、来年度もそれを維持し、県民の皆様の実践活動の普及を財政面からしっかり支えてまいりたいと考えております。
以上でございます。
進行いたします。
神野博史議員。
通告に従いまして、私は、歳出第五款環境費第一項環境対策費における環境保全規制調査費に関連してお伺いいたします。
近年、生活の質、クオリティー・オブ・ライフに対する住民意識が高くなってきておりますが、できる限りよい環境のもとで生活したいというのは、どの地域においても住民の皆さんの率直な感情であると思います。
生活環境に問題のある地域では、それぞれ改善に向けて取り組みを進めているとは思いますが、さまざまな要因によりなかなか進展が見られないところも多く見受けられます。この点、私の地元であります東海市においても、長年にわたって降下ばいじんが地域住民の生活環境に多大な影響を及ぼしており、その改善が長年の課題になっております。
そこで、私は、この問題について、住民の皆さんの意見を聞くために、去る二月に、東海市養父町における市民対話集会を開催しましたところ、皆さんからは、ガラス戸をふけばぞうきんが真っ黒になる、自動車にばいじんが降り積もる、洗濯機が汚れるなどの生活環境への被害や、健康に対する不安から健康診断をしてほしいなど、大変多くの発言がありました。
このように、県、市、企業など関係者の皆さんの長年にわたる努力にもかかわらず、養父町を中心とした生活環境はほとんど改善されていないというのが住民の実感であります。
実際、東海市内の降下ばいじん量の状況を見ますと、平成二十一年度の市内平均は、一月に一平方キロメートル当たり四・二トン、最も多い南部地域の養父児童館では八・四トンであり、十八年度の四・八トン、九トンと比べて少し改善は見られるものの、依然として県内平均より多く、養父児童館では県内平均の三倍以上であります。
私も、この問題については、過日行われました本会議や委員会などで質問を行うなど、機会あるごとに生活環境の改善を強く求めてきたところであり、これを受けて、愛知県により、平成二十年度に、東海市及びその周辺の二十一地点で降下ばいじんの調査を広域的かつ組織的に実施していただきました。
この調査結果からは、発生源は特定できなかったものの、臨海部付近において降下ばいじん量が多いことがわかり、臨海部に立地する企業によるばいじんや粉じんの発生防止対策の必要性が改めて明らかになったと思っております。
また、これまで降下ばいじん量の改善に向け、臨海部の企業に対し、県と市が連携してさまざまな対策を指導するとともに、立入検査などを行い、企業もいろいろと取り組んでいることは承知しておりますが、その結果が目に見える形であらわれていないのが実情であります。
そこで、二点お伺いいたします。
一点目は、東海市内における降下ばいじん量についてどのように認識し、その改善に向けた臨海部の企業への指導の取り組み及び企業が実施している具体的な対策などをどのように進められてきているのかお尋ねいたします。
二点目は、少しずつ改善が見られるとはいうものの、県内のほかの地域の降下ばいじん量と比べて多く、住民の方々が改善の実感がほとんどない状況にあることから一層の改善が必要と考えますが、今後県としてどのように取り組んでいかれるのかお尋ねいたします。
一方、降下ばいじんの発生源となるばい煙発生施設や粉じん発生施設には、法や条例で排出基準や管理基準が定められており、その遵守は企業の当然の責務であります。
しかしながら、昨今、一部企業による測定データの偽装などが後を絶たないということから、昨年の五月に大気汚染防止法の一部改正により、虚偽の記録などに対する罰則が創設され、また、県条例についても、本二月議会に同様の改正案が上程されております。一般論でありますが、これは基準の適合状況を判断するための測定や結果などについて間違いがあってはいけません。正確であること、そして、正確であることの客観的な確認が不可欠であるということは言うまでもありません。
そこで、事業者による測定結果などの客観的な担保について、法及び条例の改正を踏まえて、県として具体的にどのように行っていくのかも関連してお尋ねいたします。
以上です。
降下ばいじん対策について、まず、東海市内の降下ばいじんについての認識と改善に向けた取り組みについてでございます。
降下ばいじんは、工場等からのばいじんや粉じん、自然由来の土壌粒子の巻き上げなど、多様な原因がございますけれども、工場のばいじんや粉じんの対策といたしましては、法や条例によりまして、発生施設の排出規制などにより低減を図っているところでございます。
こうした中、東海市内の降下ばいじんでございますけれども、改善の兆しが見られるものの、県内の他地域に比べ依然として高い状況にあると認識いたしておりまして、従来から本県、東海市、臨海部の企業で構成する降下ばいじん対策検討会におきまして、企業に対し、粉じん等の発生を防止する具体的な対策を県として働きかけてまいりました。
その結果でございますけれども、企業によりスラグ等の処理を屋内で行う、集じん装置の能力の増強、スラグ等の堆積場への防風用環境ネットの設置、場内道路の舗装化などが実施されてきたところであります。さらに企業として、住民の方々にそうした対策を見ていただくなど、周辺住民の皆様の理解を得る努力をされているところでございます。
次に、今後の取り組みについてでございます。
県として、東海市とともに降下ばいじん量調査による実態把握に今後とも努めてまいります。また、こうした調査結果を説明し、降下ばいじんによる被害の実態や、企業による対策の状況等について、意見等をお聞きする住民の方々との定期的な話し合いを続けてまいりたいと考えております。
こうした取り組みを踏まえ、降下ばいじん対策検討会を通して、企業に対し、粉じん等の発生防止対策のさらなる徹底、粉じんやばいじんの発生が少ない施設への更新など、改善対策を働きかけてまいります。
次に、事業者による測定結果の客観的な担保という点でございます。
県では、法、条例による工場、事業場への立入検査を年間約三千件実施しております。ばい煙発生施設や処理施設の運転管理状況を現場で確認いたしますとともに、必要に応じ、県みずからばい煙測定を実施いたしまして、排出基準の適合状況の確認を行っております。
今後は、こうした立入の際に、事業者によるばい煙測定記録と実際に測定を行った業者が発行いたします計量証明書というものがございます。これは、実際の測定値が記載されている書類でございますけれども、それとの照合を必ず実施すること、そして、記録簿作成時に複数の者がチェックしているかどうかを確認することなど、今まで以上にデータ偽装の防止に努めてまいりたいと考えております。
また、その際でございますけれども、法と条例、条例につきましては、今議会で条例案を上程いたしておりまして、それをお認めいただければという前提でございますけれども、法、条例双方に測定結果の記録義務違反による罰則規定が新設されますことを周知徹底してまいりたいと考えておるところでございます。
以上でございます。
ただいまの質問に対しまして、それぞれ御答弁をいただきましたが、二点要望させていただきます。
一点目は、降下ばいじん対策の強化であります。
降下ばいじんに悩まされている地域の皆さんにとって、少しでも早く快適に過ごせる生活環境にしていただくことが一番の願いであります。生活環境改善の観点から、企業に対して、中長期の視点に立った計画的な対策の徹底を強力に指導していただくよう要望しておきます。
二点目は、降下ばいじん調査の継続についてであります。
平成二十年度に臨海部周辺の降下ばいじん調査を広域的かつ組織的に実施していただきましたが、発生源の特定や実効性のある対策を進めていただくために、地域的な状況の変化をしっかり把握していくことが重要と考えますので、今後、早い時期に同様な調査を実施していただくよう要望いたしまして、私の質問を終わります。
進行いたします。
伊藤勝人議員。
第四款県民生活費第四項統計調査費のうち、経済センサス活動調査費についてお伺いをいたします。
世界の片隅で起こった出来事の情報が瞬時に世界を駆け回り、大きなうねりとなって地球を回り、さまざまな影響を与えるようになっております。エジプト、リビア、バーレーンなどの中東諸国の情勢が石油市場に大きな影響を与え、景気の下振れリスクとなることが懸念されております。
当地の経済は、平成十四年二月から始まった戦後最長の景気拡大の中で、物づくり産業、特に自動車関連を初めとする輸出産業の順調な伸びに支えられ、元気な愛知と表現されるほどの成長を続けてまいりました。
しかしながら、平成二十年九月、アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズの経営破綻から始まった世界金融危機の影響を受け、一転、本県経済も急速な景気後退を迎え、大変厳しい状況が続くことになりました。そして、その後は、海外経済の改善や各種の政策効果に支えられ、先月二月の政府月例経済報告によりますと、景気は持ち直しに向けた動きが見られ、足踏み状態を脱しつつあると表現され、先行きについても、海外景気や為替レート、原油価格の動向等の下振れリスクが存在するものの、景気が持ち直していくことが期待されるとされております。
最近、愛知県が公表した鉱工業生産等の動きをとらえる生産動態統計調査や、労働市場の動きをとらえる毎月勤労統計調査の結果によりますと、昨年十二月の鉱工業の生産指数は前月に比べて五・四%上昇し、二カ月間連続の上昇となっております。
また、雇用面で見てみますと、同じ月の残業時間は前年に比べて一〇%増となっており、製造業についても一七・八%増となっております。
また、県内の完全失業者は、平成二十二年平均で前年より一万人少ない十七万二千人となっており、完全失業率も四・三%と前年に比べて〇・二%減となっております。
統計は社会を映す鏡であると言われておりますが、このように統計情報は、社会経済で生じている事柄を正確に把握し、国や地方公共団体の的確な行政施策の実行や、民間企業が経営判断を行う上で不可欠なものであります。今回の金融危機の際にも、経済社会の不透明感が世界全体に強まりましたが、こうした不確実性の高い時代であればこそ、統計の果たす役割は従来にも増して重要となってきています。
経済センサスは、これまで経済に関する統計調査が工業や商業などの分野ごとに異なる年次や周期で実施され、調査を受ける側の負担が大きく、また、GDPや県民経済計算などの推計データとして情報不足が否めなかったところであります。それらの諸課題を解決するため、平成二十一年度に新たな経済統計として創設されたと聞いております。
そこでお尋ねをいたします。
この新たに創設された経済センサスについては、来年度に活動調査が予定されているとのことでありますが、この活動調査はどのような調査であるのか、また、愛知県としてどのように取り組み、その成果をどのように活用されるのかをお伺いいたします。
経済センサス活動調査に関してお答えを申し上げます。
経済センサスは、我が国の全産業の経済活動を同一時点で網羅的に把握する経済統計として新たに創設され、統計法に基づき国が実施するものでございますが、県内における調査事務につきましては、本県及び県内の全市町村が法定受託事務として実施をいたします。
この経済センサスは二段構えの調査体系となっておりまして、平成二十一年七月には、どこにどのような事業所、企業があるのかを把握するための経済センサス基礎調査が実施されております。そして、来年二月には、基礎調査によって得られた情報を活用し、売上高など経済活動の把握に重点を置いた経済の国勢調査とも言われる経済センサス活動調査が実施されることとなっております。
活動調査の調査対象は、農林漁業に属する個人経営の事業所を除くすべての事業所及び企業で、名称、所在地、従業者数等の基本的事項のほか、売上高、必要経費等の経理項目に重点を置いた調査となっております。
次に、本県の取り組みとその成果の活用についてでございます。
経済センサス活動調査の愛知県内の対象事業所数は約三十四万事業所で、約四千六百人の調査員が調査を担当いたします。何分初めての調査でございますので、事業所に対しては、関係団体等を通じた協力依頼や、さまざまな機会や媒体を活用した広報を行って理解を深め、また、市町村や統計調査員に対しましては、説明会などを通じて調査方法等の周知徹底を図り、円滑かつ正確に調査が進むよう努めてまいります。
この調査結果は、国においては、国民経済計算の推計資料を初め、環境、雇用、中小企業等、政策のための重要な基礎資料として活用されるほか、地方公共団体では、総合計画や都市計画を初め、産業振興対策などにおいて、地域の実情に対応したきめ細かな施策を展開するための基礎資料として幅広く活用されます。また、民間においても、経営計画、出店計画などの基礎資料として活用していただけます。
この調査結果の成果がさまざまな分野において活用されるよう、正確で信頼できる統計の作成に努めてまいります。
以上でございます。
お願いをしておきたいと思います。
統計は、不透明な未来を切り開くための羅針盤です。今後とも、国、県、市町村の統計調査員の皆さんが連携を密にして、より精度の高い信頼される統計の作成に取り組んでいただくことをお願いいたしておきたいと思います。
そして、ともすると、統計をとった側に情報が集積をされて、そこのところが御活用になられるという部分が多いというのが今までであったような気がしております。
今回、せっかく、このきちっとしたすごい統計が、三十四万事業所の方たちからデータをいただくことになりますね。このデータをリターンといいますか、統計をとられる側の皆さんにいい情報を御提供いただいて、ともにメリットのあるような方向で御活用をいただけるようにお願いを申し上げておきたいと思います。
以上であります。
次に、第一号議案平成二十三年度愛知県一般会計予算のうち、第一条中歳出第六款健康福祉費から第八款農林水産費までの質問を許します。
通告により質問を許可いたします。
川嶋太郎議員。
私からは、認知症の高齢者について、第六款健康福祉費第四項高齢福祉費のうち、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費について及び第五項障害福祉費のうち、認知症疾患医療センター費についてお伺いいたします。
戦後、我が国では、経済成長と医学の進歩が相まって平均寿命が延び続け、現在、世界屈指の長寿大国となっております。
これは大変すばらしいことでありますが、一方で、高齢者をめぐるさまざまな問題が浮かび上がってきております。人口の高齢化に伴う認知症の増加もその一つであります。
認知症高齢者の年齢段階別出現率について、平成四年と少し古いデータですが、御紹介をいたしますと、六十五歳から六十九歳で一・五%、七十歳から七十四歳で三・六%、七十五歳から七十九歳で七・一%、八十歳から八十四歳で一四・六%、八十五歳以上では実に二七・三%となっており、これからの高齢社会において、認知症は大きな社会問題になっていくと考えられます。
本県の状況を見てみますと、本県の高齢化率は、平成二十三年一月一日現在、二〇・二%でありますが、平成三十七年(二〇二五年)には二六・五%になると推計されております。
高齢化の進展に伴い、認知症の高齢者の方の数が増加すると予想されており、本県の認知症高齢者につきましては、平成二十二年の十万八千人が平成三十七年(二〇二五年)には十八万人に増加すると推計されております。
また、現状においても、高齢者世帯の増加により認知症の方を認知症の方が介護するという認認介護の問題が出てきているなど、認知症への対応はまさに喫緊の課題であると言えます。
高齢者の方が認知症になられますと、記憶や理解、判断力の低下により生活へ支障が出てくることから、自信を失い、将来への望みも失って、うつ状態に陥ることも少なくありません。
また、介護する家族の方も、症状が進行してくるとコミュニケーションがとりにくくなったり、妄想や徘回、排せつの失敗などが起きてくると、常に見守りや介護が必要となってくることから、家族が疲弊し、共倒れになってしまうこともよく見受けられます。特に徘回は、時に交通事故に遭ったり、行方不明になる可能性もある。また、家族だけではなかなか対応し切れないものであります。
これに対し、県では、平成十九年度より認知症地域資源活用モデル事業を実施し、モデル市町村において、認知症の方やその家族が安心して暮らせる地域づくりに向けて、徘回などによる事故を未然に防ぐため、住民の方に参加していただいて、徘回高齢者の捜索、発見、通報、保護や見守りのためのネットワークづくりなどに取り組まれているとお聞きしております。
そこで質問ですが、認知症地域資源活用モデル事業の成果を踏まえて、県では、認知症高齢者の方やその御家族を地域で支える体制づくりにどのように取り組んでいかれるのかお伺いいたします。
次に、認知症に対する医療対策についてでありますが、かつては治療のすべがないとされていた認知症も、現在では医学の進歩とともに治療法も発展し、根治療法とまではいかないまでも、早期に発見し、適切な治療を受ければ、進行をおくらせたり、症状を軽くすることができるようになっております。
県事業としては、認知症対策等総合支援事業のうち、地域医療支援事業として、かかりつけ医認知症対応力向上研修や認知症サポート医養成研修などを行い、早期発見、早期治療に向けた取り組みをされてきましたが、認知症患者は近年大幅に増加しつつあり、また、認知症と身体疾患の合併症の患者も増加していることから、地域における医療体制の充実や、介護関係機関と医療機関との連携強化を図っていく必要性が高まってきております。
これらの問題に対応するため、来年度、新たに認知症疾患医療センター事業を始めるとお聞きしております。
そこで質問ですが、認知症疾患医療センター事業は、地域の認知症医療体制を強化するための取り組みを国立長寿医療研究センターにおいて行っていくとお聞きしておりますが、具体的にどのような取り組みを行っていくのかお伺いいたします。また、この事業は、本県の認知症医療対策を推進していく上でどのような効果があるのかお伺いをいたします。
以上です。
認知症に関するお尋ねのうち、認知症高齢者の方やその御家族を地域で支える体制づくりへの県の取り組みについてお答えをいたします。
認知症の方やその御家族が地域で安心して暮らしていただくためには、地域住民の方の御理解や見守りなどの支えが不可欠でございますので、県では、議員お示しのとおり、平成十九年度から四年間にわたり、認知症地域資源活用モデル事業、これを実施してまいりました。
今年度でこのモデル事業は終了いたしますが、来年度は、この事業成果を県内に広めるために、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業、これを活用いたしまして、各市町村で地域の方々が中心となって認知症高齢者を温かく見守り、声かけ、手助けができる地域づくりや、徘回高齢者を迅速に捜索する体制の構築に取り組んでいただくことといたしております。
そのために、県では、学識経験者や福祉介護の関係者などによる推進会議を設置いたしまして、市町村の取り組みへの支援や徘回高齢者の捜索など、市町村域を超えるケースについての調整、支援を行っていくことといたしております。
なお、こうした地域づくりのためには、地域で認知症の方やその御家族の気持ちを理解し、状況に応じた支援を行う方々の育成が重要でございますので、このような役割を担っていただく認知症サポーターの養成に、市町村とともに取り組んできているところでございます。
今後は、認知症の方と接する機会の多い商店や金融機関で接客業務に携わる方々にさらに御参加をいただくなど、認知症サポーターの養成に、より一層力を注いでまいることといたしております。
認知症疾患医療センターについてお答えをいたします。
まず、国立長寿医療研究センターにおける具体的な取り組みについてでございます。
国立長寿医療研究センターは、国内でも有数の認知症医療提供機能を有するとともに、従来から本県においてかかりつけ医に助言や支援を行うサポート医の養成を行っていただいておりますことから、このたび、認知症の専門医療の拠点である認知症疾患医療センターに指定することにいたしました。
具体的には、認知症の確定診断や重症患者の治療に加えて、地域のかかりつけ医との連携強化や認知症に関するさまざまな相談窓口の設置、さらには、地域の介護・保健医療関係者への研修などを行っていただくことにいたしております。
次に、この事業の効果についてであります。
認知症は、記憶力や判断力が低下し、みずからの症状に自覚がないことから、早期の発見や適切な治療が行われにくいと、そのように言われております。
今回、認知症疾患医療センターを核とした医療連携のネットワークを構築することによりまして、認知症の早期確定診断とその後の幻覚や妄想などの周辺症状に対する治療を含めた専門医療を提供する体制が整いますとともに、認知症に関する介護施設等における技術的支援も行われることになります。
この取り組みによりまして、認知症の患者さんにとりまして、在宅でのケアや医療機関での治療、介護施設の利用といったさまざまな場面での包括的なケア体制の構築につながっていくものと、そのように考えております。
進行いたします。
鈴木純議員。
通告に従いまして、歳出第六款健康福祉費第一項健康福祉総務費のうち、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金事業についてお伺いいたします。
これまで愛知県議会では、子宮頸がんの予防対策の推進についての意見書や、細菌性髄膜炎予防のためのワクチンの定期接種化についての意見書などを国へ提出してまいりました。
私も、昨年の二月に、厚生労働省のがん対策推進室などで節目検診の無料クーポンや、日本型の新薬開発等について、政務調査を行ったところであります。
また、大村新知事のマニフェストの中にも、ヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がんなどのワクチン予防接種の公費助成の創設がうたわれております。
子宮頸がんにより亡くなる方は、全国で年間二千五百人前後、本県でも百人以上の方が亡くなっています。また、二十代、三十代のいわゆる出産世代にも発生するがんであり、進行すると子宮全摘出を余儀なくされることもあることから、次世代を担う子供の喪失など、社会的な観点からも大きな損失となるがんであると言われています。
細菌性髄膜炎は、ヒブと呼ばれるインフルエンザ菌b型や、肺炎球菌の感染などが発症の主な原因と言われていますが、五歳未満の子供ではだれしも等しく起こる可能性があることから、子育て中の親にとっては大きな不安材料であり、実際、乳幼児に重い後遺症を引き起こし、死亡のおそれが高い重篤な感染症であります。また、通常、集中治療によっても二から五%が死亡し、親の心理的な問題もあり、小児救急医療を担う現場にとっても大きな負担となっています。
国の補正予算を受け、昨年の十一月末から開始された子宮頸がん等ワクチンの接種事業は、これらの病気を予防する上で有効性が高いと言われている三つのワクチン、すなわち、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種を推進するために実施されているものであります。
なお、先ごろ、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンを含むワクチン同時接種後の死亡例が四例報告され、また、きょうの新聞報道では五例目の報告がなされています。現在、国は、因果関係の評価を実施するまでの間、念のため接種を一時的に見合わせていると伺っております。
事業の内容を見てみますと、国は、子宮頸がん予防ワクチンについては基準額一万五千九百三十九円、ヒブワクチンは八千八百五十二円、小児用肺炎球菌ワクチンは一万一千二百六十七円に、対象人口、接種回数〇・九の計数を掛けて予算を算出しています。
制度としては、各市町村の助成額の二分の一を基金から補助するもので、例えば県と市町村の合計の助成額が国の基準額の半分にも満たない少額の自治体に対しても、県の補助は二分の一の定率となっております。
県内では、既に名古屋市を初め八市町村が何らかの独自助成を実施していましたが、新規事業導入後の今年度助成を実施している自治体は四十二市町村となっております。大変怖い病気でありますが、ワクチンによりかなりのリスク低減が図られているわけであります。ただ、予防という点では発症していないため、実際に健康な状態でありますので、接種を受けていただくためには、啓発と十分なインセンティブが必要であります。
今回の事業により、これまで任意で行われてきた予防接種に対し、費用について無償化等が図られ、大人になっていく女性の皆さんや生まれてきた子供たちみんなに接種を受けていただけたらと心より願うものであります。
そこでお伺いします。
今回の子宮頸がん等ワクチンの接種事業について、二十三年度は県内の全市町村が実施するとのことです。しかし、接種対象年齢や被接種者の自己負担の有無について市町村により差が生じていると聞きますが、その実態についてお伺いをいたします。
次に、このように市町村によって接種事業に差異が生じている実態について、県はどのように考えているのかお伺いをいたします。
最後に、今回の三つのワクチンについて、国は、二十四年度から予防接種法に基づく定期接種の対象とする意向と聞いています。そうした場合は、今以上に市町村の財政負担がふえるのではないかと危惧していますが、そのような場合、市町村の負担を軽減すべきと考えますが、県としてのお考えをお伺いします。
以上です。
子宮頸がん等ワクチン接種事業についてお答えをいたします。
まず、この事業の市町村による違いの実態についてのお尋ねでございます。
今回の接種事業について、接種対象年齢に制限を設けている市町村は四団体でございます。この四団体は、いずれも子宮頸がん予防ワクチンについて、国が中学一年生から高校一年生までの四学年の女子を対象と範囲を示しているところを、二学年または三学年に設定しているものであります。
また、自己負担につきましては、ない市町村が三十二団体、ある市町村が二十二団体でございまして、その負担額は一回について、子宮頸がん予防ワクチンが千円から約一万円、ヒブワクチンが八百円から約六千円、肺炎球菌ワクチンが千円から約八千円と、このようになっております。
次に、市町村における接種事業の差異についてどう考えるのかとのお尋ねでございます。
今回の接種事業は市町村の事務として行われておりまして、一つには、接種料金を地域の医療機関との契約で決め、地域の状況に応じて対象年齢や自己負担の金額が定められる、そのような仕組みとなっておりますこと、また、二つ目には、接種料金の大半を占めるワクチン価格が高いことが自己負担を求める要因の一つとなっていることなどによりまして、差異が生じているものと考えております。
最後に、平成二十四年度から見直しが予定されております予防接種制度に対する県の考え方でございます。
平成二十四年度からの予防接種のあり方につきましては、現在、厚生科学審議会の予防接種部会でおたふく風邪ワクチンなど、他の任意予防接種も含めて定期接種の対象とすることが検討されております。
現行の予防接種法の枠組みでは、定期接種は市町村の自治事務であり、対象となるワクチンがふえれば市町村の財政負担もふえることになります。このため、国におきましては、予防接種事業を持続可能な仕組みとするよう、恒久的な財源確保のあり方についてもあわせて検討を進めていると伺っております。
県といたしましては、この動きを注視しつつ、情報収集に努めますとともに、国に対し、地方に十分な財政措置を講じるよう要望してまいりたいと、そのように考えております。
御答弁をいただきました。私から少し要望だけさせていただきたいと思います。
まず最初に、市町村の格差についてでありますけれども、やはりかなり大きな開きがあるということで、せっかくインセンティブをつけてワクチン接種をお願いするというときに、一回の自己負担が一万円を超える、子宮頸がんですと三回やらなければいけないわけですから、大変大きな負担になっております。
県としては、市町村の半分しか補助ができないという、要綱で決まっているとお伺いいたしましたけれども、これから二十四年度、どうなるかわかりませんが、やはり各市町村の実態をしっかりと国にお伝えをいただいて、これだけ格差がある場合、何らかの要綱の見直しでありますとか、そういったことにも踏み込んでいただければと思います。
それから、二点目に、子宮頸がんのワクチンのほうでありますけれども、お伺いしたところ、大体安定的に供給される見通しが、六月から七月ぐらいまで、ちょっと不安定な状況が続くのではないかということでありますので、既に国のほうから三月七日付の事務連絡ということで、その対応について方針が示されているということでありますが、これから要綱等がしっかりと出てくると思いますが、そういった部分については、しっかり県として各市町村に通達をいただき、また、市町村の要望等については、局長も入っていらっしゃる全国衛生部長会等で国のほうにしっかりお伝えをいただいているということはお伺いをいたしておりますが、大変タイムラグが生ずるといろいろな不具合が生じてきますので、できるだけ速やかにこのような対策をとっていただくようお願いしたいと思います。
それから、三点目が小児用肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンを含む同時接種の死亡報告でありますけれども、大変残念な結果であります。心からお悔やみを申し上げるところでありますが、本日、専門会議が開かれるということを聞いておりますのでその内容も速やかに調査をいただいて、これから新年度を迎えますので、各市町村が混乱しないように、県としてもできるだけの力を発揮していただきますよう要望いたしまして、発言を終わります。
進行いたします。
伊藤辰夫議員。
歳出第七款産業労働費第二項商工業振興費のうち、商店街振興費のがんばる商店街推進事業費について質問します。
かつて商店街は、日々の買い物の場としてだけではなく、地域の人と人とが触れ合う憩いの場として機能してまいりました。しかし、最近では、多様でかつ変化の早い消費者ニーズへの対応や、厳しい価格競争、また、インターネットを利用した商取引の普及、さらにはモータリゼーションの進展とあわせた大規模小売店舗の郊外出店などの影響を受け、多くの商店街で空き店舗が増加するなど、大変厳しい状況にあります。
そこで、商店街が再生するには、地域住民のニーズをとらえ直し、地域コミュニティーとしてにぎわいを取り戻していくことが期待されていると思います。
こうした中、私の地元の笠寺観音商店街では、県のがんばる商店街推進事業費補助金を活用し、暮らしとにぎわい事業として、笠寺が好きという人が集まったまちづくり組織であるかんでらmonzen亭や、大学あるいは高校とも連携したファッションショーを初めとするさまざまなイベントを開催するとともに、LEDライトを使った明りの装飾を施し、華やかで安全なまちづくりに取り組むなど、他の商店街の模範となるような活動を行ってまいりました。
また、柴田商店街でも、この補助金を活用し、ふれあい・にぎわい創出事業として、伝統芸能である能を活用したイベントの開催や、飲食店マップの作成、各店舗をLEDイルミネーションで装飾するイルミネーションコンテストなどの活動を実施しました。
これらの商店街では、さまざまな活動を通じて、地域住民を初め多くの人がもう一度商店街に足を運び、買い物をし、人と触れ合う機会がつくり出されており、県内の他の商店街でも同様の前向きな取り組みが期待されます。
そのような取り組みが直ちに来街者の増加や個店の売り上げの増加に結びつくものではないことは承知しておりますが、商店街自身がやる気を出さなければ、再生の道は開かれません。県には、そのやる気を引き出すよう粘り強く商店街振興施策に取り組んでいただくことを期待いたします。
そこでお伺いします。
県内の多くの商店街や市町が期待するがんばる商店街推進事業費補助金を今後どのように展開されていくのか伺います。
がんばる商店街推進事業費補助金の今後の展開についてお答え申し上げます。
この補助制度は、市町村がまちづくりの観点から行う商店街支援の取り組みに対して助成するものでありまして、これまでに延べ四十四市町の三百五十九の事業に対し、助成をいたしております。
助成を受けた多くの市町からは、顧客の利便性が向上した、あるいは商店街の知名度が上がったなどの声をお聞かせいただいているところでございまして、支援の対象となった商店街の中には、来街者数がふえた商店街もございます。
このように、この補助制度は、総じて厳しい状況にある商店街の活性化に一定の貢献をしておりまして、県といたしましては、引き続きこれを活用した支援に取り組んでいく必要があるものと考えております。
県では、現在、商店街関係者、まちづくりの専門家、NPOなど幅広い有識者で構成する委員会を設置し、今後五年間の商店街振興の基本方針を示す新・あいち商店街アクションプランの策定を進めているところでございます。委員会での審議や、広く県民を対象としたパブリックコメントの過程では、商店街に対し、少子・高齢化の進展を踏まえた子育て支援や、高齢者の買い物支援といった地域コミュニティーの担い手としての新たな役割を期待するといった御意見をいただきました。
県といたしましては、こうした御意見も踏まえ、今後取りまとめるアクションプランに沿って補助制度の見直し、あるいは充実に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
暫時休憩されたいという動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
大見正議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、暫時休憩いたします。
午前十一時二十六分休憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
通告により質問を許可いたします。
渡会克明議員。
私からは、歳出第八款農林水産費第一項農業総務費についてお伺いをいたします。
私は、本県が世界に誇れる魅力ある農林水産業を目指すことが、元気な愛知、豊かな愛知づくりになると信じております。農林水産業に対する適切な国の政策が進まない中、本県の農林水産業の再生、発展のためには、全庁レベルでの取り組みが不可欠であります。
そこで、今回は、農業総合試験場、水産試験場など、試験研究機関の研究開発が特に重要であるとの観点から、その取り組みについてお尋ねをいたします。
近年、消費者の農林水産物への関心や要求が安全・安心にとどまらす、ライフスタイルの変化とともに多様化をしています。さらには、経済情勢の停滞や、安価な農林水産物の輸入に伴う販売価格の低迷、燃油、肥料を初めとした生産資材価格の高どまり等により、農林水産業経営は大きく圧迫され、農産漁村には閉塞感が漂っております。
さらに、昨年夏の異常高温や、年末から続いた厳しい寒さなど、地球温暖化の影響かとも心配される気象変動により、生産物の品質や生産性の低下が大変心配をされています。このように、農林水産業を取り巻く情勢はかつてない厳しさに置かれております。
しかし、今やらねばならないことは、若い農林漁家の皆さんが将来に向かって夢と意欲を持って取り組めるようにすることであります。そのために、新たな品種や技術などの研究開発を行い、商品力や生産性を向上させ、国内外の競争に打ち勝つことのできる愛知ブランドを確立していくことが今こそ求められていると考えます。
農業総合試験場や水産試験場など本県の試験研究機関では、全国に先駆けて、大学や民間との共同研究に取り組み、他の産業分野の幅広いノウハウを結集した農工連携研究の促進など、研究開発の一層の効率化が図られています。
その一方で、国際的にも、アフリカにおける稲作の改善に名古屋大学との共同研究で取り組むなど、海外との交流を通して、その先端技術や遺伝資源を本県における研究に活用できるよう、積極的に取り組まれているとお伺いをいたしております。
また、本県が保有している知的財産権の収入額のうち、約八割が農業総合試験場など、農林水産分野の研究機関が開発をした品種や特許が占めているとのことで、大変頼もしく思っているところであります。
私の地元の豊橋市では、特産のアオジソ栽培に農業総合試験場が開発した新品種が既に四割も導入をされており、病気に強い上、冬場の低温にも強く、省エネにも効果的であると評判も上々であります。
また、これを素材にした農商工連携の取り組みによりさまざまな新商品が誕生しており、地域の活性化にもつながっています。
さらに、水産業におきましては、地球温暖化に対応し、高水温でも収穫量が多く、色調の濃いノリの新品種あゆち黒吉を愛知県漁業協同組合連合会と共同で開発されたとのことであります。
このように、これまでも農業総合試験場や水産試験場などで開発された研究成果が現場において大いに利用され、活用されておりますが、国内及び海外に農林水産物の愛知ブランドを確立し、農林水産業を成長産業として育成するためには、研究開発並びに本県独自の農林水産知的財産の確保と活用を強力に推進する必要があると考えます。
そこでお伺いいたします。
県として、今後、成長戦略としての産業振興の角度から試験研究機能をより一層強化する必要があると考えますが、御所見をお伺いいたします。
以上です。
農林水産業振興のための試験研究機能の強化についてお答えいたします。
農林水産業を成長産業として育成していくためには、新たな品種や革新的技術などの開発を推進していくことが大変重要であると認識しております。これまでにも農業総合試験場では、LEDを活用した良質な花の生産技術や、重油消費量を最大七割削減できる施設園芸の冷暖房技術を、水産試験場では放流するトラフグ稚魚を増産する技術など、成長のもととなる革新的な技術開発を行ってまいりました。
また、研究成果は、県の知的財産として権利化に努めておりまして、今年度は、吟醸酒に向く酒米や、色鮮やかでおいしいミカンなどの新品種を完成し、農林水産省に登録出願を行っており、現在、出願中のものも含め、特許権十八件、意匠権一件、品種の権利であります育成者権三十八件を保有し、これら知的財産権を有効に活用して、愛知ブランドの確立に向けて力を注いでいるところでございます。
試験研究機能の強化につきましては、現在、平成二十七年度を目標年度とした農林水産業の試験研究基本計画の改定を進めており、これまで推進してきた大学や民間との共同研究に加えまして、知の拠点や農林水産以外の分野とも連携した先端的な研究開発を促進するなど、一層の重点化と効率化を図り、今後も新品種、新技術の開発に努めてまいります。
以上でございます。
私からは、歳出第六款健康福祉費第一項健康福祉総務費のうち、子宮頸がん対策について質問いたします。
先日、名古屋市立の中学校に通う私の娘が一通のペーパーを学校から持って帰ってきました。それは、子宮頸がんワクチン接種に関しての希望調書でありました。
子宮頸がんについては、今まで何度かこの議場でも議論されたこともありますし、私なりにも調査をしたりしてそれなりの知識がありました。
まず、子宮頸がんは、原因となるヒトパピローマウイルスに感染しても、多くの場合は自然治癒したり、例え子宮頸がんに発展しても、早期に発見さえすれば、手術により治療でき、妊娠することも可能であるということ。ですが、発見がおくれると、世界の女性のがんの中で死亡率は第三位と言われている大変恐ろしいがんであるということ。また、ヒトパピローマウイルスの高リスク型ウイルスは十三種類あって、今回の二価ワクチンでは、十六型と十八型しか予防することができず、日本人の子宮頸がんウイルスの約六〇%しか防げないということであります。
そしてまた、ワクチンは、最長で約六・四年間しか感染の予防ができないことであります。ですから、もし一〇〇%の方がこのワクチンを接種していただいたとしても、ヒトパピローマウイルスの六〇%程度にしか効果がないわけですから、子宮頸がんの撲滅には、ワクチンの接種とあわせて、検診受診率の向上を図ることが大変重要だというふうに考えております。
そこで、まず、ワクチンの接種についてでありますが、市町村によりばらつきがありますが、今回の事業により、ワクチンの接種を希望する方の経済的な負担を軽減し、気軽に接種できるようにするものですから、大変に有用な施策であるというふうに考えております。
また、今回のこの事業によって、県民の皆様の子宮頸がんに対する意識は飛躍的に高まると考えておりますが、この機を逃さずに、正確な情報を県民の皆様にお伝えできるよう、徹底した啓蒙活動を進めていくべきだと考えております。
お伺いいたしますが、現在までの子宮頸がん検診の普及啓発に関しての状況、そして、今後どのような普及啓発活動をされていくのか、健康福祉部のお考えをお聞きいたします。
先ほども申し上げましたが、子宮頸がんは、早期に発見さえすれば手術で治療でき、その後は妊娠も可能であります。どのようながんについても言えることですが、早期発見が何より肝要なわけでありますが、がん患者団体の方の話によりますと、子宮頸がん検診の検査方法については、細胞診検査のほかに、最近では、HPV─DNA検査も注目されているということであります。
このHPV─DNA検査は、家庭で自己採取し、郵送による検診を行うものでありますが、この検査により、郵送検診が可能となれば、だれもが検診を気軽に受けることができるようになると思います。しかし、このHPV─DNA検査の今後の動向、国や研究機関での検証や評価を今後も期待を持って注意深く見ていかなければならないと考えておりますので、その点はまずどうぞよろしくお願いをいたします。
さて、現状では、県としては、国が推奨するオーソドックスな子宮頸がん検診などの対策を着実に推進していくこととなるわけですが、欧米では約八〇%と言われている検診率は、我が国では約二〇%ほどと推計され、極めて低いのが現状であります。折しも、昨年度から子宮頸がんの検診が、年齢の定めがありますが、対象者にクーポン券などが配布され、無料で受けられる事業が県内全市町村で始まっております。
そこでお尋ねいたしますが、県は、がん対策推進計画において、平成二十四年度までに検診率を五〇%までに上げるという目標を掲げておられますが、この無料クーポン券事業の効果はどのようになっているのかお伺いをいたします。
子宮頸がん対策のお尋ねのうち、まず、子宮頸がん検診の受診率向上に向けた普及啓発についてお答えいたします。
子宮頸がん対策といたしましては、ワクチン接種に加え、検診を定期的に受診することが大変重要でございまして、一定の年齢になれば必ずがん検診を受けるという社会機運を県民全体の中で高めていく必要があると考えております。
本県では、従来から国のがん検診受診率五〇%達成に向けた集中キャンペーンにあわせまして、行政による啓発活動だけではなく、地域社会の重要な構成員でありますNPO、企業などと共同して、がんシンポジウムの開催や、連携企業でのレシートへの啓発メッセージの掲載、さらには、連携企業とともに街頭で啓発資材を配布するなどの啓発に努めております。
来年度におきましては、これらに加え、がん検診の必要性を啓発するため、検診へ行こうキャンペーンなどの実施を予定しており、特に若い世代に対する効果的な啓発を行うことによりまして、一層の受診率の向上を図ってまいりたいと考えております。
次に、子宮頸がん無料クーポン券事業の効果についてでございます。無料クーポン券事業につきましては、検診を受けたことがない方が初めて検診を受けるよいきっかけとなる重要な施策でありますことから、市町村に対し円滑に実施できるよう支援してまいったところであります。
お尋ねの無料クーポン券事業の効果でありますが、平成二十年度と事業を実施しました二十一年度の受診率を比較いたしますと、例えば対象年齢を含む二十歳から二十四歳の方では五・九ポイントの増加が見られ、それ以外の対象の二十五歳から四十四歳までの方は、一〇ポイント以上の増加が認められております。これに対し、対象年齢ではない四十五歳以上の方には増加が見られないことを勘案いたしますと、無料クーポン券事業の効果は明らかであり、今後の検診受診率の向上が期待できるところでございます。
通告に従いまして、質問をいたします。歳出第八款農林水産費第四項農業用水費のうち、愛知用水事業について質問をさせていただきます。
愛知用水は、昭和三十六年九月三十日の通水開始からことしで五十周年を迎えます。愛知用水が来る以前、私の地元の南知多町師崎では、水源は数少ない共同井戸であったために、慢性的な水不足に悩まされておりました。まだ子供であった私は、その井戸に行列をつくって水をくみ、家まで運び、水がめにためるという大変な作業が日課になっていたことを記憶いたしております。五十年前、私が十九歳のとき、水道の蛇口から初めて愛知用水の水が出たときの感激を今でも忘れることができません。
また、愛知用水は、生活水準の向上という面だけではなく、産業においても大きな恩恵をもたらしております。農業用水については、通水が始まると効果はたちまちあらわれました。水田では、雨やため池だけに頼っていたときに比べ、十分に水を使えるようになったため、一反当たり五俵程度しかとれなかった米の収量は、現在では安定して八俵程度とれるようになりました。ひどい干ばつの際には二俵もとれない年もありましたので、その効果は絶大であったと言えます。また、畑では、ミカンの栽培が盛んになり、愛知用水はオレンジ運河とも呼ばれておりました。
さらに、南知多町では、昭和五十一年から国営農地開発事業により三百ヘクタールを超す畑地が造成され、花卉や野菜など高収入な作物が作付できるようになりましたが、それも愛知用水の水があるからこそ実現したものであります。
一方、工業用水についても、愛知用水の水が工場誘致の呼び水となり、名古屋港臨海部へ新日鉄や大同製鋼などの大企業が相次いで進出をし、今やこの地域は中京圏工業地帯の中核をなすまで飛躍的な発展を遂げております。
そこでお尋ねをいたします。
この五十年間に愛知用水が果たしてきた功績について、県はどのように評価をしておられるのかお伺いをいたします。
次に、愛知用水に対する私の思いを述べさせていただきますとともに、私と同じ年である、あるいはそれよりも年配の方は、常に水の恵みはもとより、愛知用水をつくっていただいた先人の御努力や、その偉業に心から深く感謝をいたしております。
しかし、今日、愛知用水が通水をし、昭和三十六年以後に生まれた人たちが大半を占め、蛇口をひねれば水が出るようになっておりますので、水の恩恵に対する感謝の念は大変希薄化しているのではないかと強く感じております。
思い起こせば、平成六年の大渇水では、この地域の多くの人々が長時間の断水を経験したにもかかわらず、のど元過ぎれば熱さを忘れると申しますか、いつの間にか水はあるのが当たり前との認識に戻ってしまっているようであります。
ましてや、平成六年の断水を経験していない年代は、既に高校生になっております。未来を担う世代が、このように愛知用水のありがたさを全くと言っていいほど感じていないことは、非常にゆゆしき事態と言わざるを得ません。
こうした中、昨年十月、南知多町先端の師崎港から長野県の大滝村にある愛知用水の水源、牧尾ダムまで約二百キロの道のりをのぼりを掲げ、延べ八日間かけて歩く愛知用水人の旅が行われたと新聞で知りました。これは、愛知用水土地改良区が呼びかけ人となり、愛知用水や水源地への思いを再認識しようと、愛知県や水源機構の関係者など、延べ百三人が参加をしたと聞いております。
また、南知多町は、愛知用水と同じく、ことし町制五十周年を迎え、五月下旬から記念行事を予定しております。その中、愛知用水に関する展示なども行うと聞いております。これは、南知多町の発展に愛知用水は欠かせないものであり、愛知用水への感謝の念を次の世代につなげていこうという思いから実施されるものと聞いております。
こうしたことを初めとして、愛知用水の受益市町村や土地改良区、上水道、工業用水道の受水団体では、通水五十周年を機に、愛知用水への感謝の念をいま一度確認するとともに、地域の方々一人一人に対しても、愛知用水の重要性、水源地からの恵みをしっかりと伝えていきたいとの機運が、大いに高まっておるところであります。
そこでお尋ねをいたします。
愛知用水通水五十周年という記念すべき年を迎えるに当たって、県としてどのような取り組みを考えておられるのかお伺いをいたします。
水源資源の管理について、歳出第八款農林水産費第六項水産業費第二目水産業振興費に関して質問をいたします。
伊勢湾、三河湾は、古来より魚介類の宝庫として知られ、豊かな海や川の恵みを享受してまいりました。現在でも、本県は多くの魚種で全国有数の産地であり、平成二十年には海面漁業、養殖業の生産量はおよそ十一万トンで全国第十四位であるものの、漁業種類別では船引き網漁業による漁獲量が全国第一位、魚種別では、シラス、アサリ類の漁獲量が全国第一位となるなど、沿岸区を中心に特色ある水産業が営まれております。
水産業は、良質で多様な水産物の安定供給を通して、健康で豊かな県民の食生活に貢献をいたしており、食の安全性への関心が高まる昨今では、新鮮で安全・安心な水産物を食卓へ届ける役割を担う本県水産業の役割は一層高まっていると思います。
しかし、海の魚はだれのものでもないことから、昔から、親のかたきと魚は見つけたらとれと言われ、漁業者は、とり過ぎるから減るとわかっていても、人にとられるくらいならとってしまえになりがちです。
しかしながら、水産資源は、石油や石炭などの鉱物資源と違って、適切な管理により上手に利用すれば持続的に利用できる再生可能な資源であります。
こうした中、昨年十月に本県で開催されましたCOP10で採択された愛知ターゲットの目標の一つに、二〇二〇年までに水産資源の持続管理により過剰漁獲を避け、生態系などへの漁業の影響を生態学的な安全の範囲に抑えることが規定されております。
そこでお伺いをいたします。
本県では、具体的に水産資源の管理をどのように取り組んでおられるのかお尋ねをいたします。
次に、農林水産省のホームページによりますと、漁業でも来年度から資源管理・漁業所得補償対策が講じられていると記載されております。資源管理・漁業所得補償対策の内容や、本県の役割についてお尋ねをいたします。
以上です。
愛知用水に関するお尋ねのうち、まずこれまでの愛知用水の功績に対する県の評価についてお答えをいたします。
愛知用水は、農業、水道、工業の各部門にまたがる全国初の総合水利開発事業でございまして、いずれの部分においても大きな功績を上げたものと評価をしております。
まず、農業におきましては、愛知用水の通水による安定した水の供給により、水田において、稲の収量を大幅にふやすとともに、畑においては、多種多彩な野菜や果樹、花卉などの作付を可能といたしたところでございます。
また、安定した水源が確保されたことによりまして、議員お示しの国営農地開発事業以外にも、知多半島を中心に約四千四百ヘクタールに及ぶ県営圃場整備事業を初めとする基盤整備事業が計画的に実施され、生産性の飛躍的な向上がもたらされました。
こうした成果を知多半島の農業産出額で見てみますと、愛知用水通水前の昭和三十五年に約五十四億円であったものが、平成十八年には約七・四倍の四百億円程度となっております。
次に、水道用水におきましては、現在、約八十五万人の生活を支えるライフラインとなっておりまして、この地域が名古屋市近郊のベッドタウンとして、大きく発展する重要な基盤になったものと認識をしております。
また、工業用水におきましても、愛知用水は、水を大量に使う鉄鋼業等の工場誘致を可能とし、名古屋市港区、東海市を初めといたします臨海工業地帯の製造品出荷額を見てみますと、愛知用水通水当時の昭和三十六年に約二千四百億円であったものが、平成二十年には約二十倍の約四兆九千億円と著しい伸びを示しております。
このように、愛知用水で大きな成功をおさめた総合水利開発事業は、その後、豊川用水や木曽川用水、矢作川総合用水等に受け継がれ、物づくり日本一の愛知を支える原動力となるとともに、県土の均衡ある発展に多大の貢献を果たしたものと高く評価しておるところでございます。
次に、愛知用水通水五十周年の取り組みについてお尋ねをいただきました。
世紀の大事業であり、本県発展の原動力となった愛知用水につきましては、建設に携われた先人たちの偉業をたたえ、水源地域の方々に感謝するとともに、未来を託す若者たちに愛知用水に関する正しい理解と、感謝の念をしっかりと引き継いでいくことが私どもに課せられた重大な使命であると考えております。
通水五十周年を迎える本年は、そうした取り組みを展開する絶好の機会でございますので、農業、水道、工業の各用水の受水団体や、管理者であります水資源機構、あるいは関係市町、本県及び岐阜県が連携をいたしまして、より効果的な記念事業を展開すべく、九月下旬の記念式典を初めとしまして、幾つかの企画案を持ちより、現在、検討、調整を進めているところでございます。
議員お示しのとおり、若年層を中心に、水の恩恵に対する感謝の念が希薄化している状況が見受けられますので、水源などの施設見学を通じて、愛知用水を直接見たり、触れたりしていただく企画や、テレビ、ラジオなどのメディアを通じた情報の発信に特に力を注いでまいりたいと考えております。
県といたしましては、地域の方々一人一人が愛知用水の重要性や水源地からの恵みを、しっかりと認識をし、愛知用水への感謝の念をいま一度思い起こしていただけるよう、通水五十周年の記念事業に受水団体、関係機関ともども取り組んでまいる所存でございます。
水産資源の管理に関しまして、二点御質問をいただきました。
まず、水産資源の管理についての具体的な取り組みについてでございます。
取り組みの一例といたしましては、小さな魚を保護するため、トラフグでは、七百グラム未満のものを海に戻すことや、アナゴでは、網の目を大きくすることで全長二十五センチメートル以下のものはとらない工夫、また、シャコでは、産卵前の親を保護するため、漁獲量の制限を行っております。さらに、全国的に優良な事例として常に取り上げられておりますイカナゴでは、関係漁業者が水産試験場の調査結果をもとに話し合い、一定の大きさ以上になってから漁獲を開始し、翌年の親として二十億尾以上を必ず残すことにより、資源の確保に努めております。なお、この愛知のイカナゴ漁業は、昨年三月、水産資源の保護と生態系の保全に積極的に取り組んでいる漁業であることの証である水産エコラベル認証を全国で四番目に受けたところであります。
今後とも、さらに多くの水産資源について、必要な調査や漁業者との協議等を進めてまいります。
次に、資源管理・漁業所得補償対策についてでございます。
来年度から国が始める資源管理・漁業所得補償対策の内容につきましては、漁業共済制度を活用いたしまして、計画的に資源管理に取り組む漁業者に対しましてのみ、漁業共済掛金の負担を軽減するというものでございます。
また、本県の役割でございますが、計画的に資源管理に取り組む漁業者のために、まず、県の資源管理の方針となる愛知県資源管理指針を策定し、その指針に従って漁業者が作成する資源管理計画についての指導や取り組みの評価を行うこととなっております。このような取り組みによりまして、水産資源の管理の推進や、漁業所得の安定を図ってまいります。
以上でございます。
農地・水・環境保全向上対策事業の今後のあり方についてのお尋ねでございます。
議員お示しのとおり、国におきましては、本事業の対策期間を平成十九年度から二十三年度までの五カ年としております。こうした中、対策期間の中間年に当たります昨年度、国、県が実施した中間評価では、多数の活動組織から、用排水路の管理が行き届くようになり、用水供給や排水機能に問題がなくなった、あるいは地域の景観が向上した、地域コミュニティーが活性化されたなどの声が寄せられ、農地・農業用水や地域の環境保全に大きく貢献しているとの高い評価結果が得られたところでございます。
また、県は、すぐれた取り組みを行った活動組織を表彰し、その内容を紹介する農地・水・環境の集いを毎年開催しておりまして、活動組織間の情報交換を促進するとともに、本事業に対する県民の皆様の理解を深めていただくよう努めているところでございます。
こうした機会には、活動組織の熱心さや、メンバー間のつながりの深さなどに直接触れることができ、事業開始から四年目を迎え、地域ぐるみの取り組みがようやく根づいてきていることを認識しているところでございます。
さらに、本事業における平成二十三年度の政府予算案におきましては、これまで支援をしてきました保全活動に加え、老朽化が進む用排水路などの小規模な補修、更新に対して支援を行う制度拡充が盛り込まれておりまして、これは、議員お示しの末端施設の長寿命化対策という課題にまさに対応できる内容に改善される予定となっております。
県といたしましては、このように貴重な地域資源の保全に大きな効果を発揮し、地域のきずなを深める本事業におきまして、平成二十四年度以降も継続するよう、国に対し強く働きかけていきますとともに、拡充される長寿命化対策についての活動組織の取り組みに対しましても、積極的に支援してまいりたいと考えております。
以上でございます。
私からは、歳出第九款建設費第九項住宅費についてお伺いをいたします。
県営住宅は、昨今の不安定な経済状況もあり、最近は、募集倍率も平均で十倍を超えるような状況になっております。愛知県では、現在二百九十八住宅、約六万戸の県営住宅があり、この多くは高度経済成長期である昭和四十年代から五十年代にかけて、産業構造が大きく変化する中で、農村部から都市部への大規模な人口移動の受け皿として大量に建設されたものであります。この時代に建設された住宅は、県営住宅全体の半分近くを占めており、老朽化が進みつつあります。今後、これらの住宅ストックに対してどのように対応していくかは、公営住宅における大きな課題の一つだと思います。
これら住宅の中には、階段だけでエレベーターがついていないものや、室内が狭小な住宅も多く、本県では、こうした不便で老朽化した住宅を対象に、順次建てかえ工事を行ってきております。
一方、こうした建てかえ事業と並行して、県では、既設住宅の住戸内外の改善を行う既設県営住宅の改善事業にも取り組んでおります。近年では、入居者の高齢化に対応して、エレベーターの設置や、住戸内の段差解消、手すりの設置などを行う高齢者対応改善工事を進めております。私の地元、愛知郡にも五つの県営住宅があります。各住宅でも建てかえや改善工事などがなされておりますが、住宅は日々の暮らしを送る生活の基盤となるものであり、広さや整備などが一定の水準に保たれていることが必要であります。
特に古い住宅は、設備が旧式であったり、床に段差があり、スイッチ類が小さいなど、高齢者には生活しにくいところが少なくありません。しかし、こうした住宅でも、建てかえだけでなく、床の段差がなくなり、手すりがつけば、たとえ古くなったとしても使い続けることができるわけであります。
欧米では、建設されてから百年を超える建物も珍しくありませんが、一方で、日本の住宅は、わずか三十年程度で建てかえが行われております。石づくりと木造建築といった建て方の違いはありますが、鉄筋コンクリートでつくられた県営住宅も、予算の限られる中、スクラップ・アンド・ビルドを続けるのではなく、なるべく長く使い続けていく方向に発想を変えていくことが必要だと思います。
県財政は、引き続き厳しい状況が続く中、国においても公共事業が厳しく削減され、必要な財源を十分確保することが難しい状況下にあります。こうした中で、県が昨年二月に公表した愛知県第五次行革大綱では、県営住宅の効率的な管理運営に関する取り組みで、長寿命化改善を行うことで除去、建てかえ時期を先送りするなど、建てかえ戸数の減少について検討すると記載がなされておりました。
限られた財源を活用し、現在ある住宅ストックを有効利用するという趣旨から、長寿命化改善とは具体的にどのような工事を行うものなのか、また今後どのように進めていくのか、質問させていただきます。